新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?

目次
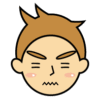
「うんえいししん」ってな~に?
2015年、学童保育で行う支援の内容を具体的に示した「放課後児童クラブ運営指針」(以下「運営指針」)が定められました。
「運営指針」は、その前の年に定められた、「設備運営基準」(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)によって作られました。
現在の学童保育(放課後児童クラブ)は、この「運営指針」と「設備運営基準」に基づいて行われています。

うんえいししんは、学童保育の「心」についての決まりごとなんだよ
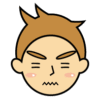
こころ?
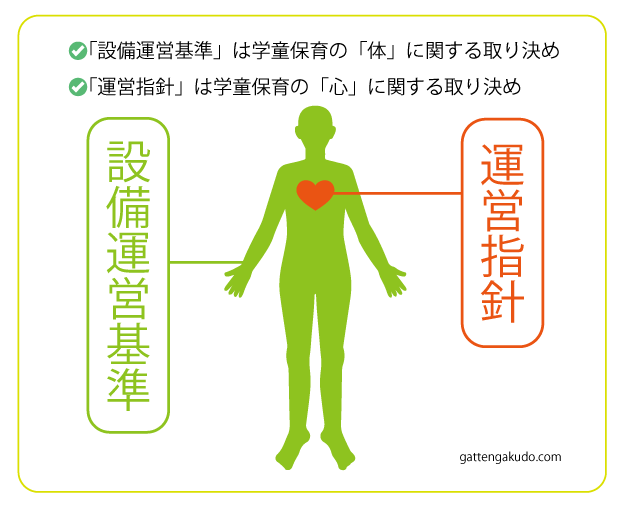
「運営指針」と「設備運営基準」の関係を例えると、運営指針は学童保育の「心」に関する決まり事、「設備運営基準」は学童保育の「体」に関する決まり事、と言えるかもしれません。
どれだけ立派な「体」であっても、「心」が宿っていないと、子ども達が幸せに過ごすことができる学童保育を行えません。

運営指針には、学童保育で大切にすべきことがたくさん書かれています
ところが、この運営指針、全部で17000字以上もあって、とっても長いんです。おまけに、字ばっかり!当たり前ですけどね・・・。

17000字~?
そんな運営指針の、ポイントを図にしてわかりやすく解説しよう!というのがこの記事のテーマです。
運営指針の内容が知りたいけど、忙しくて全部読むのは無理!という人は、この記事内のイラストだけを追ってもらうと、運営指針のポイントが網羅できるようになっています。
こんな人におすすめ!
- 運営指針の概要を知りたい人
- 運営指針のポイントの復習がしたい人
- 長い文書を読む時間がない人
- 放課後児童支援員の仕事が知りたい人

ではさっそく内容を見ていきましょう!

学童保育の「心」を勉強するぞ~!
第1章「総則」
運営指針は全部で7つの章でできており、それぞれの章の内容を簡潔に言うと、以下のようになります。
運営指針の章立て
- 総則
- 子どもの発達
- 育成支援の内容
- 運営
- 学校・地域との連携
- 施設・設備・衛生・安全
- 職場倫理
今回は、第1章「総則」を解説していきます。
「総則」は「前提」という意味です。
第1章には、運営指針の全てにかかわる基本的な考え方と、放課後児童支援員の役割、放課後児童クラブの社会的責任について書かれています。
1.趣旨
第1章-1-(1)
この運営指針は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に基づき、放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童クラブ」という。)における、子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援(以下「育成支援」という。)の内容に関する事項及びこれに関連する事項を定める。
ポイント
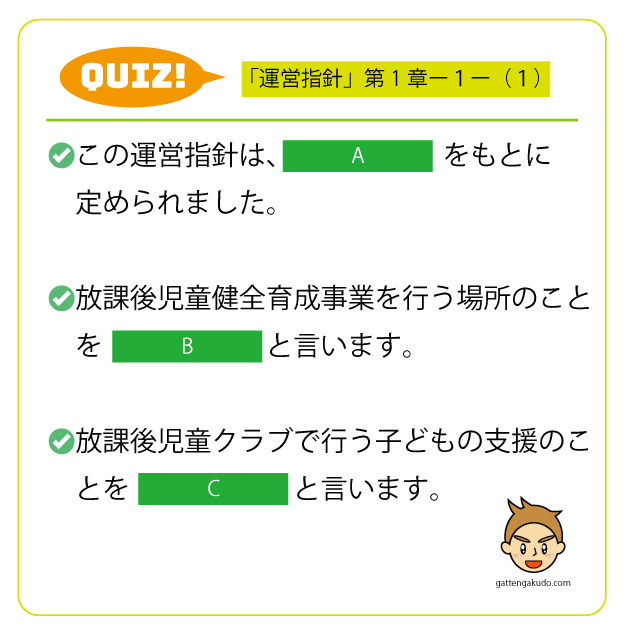
正解:A「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」/B「放課後児童クラブ」/C「育成支援」

解説を飛ばして1章の要点だけを知りたい人は、「次のポイントへ」をクリックしてください
解説
運営指針は、「設備運営基準」に基づいて作られました。
設備運営基準については、こちらの記事にわかりやすくまとめていますので参考にしてください。
こちらもCHECK
-
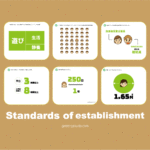
-
【学童保育】「放課後児童クラブの設備運営基準」をイラストでわかりやすく解説
続きを見る
また、設備運営基準や運営指針が誕生した経緯や学童保育制度について知りたい人には、こちらの記事がおすすめです。
こちらもCHECK
-
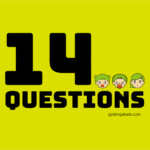
-
【学童保育の制度や関連する施策をクイズ形式で解説】これだけは知っておきたい基本の14問
続きを見る
第1章-1-(2)
放課後児童健全育成事業の運営主体は、この運営指針において規定される支援の内容等に係る基本的な事項を踏まえ、各放課後児童クラブの実態に応じて創意工夫を図り、放課後児童クラブの質の向上と機能の充実に努めなければならない。
ポイント
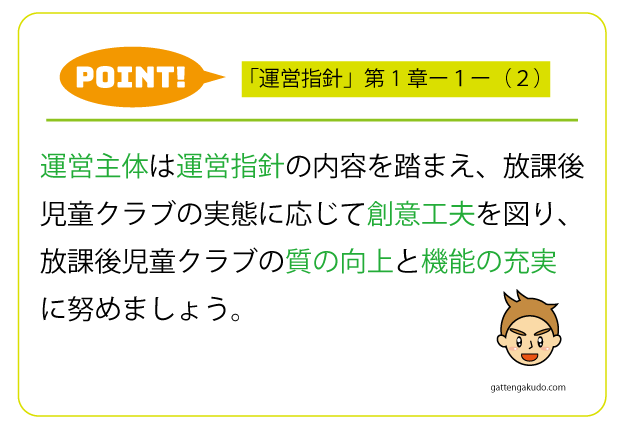
解説
放課後児童クラブの運営主体は、運営指針の内容を踏まえて、子ども達や保護者の実態に応じて工夫をしながら、放課後児童クラブの内容が向上するように努めます。
また、設備運営基準では、運営主体が、最低基準を理由に放課後児童クラブの設備や運営を低下させてはならないとしています。
「運営主体」とは
放課後児童クラブを行う組織や団体のことです。「公営」の放課後児童クラブの場合は、運営主体は市町村です。市町村が運営を「委託」している場合は、法人や企業、父母会などがそれぞれの運営主体ということになります。
2.放課後児童健全育成事業の役割
第1章ー2ー(1)
放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項に基づき、小学校に就学している子ども(特別支援学校の小学部子どもを含む)であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後(「放課後」という)に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業である。
ポイント
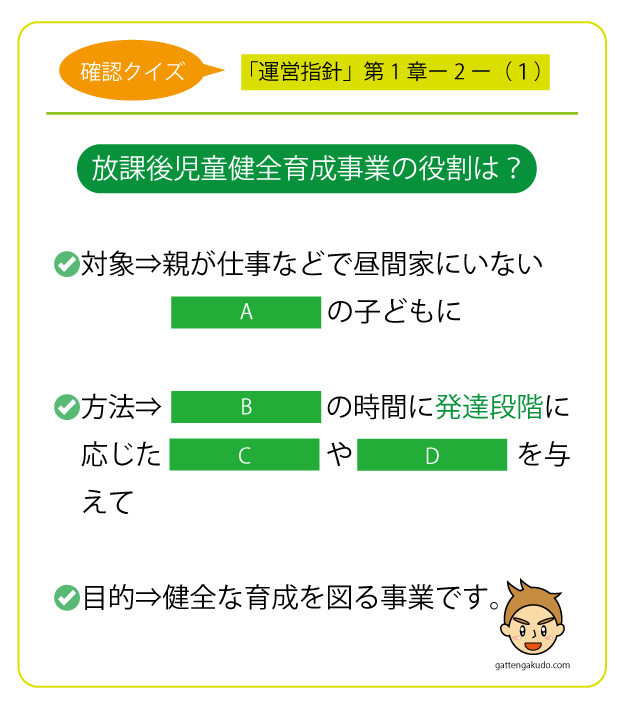
正解:A「小学生」B「放課後」C「遊び」D「生活」
解説
放課後児童健全育成事業の対象となる子どもは、2012年の児童福祉法改正により、「おおむね10歳未満」から「1~6年生まで」となりました。
保護者が働いている場合以外では、病気や介護・看護・障害なども放課後児童クラブを利用することができます。
発達段階とは
子どもが成長し成熟するにつれてたどっていく、身体的・精神的・感情的な段階のことです。
同じ放課後児童クラブに通っていても、1年生と6年生では、体の大きさはもちろん、心の成長や仲間関係・遊びの世界は大きく違います。そんな一人ひとりの状況に合わせて、育成支援を行っていくことが大切です。
第1章ー2ー(2)
放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブは、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進することに努めなければならない。
ポイント
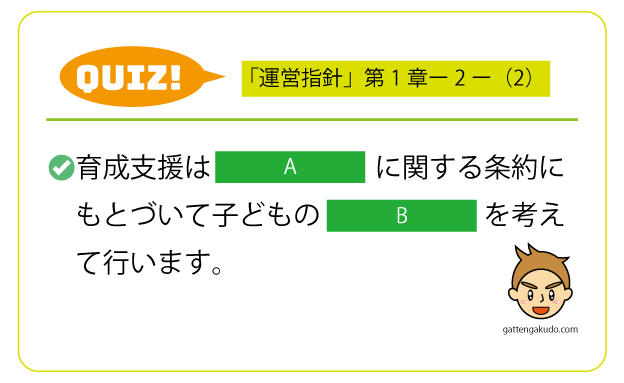
正解:A「児童の権利」B「最善の利益」
解説
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の第3条に、「子どもの最善の利益」が書かれています。
この言葉は、放課後児童支援員等の大人の利益が子どもの利益より優先されてはいけないことの大切さを表しています。
子どもの権利条約については、こちらの記事にまとめていますので参考にしてください。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】子どもの最善の利益って?「子どもの権利条約」を学ぼう
続きを見る
第1章-2-(3)
放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブは、学校や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、その家庭の子育てを支援する役割を担う。
ポイント
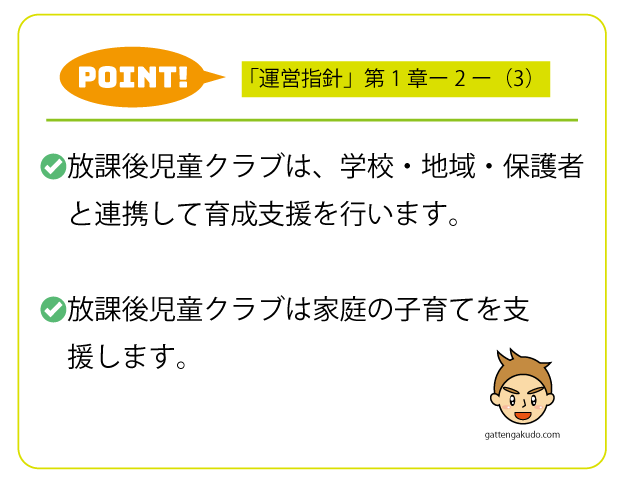
解説
放課後児童クラブは、保護者や学校と連携をしながら子どもの育成支援を行っていきます。
また、地域にある児童館や公民館などの施設や、自治会・町内会・民生委員などの組織とも連携します。
保護者からの相談に対応する時には、必要に応じて地域にある様々な相談窓口や関係機関と連携をしながら、放課後児童クラブに通う子どもの家庭の子育てを支援する役割を担います。
3.放課後児童クラブにおける育成支援の基本
第1章ー3-(1)
放課後児童クラブにおける育成支援
放課後児童クラブにおける育成支援は、子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、子どもの発達段階応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図ることを目的とする。
ポイント
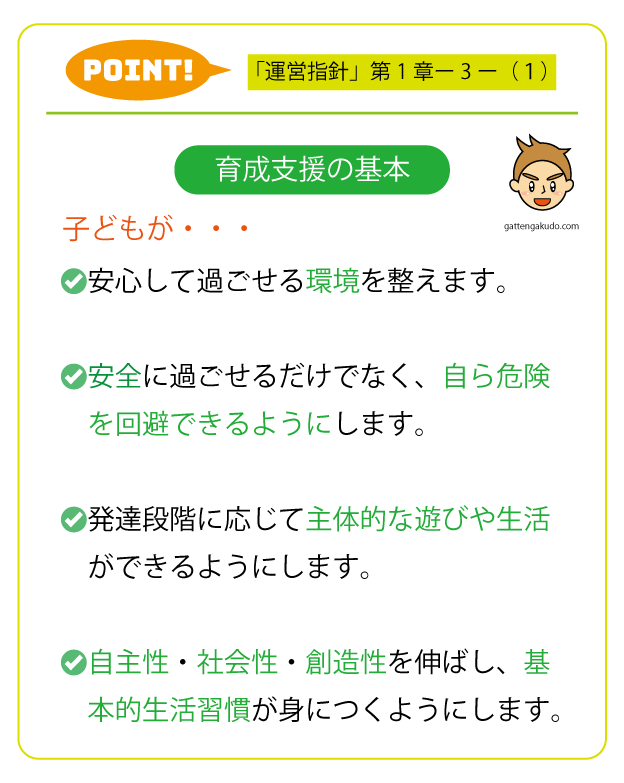
解説
設備運営基準では、放課後児童クラブに、遊び・生活・静養などをするための機能を備えた「専用区画」を設置すると定めています。
子ども達が落ち着いて宿題やおやつなどの生活の営みをしたり、大好きな遊びをしてのびのびと過ごすことができる環境を整えます。
また、放課後児童クラブでは、子どもが安全に過ごせるように配慮しますが、子ども自身が危険に気付いて対処する力を身に付けられるようにしていきます。
放課後児童クラブでは、1年生から6年生までの発達段階の異なる子ども達が共に遊びや生活を行います。
一人ひとりの発達が異なることを踏まえて育成支援を行います。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】「ギャングエイジ」と呼ばれる子どもたち
続きを見る
こちらもCHECK
-
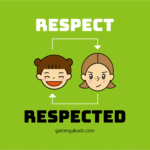
-
【学童保育】下級生と上級生の「憧れ・憧れられる関係」を育むリーダー制について
続きを見る
第1章ー3ー(2)
保護者及び関係機関との連携
放課後児童クラブは、常に保護者と密接な連携をとり、放課後児童クラブにおける子どもの様子を日常的に保護者に伝え、子どもに関する情報を家庭と放課後児童クラブで共有することにより、保護者が安心して子どもを育て、子育てと仕事等を両立できるように支援することが必要である。また、子ども自身への支援と同時に、学校等の関係機関と連携することにより、子どもの生活の基盤である家庭での養育を支援することも必要である。
ポイント
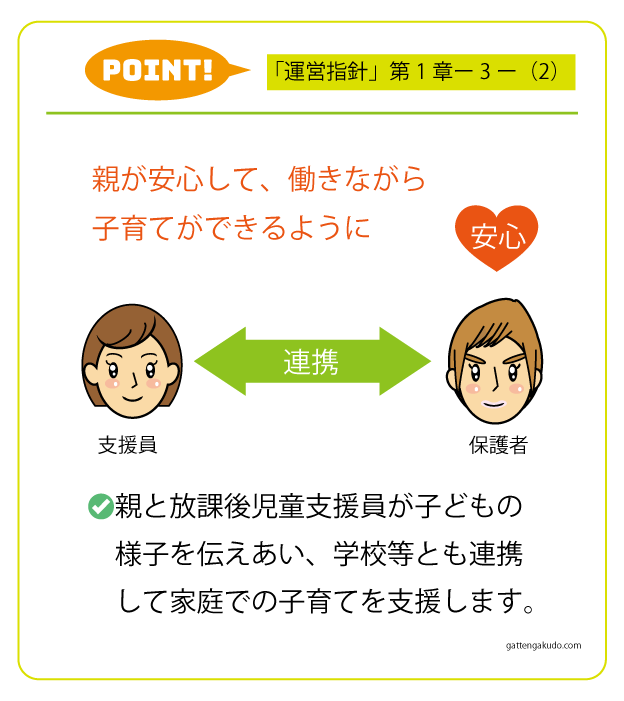
解説
放課後児童クラブでの子どもの様子を、日常的に親に伝えたり、逆に家庭や学校の様子を親から伝えてもらったりして、子どもの情報を家庭と放課後児童クラブで共有することで、親は安心して働き続けることができるようになり、子育てと仕事を両立することができます。
また、親と放課後児童支援員が信頼関係を深めることで、子どもは安心して放課後児童クラブで過ごすことができるようになります。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】「図解でわかりやすい」けがや体調不良・トラブルの対応と家庭への連絡について
続きを見る
第1章ー3ー(3)
放課後児童支援員等の役割
放課後児童支援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研鑽に励みながら必要な知識及び技能を持って育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して子どもにとって適切な養育環境が得られるよう支援する必要がある。また、放課後児童支援員が行う育成支援について補助する補助員も、放課後児童支援員と共に同様の役割を担うように努めることが求められる。
ポイント
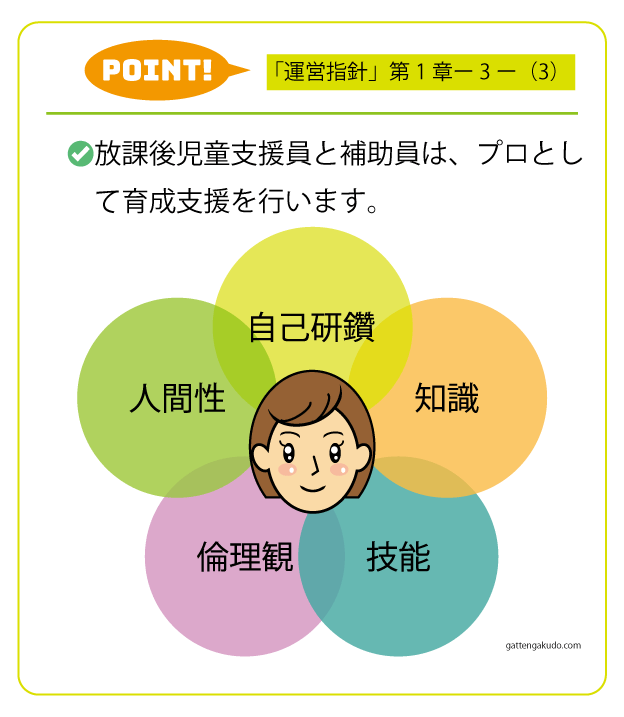
解説
放課後児童支援員の言動は、子ども達に大きな影響を与えます。
そのことを自覚し、育成支援のプロフェッショナルとして、よりよい支援のために絶えず研鑽を積み、必要な知識や技能を向上させるよう努めます。
同じことは、放課後児童支援員が行う支援を補助する「補助員」にも求められます。
第1章ー3ー(4)
放課後児童支援員等の役割
①放課後放課後児童クラブは、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行い、子どもに影響のある事柄に関して子どもが意見を述べ、参加することを保障する必要がある。
ポイント
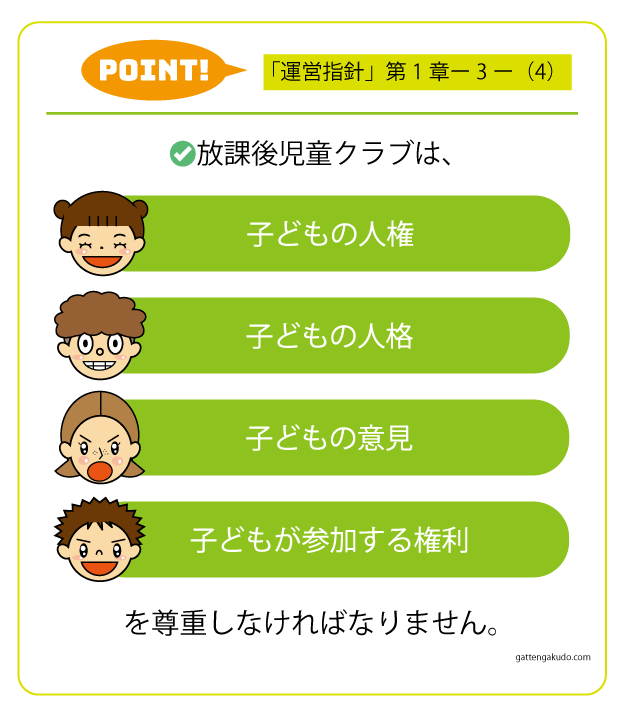
解説
放課後児童クラブの運営主体や放課後児童支援員は、体罰や言葉の暴力、子どもに精神的・肉体的な苦痛を与えること、過度に管理したり規制することが決してないようにしなければなりません。
また、児童福祉法第2条には、「児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身共に健やかに育成されるように努めなければならない」と書かれています。
放課後児童クラブでは、様々な場面で子どもの意見を尊重し、行事の企画段階から子どもが参加するような取り組みを積極的に行っていきます。
第1章ー3ー(4)
放課後児童支援員等の役割
②放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)に対し、その資質の向上のために職場内外の研修の機会を確保しなければならない。
③放課後児童支援員等は、常に自己研鑽に励み、子どもの育成支援の充実を図るために、必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
ポイント
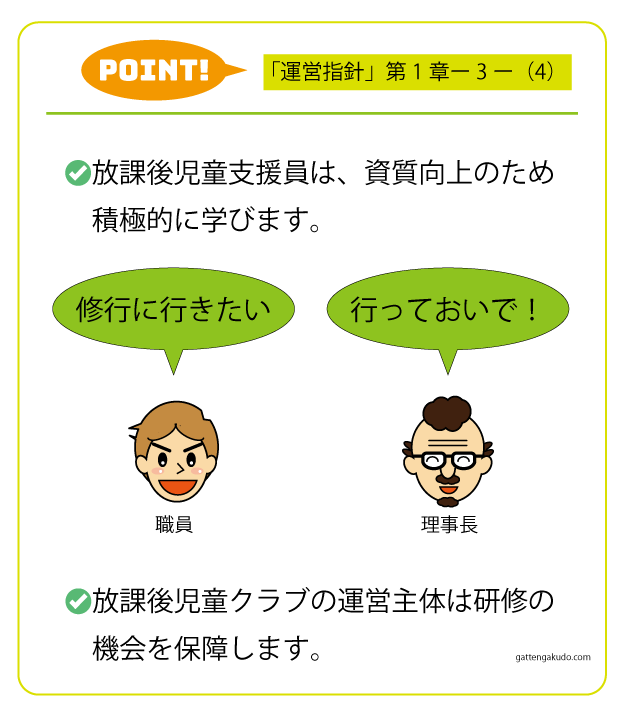
解説
放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員や補助員が資質を向上できるように、職場内外の様々な研修に参加することを保障します。
また、放課後児童支援員や補助員は、日々の子どもとのかかわりの中で学びを深めるとともに、育成支援に必要な知識や技能を習得するために積極的に研修等に参加する必要があります。
第1章ー3ー(4)
放課後児童支援員等の役割
④放課後児童クラブの運営主体は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に当該放課後児童クラブが行う育成支援を適切に説明するように努めなければならない。
ポイント
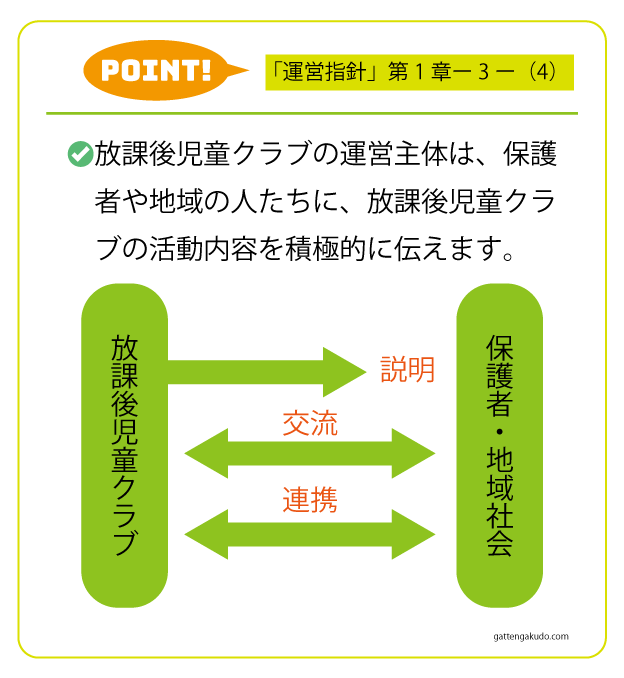
解説
放課後児童クラブの運営主体は、地域社会と交流や連携を図り、地域住民に放課後児童クラブの存在や役割が十分に理解されるように努めます。
子ども達の活動や育成支援の内容を個々の保護者に伝えながら、全体の保護者に定期的に伝える機会や、地域社会に説明するような機会を大切にします。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】理解と共感を拡げるための取り組み「発信」について
続きを見る
第1章ー3ー(4)
放課後児童支援員等の役割
⑤放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、子どもの利益に反しない限りにおいて、子どもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。
ポイント
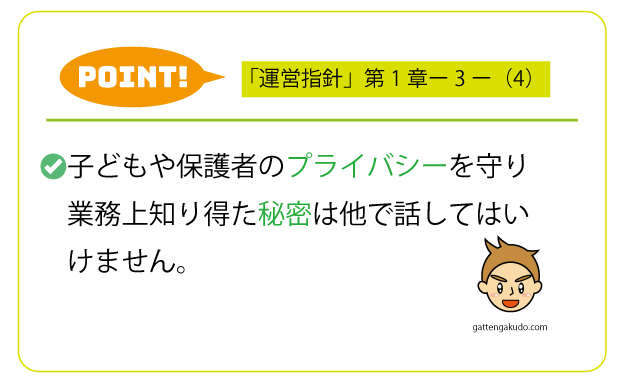
解説
放課後児童クラブの運営主体や放課後児童支援員・補助員は、正当な理由がなく、子どもや保護者に関する情報を第三者に提供してはいけません。
なお、原文では、「子どもの利益に反しない限りにおいて」とされていますが、これは、児童虐待等のケースを発見した時などに、児童相談所等に通告する場合や、市町村に情報を提供する場合などを指しています。
第1章ー3ー(4)
放課後児童支援員等の役割
⑥放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、子どもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を図るように努めなければならない。
ポイント
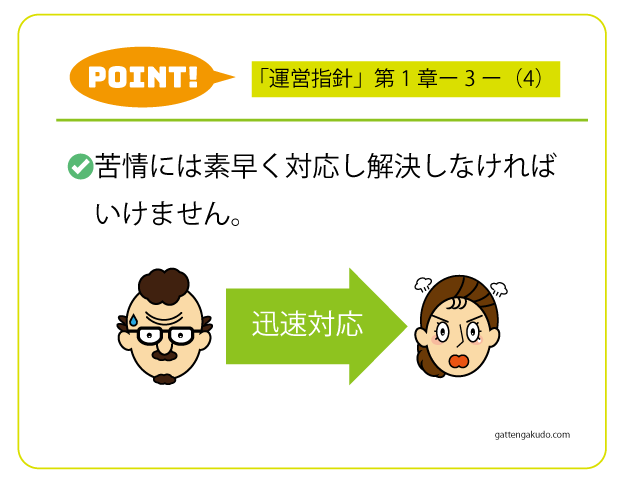
解説
放課後児童クラブは、子どもや保護者の要望や苦情に誠実に対応し、自らの事業内容を見直すことが求められます。
そのために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、保護者に周知したり、苦情に関する対応を記録し、職員間で共通理解を図ります。
さいごに・・・
最後まで読んでくださった皆さん、お疲れまでした。

第1章の内容を理解することができましたか?

ば、ばっちりっす!
運営指針は、次の章から面白くなってきますよ。
第2章は、学童期の発達についての内容です。
それでは皆さん、次の記事でお会いしましょう!

放課後児童支援員のみなさんは、厚生労働省編「放課後児童クラブ運営指針解説書」を読んでくださいね
※画像をクリックすると購入ページ(Amazon)にジャンプします。

当サイトの別の記事では「運営指針」の全文を掲載しています。原文を確認したい方はこちらも参考にしてくださいね。
こちらもCHECK
-
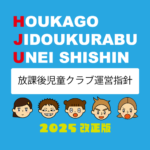
-
放課後児童クラブの「運営指針2025年改正版」一目で改正箇所がわかる!
続きを見る
参考文献:「改訂版 放課後児童クラブ運営指針解説書」厚生労働省編/「全訂 学童保育ハンドブック~適切な運営の判断基準~」全国学童保育連絡協議会編集










