新着記事
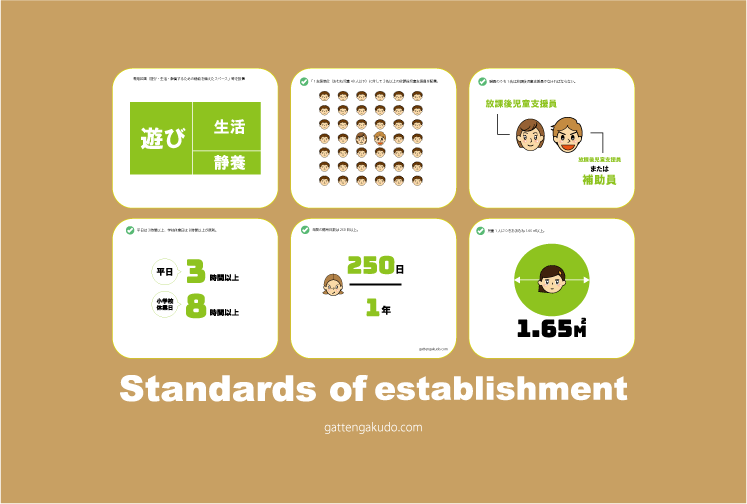

今日は「学童保育所の基準」について学ぼう

きじゅん??
2014年に、国が、厚生労働省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(以下「設備運営基準」)を定め、これに基づき、各自治体が「基準条例」を定めることになりました。
現在の学童保育(放課後児童クラブ)は、この「設備運営基準」と、同じく国が策定した「放課後児童クラブ運営指針」に基づき運営されています。
こちらもCHECK
-
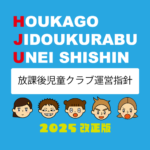
-
放課後児童クラブの「運営指針2025年改正版」一目で改正箇所がわかる!
続きを見る
「設備運営基準」が定められるまでは、学童保育の基準は、児童福祉法施行令で、「衛生及び安全が確保された設備を備える」とだけ定められていいました。
2012年に改正された児童福祉法で、「児童の身体的、精神及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない」とされたことにより「設備運営基準」が公布されることになりました。

学童の基準ができたことは画期的なことだったんだよ
支援の目的

「設備運営基準」では、放課後児童クラブ(学童保育)の目的を以下のように定めています。
支援は、留守家庭児童につき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない。(第5条)
設備
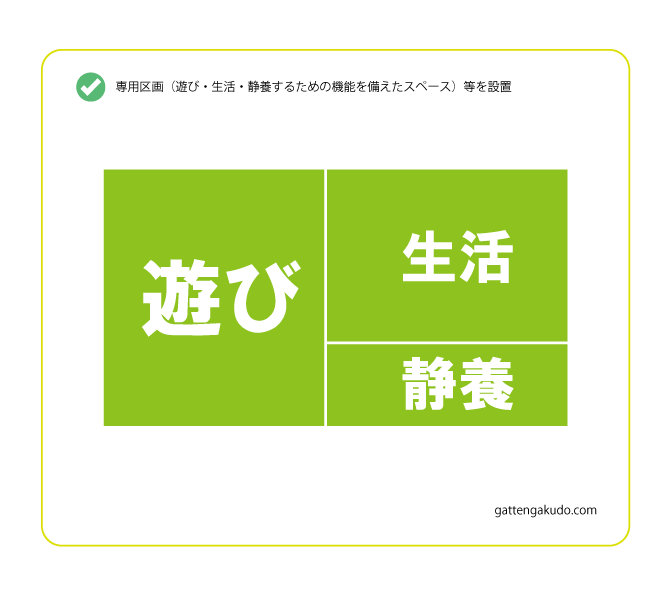
「設備運営基準」では、学童保育の設備について、以下のように定めています。
○専用区画(遊び・生活の場としての機能、静養するための機能を備えた部屋又はスペース)等を設置する。(第9条)

○専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65㎡以上とする。(第9条)
参考までに、保育所の面積基準は以下の通りです。
| 乳児室 | 乳児1人につき1.65㎡ |
| 保育室 | 幼児1人につき1.98㎡ |

赤ちゃんと同じ広さって・・・

ちなみに畳1畳が約1.65㎡です
児童の集団の規模
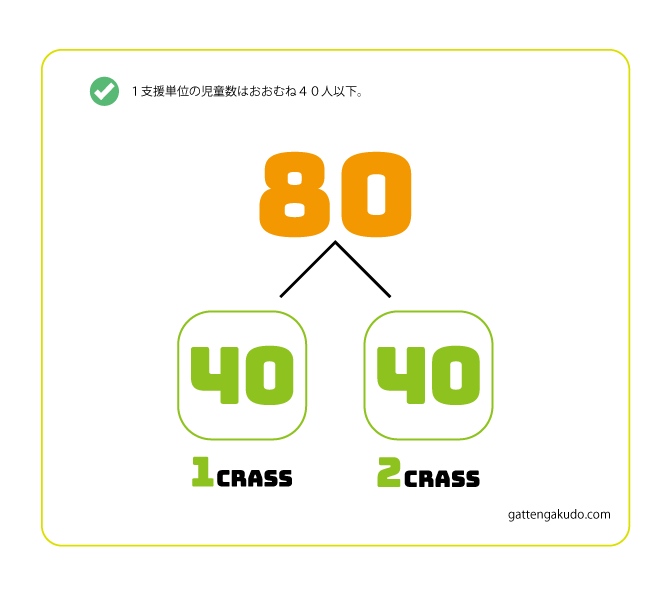
「設備運営基準」では、施設ごとの児童数について以下のように定めています。
○一の支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下とする。(第10条)
「運営指針」でも、「子どもが相互に関係性を構築したり、一つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下」と定められています。
例えば児童数が41人の施設の場合は、20人と21人に支援の単位を分けて学童保育を実施しなければなりません。
施設の状況により、施設を分割(新しく施設を準備)する場合や、既存の施設に複数の支援の単位(クラス)を置く場合などがあります。
単純な数字だけで言うと、児童数が81人から支援の単位が3となり、41人の学童と80人の学童は支援の単位が同じ2となります。

2020年時点で、1支援単位が40人以上で運営されている地域が全国で4割ほどあるそうです
職員
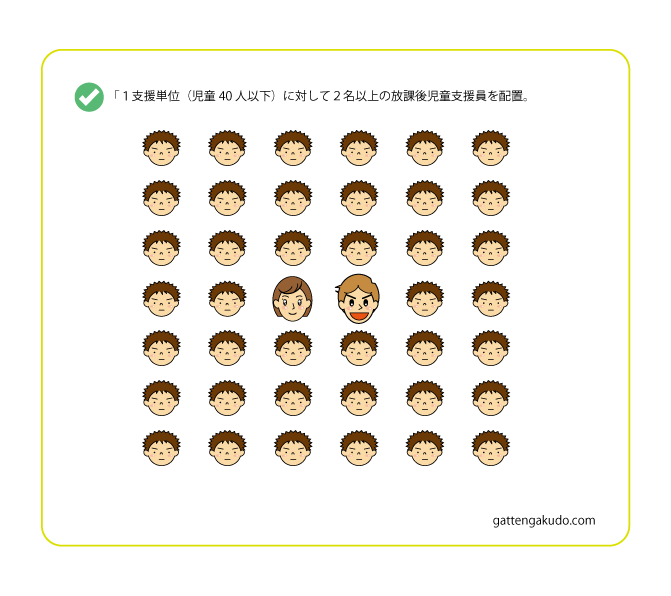
「設備運営基準」では、放課後児童クラブの職員配置について以下のように定めています。
○放課後児童支援員を、支援の単位ごとに2人以上配置する。(第10条)
「放課後児童支援員」とは、「保育士、社会福祉士等であって、都道府県知事が行う研修を修了した者」とされています。
放課後児童支援員の資格要件
- 保育士資格を持っている人
- 社会福祉士資格を持っている人
- 教員免許を持っている人
- 大学・大学院で社会福祉学等を学び卒業した人
- 高卒者で、2年以上放課後児童健全育成事業に類似した仕事をした人で市町村町が適当と認めた人
- 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した人で市町村町が適当と認めた人・・・など
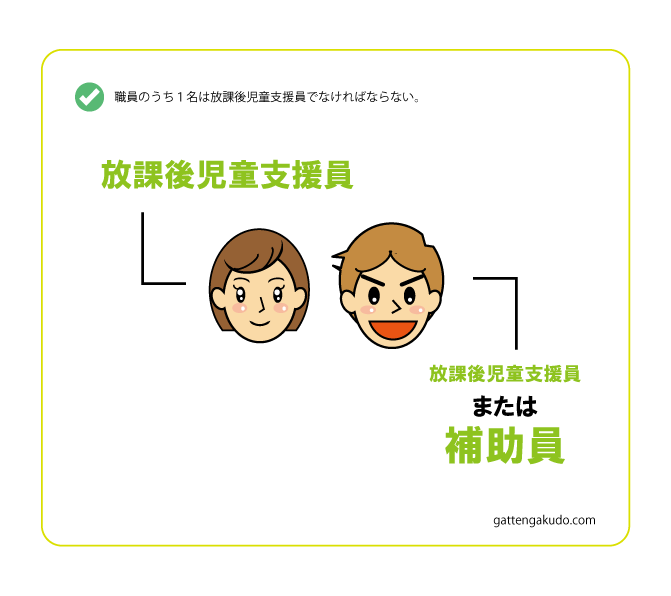
放課後児童支援員は、支援の単位ごとに2人以上配置することになっていますが、
「うち1人を除き、補助員の代替が可」とされています。

この基準は、もともと「従うべき基準」とされていましたが、2019年から「参酌すべき基準」となってしまいました
※「従うべき基準」「参酌すべき基準」については後述があります。
開所日数
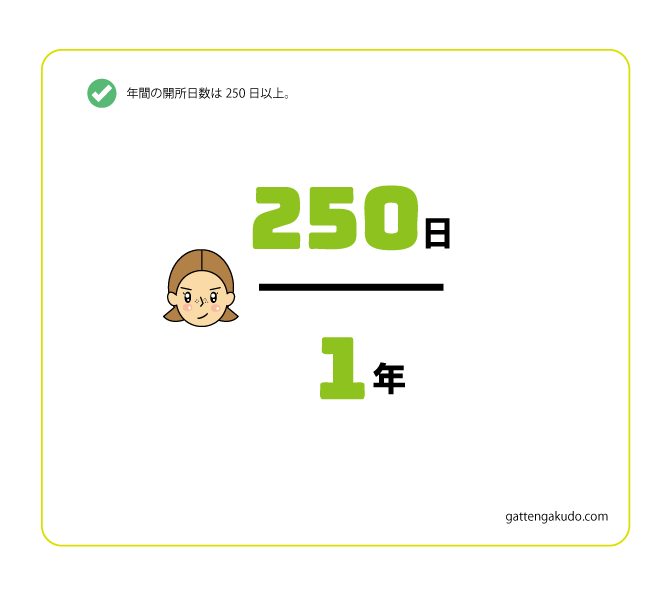
「設備運営基準」では、放課後児童クラブ(学童保育)の開所日数について以下のように定めています。
○開所日数は、原則1年につき250日以上とする。(第18条)
開所日数については、その地域の保護者の就労状況や学校の休業日等を考量して事業を行う者が定めることとされています。
ちなみに、2021年の年間の平日(月~金)の日数は246日、土・日・祝日の日数は119日です。
開所時間
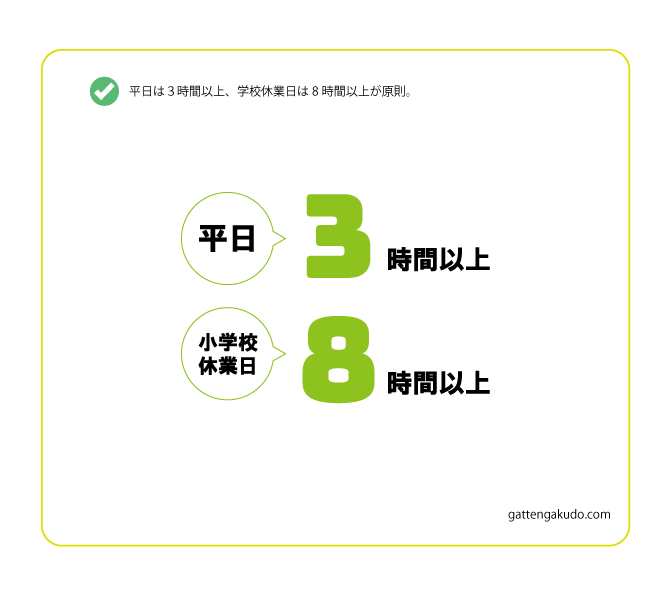
「設備運営基準」では、一日あたりの開所時間について、以下のように定めています。(第18条)
○ 土、日、長期休業期間等(小学校の授業の休業日)→ 原則1日につき8時間以上
○ 平日(小学校授業の休業日以外の日)→ 原則1日につき3時間以上
その他
他にも、「設備運営基準」では様々な項目が定められています。
- 非常災害対策
- 児童を平等に取り扱う原則
- 虐待等の禁止
- 衛生管理等
- 運営規程
- 帳簿の整備
- 秘密保持等
- 苦情への対応、
- 保護者との連絡
- 関係機関との連携
- 事故発生時の対応 など

詳しくは、記事の最後に原文を掲載していますのでご確認ください
「参酌基準」とは
2014年に、「設備運営基準」が策定された当初は、第10条の「指導員の資格と配置」に関しては、市町村が「基準条例」を定める際に「従うべき基準」とされていました。
しかし、2019年に成立した「第9次地方分権一括法」により、指導員の資格や配置を含むすべての基準が「参酌すべき基準」とされました。

「参酌基準」「従うべき基準」って??
- 従うべき基準=自治体は、省令で定める「設備運営基準」を上回る基準は策定できるが、下回る基準は策定できない
- 参酌すべき基準=自治体は、省令で定める「設備運営基準」を参考にして基準を策定する
さいごに・・・

学童の基準ができてよかったけど・・・なんだかな~・・・

基準ができたことは大きな前進だけど、これからもより良い学童保育のために国や自治体に働きかけて行くことが大切なんだ
子ども達が、学童保育施設で安心して豊かな放課後を過ごせるように、また、保護者が安心して働き続けられるためにも、より良い制度を求めて、指導員や保護者の声を関係各所に届けていきましょう。
【参考文献】「日本の学童ほいく」2021年3月号・「日本の学童ほいく」2021年10月号/全国学童保育連絡協議会
【参考URL】放課後児童クラブの基準について・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準/厚生労働省










