新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
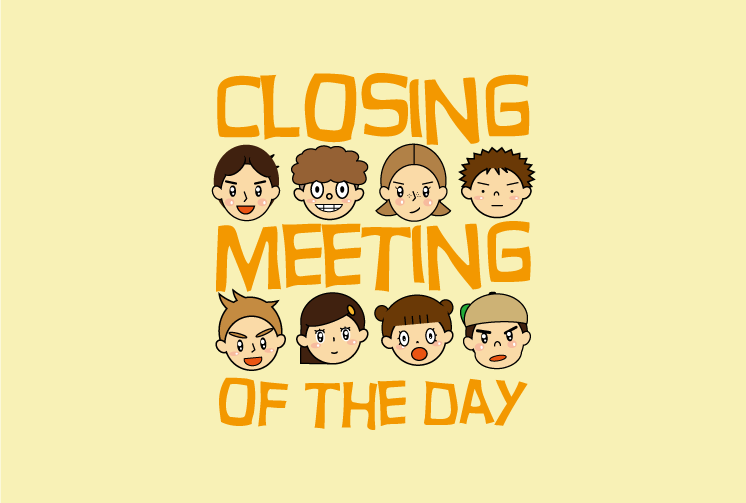
こちらもCHECK
-

-
【学童保育指導員のチームワーク①】「中堅指導員」の私を疲れさせる理由は・・・
続きを見る
指導員の皆さん、保護者の皆さん、今日も一日お疲れ様でした。がってん学童を訪ねてくださりありがとうございます!

がってん学童の指導員、りえです。
今日は待ちに待った小学校給食の始まりでした。こどもたちが学童に帰ってくる時間が遅くなりました。これでやっと一息つけると思いました。

そしたら、新年度の疲れが津波のように押し寄せてきました。
めっちゃ疲れています。早く寝たいです。けど頑張ります。
ブログ村や人気ブログランキングで投票してくれている皆さん、がってん学童にアクセスしてくれている皆さん、本当にありがとうございます。私に勇気と元気をくれてありがとう。本当なら直接会ってお礼が言いたいんです。

がんばってこ~!!
ってとりあえず気合を入れました。
すいませんね。今日はしょっぱなからぼやきモードで。皆さんも、どうかご自愛ください。
私がなぜ、今日、こんなにも疲れて、やけのやんぱちみたいになっているかは、数日後の記事で明らかになります。
新年度の雰囲気作りは帰りの会から

というわけで、今日のテーマです
今回の記事は、帰りの会の時間を大切にして、新年度の学童の良い雰囲気を作っていきましょう!って内容です。
この記事の内容
- 帰りの会が大事な理由
- 帰りの会で子どもに伝えたいことは
- とにかく子どもに「静かにすること」を求めていた私
- 子どもたちの望ましい姿を引き出すテクニック
- 子どもが主人公の帰りの会を
- 帰りの会で子どもを叱る時の話し方
- 帰りの会で子どもをほめる時のポイント
- 子どもの「ちょっといい姿」をみつけるためには
- おわりに(帰りの会でできるおすすめ遊びのまとめサイトの紹介)
みなさんの学童では、どんな風に、帰りの会を行っていますか?
がってん学童保育所の帰りの会は、こんな感じです。
-
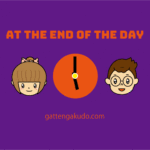
-
【学童保育】子どもが話を聞いてくれない?「帰りの会」の進めかた
続きを見る
1年間のスタートにあたるこの時期に、帰りの会のことをもう一度考えてみたくて、「私が大切にしていること」を改めてまとめてみました。

私は帰りの会の時間って、本当に、とってもとっても大事だと思っているの
帰りの会が大切な理由
なんで帰りの会が大事なのでしょうか?

まずは、そこから説明しますね
帰りの会が大事な理由
- 子ども達がばらばらにやって来てばらばらに帰って行く学童保育の生活の中で、唯一全員が集合する時間だから
- 毎日あるから!
そうなんです。帰りの会は、指導員が、学童の子どもたち全員に対して、発言することができる超貴重な時間なんです!
帰りの会が、一日10分あるとして、一週間で(土曜日抜きで)50分、一カ月で220分です。

220分って言ったら、3時間40分!
これだけの時間なんですよ!毎日の帰りの会で指導員が子どもに「何を伝えるのか?」、子どもたちが帰りの会で「どのように過ごすのか?」によって、そりゃ学童の雰囲気を良くも悪くもすることができる!
新年度の帰りの会で指導員のお説教は禁物、連絡事項だけで終わらすなんてもったいない!

って思いませんか!?
帰りの会で子どもに伝えたいことは

では、新年度の帰りの会で、どんな話を子どもたちにしたらよいのでしょうか
ってことを考える前に、皆さんは、皆さんの職場である学童保育所をどんな学童にしたいと考えていますか?
私は、こんな風に思っています。
私が目指す学童
- 子ども達が安心して過ごせる学童
- 子どもたちが生き生きと遊んでいる学童
- 子どもたちが失敗を恐れずいろんなことに挑戦できる学童
- 下級生と上級生の間に、憧れ・憧れられる関係がある学童
- 子どもが主体の学童
- けじめのある学童
良かったら皆さんも、紙と鉛筆を持って、5つほどリストアップしてみてください。
で、どんな話を帰りの会でしたらいいのか?って話です。

もうおわかりですよね
あなたが目指す学童につながる子どもたちの「行動」を、帰りの会でどんどん褒めていくんです!
とにかく「静かにすること」を子ども達に求めていた私
実は私は、以前は、帰りの会こそ、子どもたちに「けじめ」を教える絶好のチャンスだと思っていたんです。
そして、「話を聞く態度」を子どもたちが身につけるためには、「新年度が肝心だわ!」って、とにかく静かにすることを子どもたちに求めていました。こんな感じです。

みんなが静かにしたら、先生は話をしますね

まだ声が聞こえるわね

まだしゃべっている人がいるわね

(しーん)

やっと静かになったわね。それでは先生の話をします・・・・
私はこの頃、子どもを静かにさせることが、指導員の「指導力」だと思っていたんです。
でも、静かにさせることには結構な情熱を注いでいたけど、子ども達が静かになった後の指導員からの話は「簡単な伝達事項」だけだったりました。
子どもたちに「けじめ」を伝えたり、「話を聞く態度」を身につけさせることが悪いことだと言っているじゃないんです。

それ以外に、子どもたちに伝えたいたくさんのことを、もっと大切にしなくちゃいけないんじゃないの?って思ったんです
今は、だいぶやりかたが変わりました。
子ども達が聴きたくなる話を準備して、帰りの会で話すんです。
そうしたら、子ども達、最初はおしゃべりしていてうるさいけど、だんだん静かに聞いてくれるんです。
そして最後に、

みんな、静かに聞いてくれてありがとう。
先生嬉しかったよ
って言うんです。

静かにしなさい!
って言うことは、子ども達のできていないところを指摘することでしょ。
けど、

聞いてくれてありがとう
って言うのは、子ども達ができたことを認めることです。
私は、新年度はとにかく、子どもたちができていないことを言うんじゃなくて、できたことをどれだけ認められるかが勝負だ!って考えています。
それが、学童の「雰囲気」を作っていくことになるんだ、って思っているからです。
帰りの会で「叱らない」方法
帰りの会で、子どもたちに静かにしてほしい時や、ちゃんとした姿勢をしてほしい時に、私がよく使う技があります。
例えば、「もっとみんなにちゃんと座ってほしいな~」って思った時は、綺麗な姿勢で座っている子を探すんです。
そして、

だれが、きれいな姿勢で座っているかな~?

あら、てっちゃんの姿勢、とっても綺麗だね!
って、呟くんです。
そうしたら、他の子どもたちが一斉にてっちゃんを見て、自分の姿勢を正すんですよね。
言葉で「ちゃんとした姿勢で座りましょう」って言うより、ちゃんと座っている子どもを他の子どもに見てもらう方が、子ども達にとってはばっちり視覚で伝わるからわかりやすいんです。

これは、帰りの会以外の場面でも使える方法です
望ましいと思う行動を子どもたちから引き出すためには、モデルとなる子どもを見つけて、ほめてあげるんです。
子どもが主人公の帰りの会を
ちょっと、話が変わるけど、私はやっぱり、帰りの会の司会は、指導員じゃなくて子どもがやるほうが良いと思っています。
指導員が「話をする人」、子ども達が「聞く人」って関係性が固定しちゃうと、帰りの会でできることが拡がっていかないんですよね。
学童の生活の主人公は子どもなんです。子どもはお客さんじゃありません。

子ども自身が帰りの会の運営をする
そこから子どもの主体性を大切にする学童保育の実践が始まっていくと、私は思っています。
どうしても叱らないといけない時には
そんないいことばっかり言っていても、帰りの会で、子ども達を叱らないといけないこともありますよね。
そんな時には私は、

こら~!!
って言うんじゃなくて、こんな風に言います。

今日は私、とっても悲しいことがありました・・・
子どもの心にしみじみと伝わるように、語りかけるように話すようにしています。
帰りの会で子どもをほめる時のポイント
次に、帰りの会で子どもたちをほめる時の注意点です。
あんまりほめすぎると、子ども達に「こうじゃなきゃ先生嫌だよ」って無言のプレッシャーをかけることになりかねません。
なので、私は、子どもたちの、「めっちゃかっこいい姿」の話を、あんまりしすぎないように気をつけています。
私が帰りの会でとりあげる話は、子ども達の「ちょっといい姿」なんです。

今日ね、先生、てっちゃんの「ちょっといい姿」見ちゃったんです。
てっちゃん、1年生に新聞紙の剣を作ってあげていたんだよ。1年生はすごい嬉しそうだったね。先生もなんだか嬉しかったな~
って感じで、子どものふとした行動を見つけた時の私の気持ち発表するようにしています。
そして、物事の結果をほめるのではなく、その過程や行動に焦点を当てて話をするようにしているんです。
そしてそして、「成功例」の話ばっかりじゃなくて、「失敗談」の話を織り交ぜていくことも大切なポイントだと思っています。
子どもの「ちょっといい姿」を見つけるためには・・・
帰りの会で、子どもたちの「ちょっといい姿」の話をするために、私は、一日の中で、とにかくたくさん子どもたちと関わって、いつもアンテナを張って

子ども達の「ちょっと良い」姿を見つけるぞ~!
って考え続けています。
一緒に遊んだり、一緒に生活したり、一緒に取り組んだり・・・そんな子どもたちとのかかわりの中で、宝もののようにキラリと輝く素敵なエピソードに出会えるんですよ。
帰りの会で、指導員が子どもたちに伝える「ちょっといい姿」の話は、たくさんである必要は全然ありません。

一日一個、それを毎日続けていきましょう
絶対に学童の雰囲気がよくなっていきますよ!
おわりに・・・
いかがでしたか?
今回は、帰りの会の機会を大切にして、学童の雰囲気を作っていきましょう!って話でした。

新年度は、帰りの会でゲームや遊びをみんなで楽しむのもおすすめです
これに関しては、ジャムさんのブログで最高にためになる記事があるからご紹介しておきます。
【帰りの会ゲームネタ30】小学校や学童の子どもたちが座って短時間でできる!
ジャムさんは、学童保育歴20年で、指導員や保護者の方のためになるサイト「学童クラブ指導員と保護者の部屋」を運営されています。

とってもおすすめのページです。ぜひ参考にして、子どもたちと素敵な帰りの会の時間を過ごしてくださいね!!
それでは皆さん、またの記事でお会いしましょう!

ちょっと補足したいんだけど・・・
実は以前の記事で、子どもの褒め方についてまとめています。
-

-
【学童保育】意外と悩む「子どもの褒めかた」について
続きを見る
この記事の中で、「親や指導員が、自分の思い通りにするための手段として、子どもを褒めるのは良くないんだよ」と書いています。
今回の記事の内容の「指導員が目指す学童につながる子どもたちの行動を、帰りの会でどんどん褒めていく」や、「望ましいと思う行動を子どもたちから引き出すためには、モデルとなる子どもを見つけて、褒めてあげる」は、良くない褒め方なんじゃない?と思う人がいるかもしれません。

二つの記事で、違うことを言っちゃっているんだけど、りえ先生はどう思う?

あらいやだ!えらいこっちゃ
この問題については、がってん学童保育所の「宿題」として、指導員で議論を深めてみたいと思います。
皆さんのご意見もぜひ聞かせて欲しいです。(「お問い合わせ」のページから送信できます)










