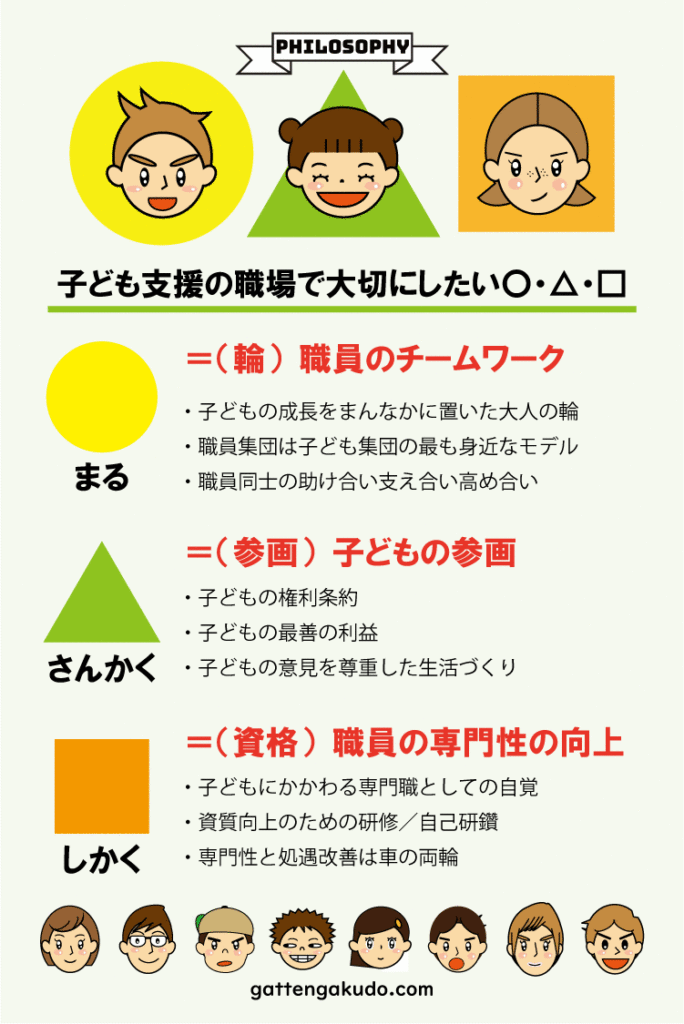今回の記事では、子どもに意見を聴く時の大人のマナーについて考えるとともに、「意見とは何か?」という根本的なテーマについて考えを深めていきたいと思います。

新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし!
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
目次

こんんちは、がってん学童所長です。

新人支援員のたけしです!
今日は、「子どもの意見を聴く」ということについて一緒に考えていきたいと思います。
2023年4月1日に発足したこども家庭庁は、子どもの意見が大切にされる「こどもまんなか社会」を目指すと言っています。
2022年6月に国会で成立した「こども基本法」にも、「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。(第十一条)」と書かれています。
今後、具体的に、私たちの自治体にどのような形で「子どもの意見を聴く」取り組みがおりてくるのかはまだ不明ですが、この機会に「子どもに意見を聴く」ということについて、あらためて考えを深めておくことも大切じゃないかと思うんです。

なるほど~、こども家庭庁のからみなんっすね。

子どもにかかわる施設の職員の方や、子育てをする保護者の方にはぜひ読んでいただきたいと思います。
こちらもCHECK
-
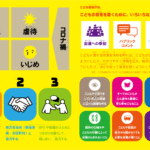
-
【こども家庭庁が5分でわかる!】基本的な内容をイラストでわかりやすく解説
続きを見る
まず最初に「子どもの意見」をどうとらえるか

最初に、今日のテーマの前提となる話をしておくよ。そもそも「意見」とはなんだろうか?

意見とは・・・?
ちょっと前置きが長くなってしまうのですが、大切なことなので考えておきたいと思います。
僕の家にある旺文社の国語辞典には、次のように書かれていました。
意見=心に思うところ。考え。
また、ネットで検索すると、次のようなものもでてきました。(「ブリタニカ国際大百科事典 小項目辞典」参照サイト:コトバンク)
意見=人が特定の状況や対象に対してもつ特定の態度の言語的表明
様々な説明があるので、皆さんも一度調べてみてください。
ここで考えるべきポイントは、言葉になったもの(言語的に表明されたもの)だけを「意見」と認めるのか、心で思っていることだって意見だと認めるのか、どっちなんだろう?ってことです。

たけし先生はどう思う?

そうっすね・・・、僕は「意見」って言ったら言葉にして相手に伝えるものって思っていたけど、あらためて言われたら、心の中で思っているだけでも「意見」なのかもしれないと思いました。
言葉にならない思いも子どもの「意見」?

僕もたけし先生と同意見です。
特に子どもの場合は、言語能力が大人と比べて発展途上であることもあり、言葉に置き換えられたものだけを意見ととらえてしまうと、はっきりと意見を言うことができる子どもの意見だけが取り上げられることになってしまうと思います。
その陰で、言葉にならないたくさんの子どもの「意見」が切り捨てられてしまう、そのような状況は「こどもまんなか社会」とは言えないですよね。

子どもの言葉にならない思いや感情・態度等を大きく「意見」ととらえる大人の姿勢が大切だと思うんだ。
同時に、意見は大人が求める時だけ受け付けるものではなく、子どもは常々何らかの意見を表明しているととらえることも必要だと思います。
そういった、大人の理解と適切なかかわりのもとで、子どもたちは成長とともに、意見を言葉で言い表せるようになっていくのです。

大人のかかわりが大切なんですね?
なぜ子どもの意見を聴くの?

あの~、今さらって感じなんすけど、なんで子どもの意見を聴かなければいけないんですか?

子どもの権利として保障されているからなんだよ。
先ほどご紹介した「こども基本法」の他にも、児童福祉法や僕たちの職場の学童保育に関する「放課後児童クラブ運営指針」など、子どもに関する様々な条文の中に、「児童の権利に関する条約」が登場します。
児童の権利に関する条約は、1989年に国連総会で採択されました。日本は、世界で158番目に子どもの権利条約を批准しました。
子どもは大人から守られる(保護される)対象ではなく、自ら権利を行使する主体である、ということを世界的な約束事として定めたのが児童の権利に関する権利条約です。

子どもの権利条約を学童保育に活かす (そこが知りたい学童保育ブックレットシリーズ)

とってもいい本ですよ
ぜひお手元に一冊置いてくださいね
「児童の権利に関する条約」には、次のように書かれています。
第12条
- 締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。
- この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。

第12条は、「意見表明権」と呼ばれているんだよ。
児童の権利に関する条約では、子どもにとって一番よいこと(第3条子どもの最善の利益)は、子どもに聴いて(第12条意見表明権)、子どもと一緒に考えて決めていこうと定められています。

なるほど~!
子どもの意見表明権の英文が教えてくれること

余談ですが、児童の権利に関する条約の12条「意見表明権」は、英語では「Respect for the views of the child」となります。
意見と言うと「Opnion(オピニオン)」という英単語が浮かぶのだけど、児童の権利に関する条約の原文(英文)では「View(ビュー)」という言葉が使われています。
「Opnion」と「view」はどちらも自分の考えや見方を表す言葉ですが、「view」という表現は「Opnion」に対して、より広い視野や見解、考え方を意味しています。
児童の権利に関する条約の原文で、「View」という表現が用いられるのは、子どもの意見を、より包括的な視点から理解する必要性をうったえかけていると考えられます。(※がってん学童解釈)

(英語はさっぱりだけど)さっきの話にあったように、子どもの言葉にならない思いや感情・態度等を大きく「意見」ととらえることが大切ってことがわかりました。

前置きが長くなっちゃったけど、次が本題です。
子どもの意見を聴く時の大人のマナー
子どもに意見を聴く時には、大人が大切にしたいいくつかのマナーがあります。

聴く側の大人がマナーを守ることによって、子どもたちは安心して意見を言うことができるようになります。
親子関係や施設で職員が子どもに意見を聴く時など、様々なシチュエーションを想定しつつ、共通して以下のことが「子どもに意見を聴く時の大人のマナー」と言えると思います。
- 真剣に聴く
- 最後まで聴く
- 意見を言いやすいように援助する
- 子どもの意見を尊重する
- 感謝の言葉を伝える
それでは、ここで、がってん学童の中堅支援員りえ先生に登場していただき、お手本を見せてもらいながら説明していきましょう。

よろしくお願いします。

先輩!よろしくっす!

プレッシャーだわ~
真剣に聴く

おれは絶対カレーライスが食べたいんだ!

そうなんだね。
子どもの意見を聴く時は、相手に体を向け、子どもの目を見て話を聴きます。
そうすることで、「あなたの意見を真剣に聴いている」というこちらの気持ちが子どもに伝わります。
最後まで聴く

・・・わた・し・は・・・

うん、うん・・・

は・や・・し・らいす。
子どもの意見を途中でさえぎったりせずに、最後まで聴きます。
スラスラと自分の意見を言えないこどももたくさんいます。子どもが思いを言葉にする過程を我慢強く見守りましょう。
意見を言えるように援助する

ルーを何にしたらいいかなんて、そんなのわからないよ・・・

さっちゃんはシチューとカレーどっちが好きなの?

シチュー!!
子どもが意見を言葉にできなくて困っている場合は、整理してあげたり、よりわかりやすい言葉で質問してあげることも大切です。
子どもが意見を言いやすくなります。
子どもの意見を尊重する(否定しない)
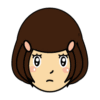
私はシチューにチーズをのせたいな

おいしそうね
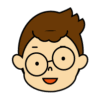
ぼくはポテチをのせたい

どんな味になるんだろう?
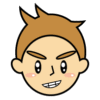
おれはチョコをのせる

チャレンジャーだね
子ども達が表明した様々な意見を、否定せず、肯定的な反応を示すことも大切です。
せっかく言った意見を大人に否定されたら、次に意見を言おうという意欲が失われてしまいますよね。「どうせ言っても無駄だ」という思いを子どもに持たせることがないようにしましょう。
感謝の言葉を伝える

今日はみんな、たくさん意見を言ってくれたね。ありがとう。

うん!
子どもが意見を言ったことに対して、感謝の意を伝えます。
意見を言ったこと自体を認めてもらえたことが次の意欲につながります。

いったい何の意見を聴いていたんですか?そっちの方が気になったんですが・・・

今度の合宿の晩御飯のメニューだよ。

りえ先生、どうもありがとうございました。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】子どもの参画「子どもはお客さんではありません。」子どもの参画を促す手軽な活動のアイデア10選
続きを見る
文句だって立派な意見?

よっしゃー!これからはマナーを守って子どもの意見をいっぱい聴ける支援員を目指すぞ~!

その意気だね!
そんなたけし先生にもう一つアドバイスがあります。
意見は言うのは苦手だけど、文句だったら言うのが大好きって子ども、学童にいませんか?

い、います・・・。
子どもって文句を言うのは得意ですよね。
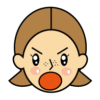
え~!?
とか、

なんでそんなんしないといけないんだよ~!
とか、

ぶー!

ぶー!
って、支援員の言うことにぶーぶーとブーイングしたり・・・。

そんな子ばっかり!

けどさ、文句も立派な意見表明だと思うんだよね。
そんな文句を受け止めてくれる大人がいるから、子どもたちは自分の様々な思いを自由に表現できるし、そんな経験があるから意見を言える子どもへと成長していくと思うんです。
「文句は言わないの!」とか、「文句じゃなくて意見を言って!」などと対応するのではなく、

え~!?って文句言うけどさ、だったらどうしたいと思っているの?
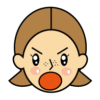
私はカレーがよかったのに!
なんてかかわりも大切にしたいですよね。

また晩御飯のお話??
さいごに 意見を言うのは大人だって難しい?
というわけで、今日は「子どもに意見を聴く時の大人のマナー」について考えてみました。
様々なご意見があると思いますので、職場等でこの記事を踏み台にして議論を深めていただけると幸いです。
また、この記事の続編として、「子どもに意見を聴く前と聴いたあとに大切にしたいチェックポイント」という記事を予定しています。

実際の現場では、子どもの意見を聴く時の大人のマナーの応用力が問われます。そんな内容をまとめてみたいと思います。
最後になりますが、今回の記事は、子どもに意見を聴くというテーマでしたが、私たち大人は、ちゃんと意見を言えているでしょうか?
社会人になって大人同士であっても、意見を言うことや意見を聴くということはとても難しいことだと私は感じています。
うまく意見を言えなかったと落ち込むことも日常茶飯事です。

大人にも難しいことだから、子どもにとっては本当に難しいことなんですね・・・。
それに、こども基本法では、こども施策に子どもの意見を反映させる旨が書かれていますが、大人はどうなんでしょうか。
政策に意見を反映する機会であるはずの選挙の投票率がなぜこんなに低いのでしょうか。大人がそんな状況で、子どもに意見を聴くという取り組みに説得力があるのでしょうか。

大人だって意見をいってね~じゃね~か!
なんて、子どもに言われないようにも、子どもに意見を聴くということについて、大人も含めたこの国の課題として考えていくことが必要なんじゃないかと思う今日この頃です。

えらそうなこと言ってすいません。
(おわり)