新着記事
日々の支援・計画・記録などを1冊に書き込みこむことで、仕事が蓄積・共有され、実戦力アップにつながります。■主な内容■
●2024年12月〜2026年4月までのダイアリー
●学童保育と子どもとあそびに関わる指導員のエピソード
●遊びルールの紹介(ケイドロ・マンカラなどQRコードから)
●放課後児童クラブ運営指針(2025年4月から実施の改訂版)
●設備及び運営に関する基準/職場倫理チェックリスト先行セール開催中amazon プライムデー
7月11日(金)~14日(月)


今回は、僕が大好きな遊びを紹介します!
こんにちは、がってん学童所長です。
今日は、私の20年以上の学童保育人生の中で、子どもたちと思いっきり楽しんできた、作って遊べる「めんこ」をご紹介します。
猛暑日や雨で外遊びができないと、元気な子どもたちは力を持て余して落ち着きませんよね。そんな時には、室内で思いっきり発散できて、様々な遊び方・楽しみ方ができる「めんこ」が超おすすめなんです。
では、さっそく、めんこの作品から見てもらいましょう!
私が作っためんこや、学童の男の子・女の子たちが作った、愉快なめんこがたくさん登場します。お楽しみに!
目次
オトナの「めんこ」

まずは僕が作った、とっておきのめんこです。
20年以上前に作って、まだ現役で活躍中の、子どもたちから最強と恐れられためんこです。

めんこは、縦8センチ×横5センチくらいのボール紙(厚紙)を重ねて作ります。
裏と表に絵を描いて、木工用ボンドで貼り合わせたら完成です。
続いて2枚目のめんこは、人気のテレビシリーズの主人公を描いたもの。めんこの絵にはその時々の流行りの文化が反映されます。

もちろん、投げる時は、
100倍返しだ!!
と気合の絶叫をします。めんこは、投げる時のかけ声が大事なんです。
めんこの絵は、縦向きに描いても横向きに描いても自由です。

このめんこを投げる時は、
そのもの青きころもをまといて金色の野におりたつべし!!
と叫んで、べし!!のところで投げるんです。かけ声大事です。
子どもの「めんこ」

子どもたちが作っためんこも見てください。
もう20年も前ですが、前の職場の学童で、めんこが空前の大ブームになった時のものです。
子どもに頼んでカラーコピーをさせてもらいました。
とても可愛い絵ですよね。
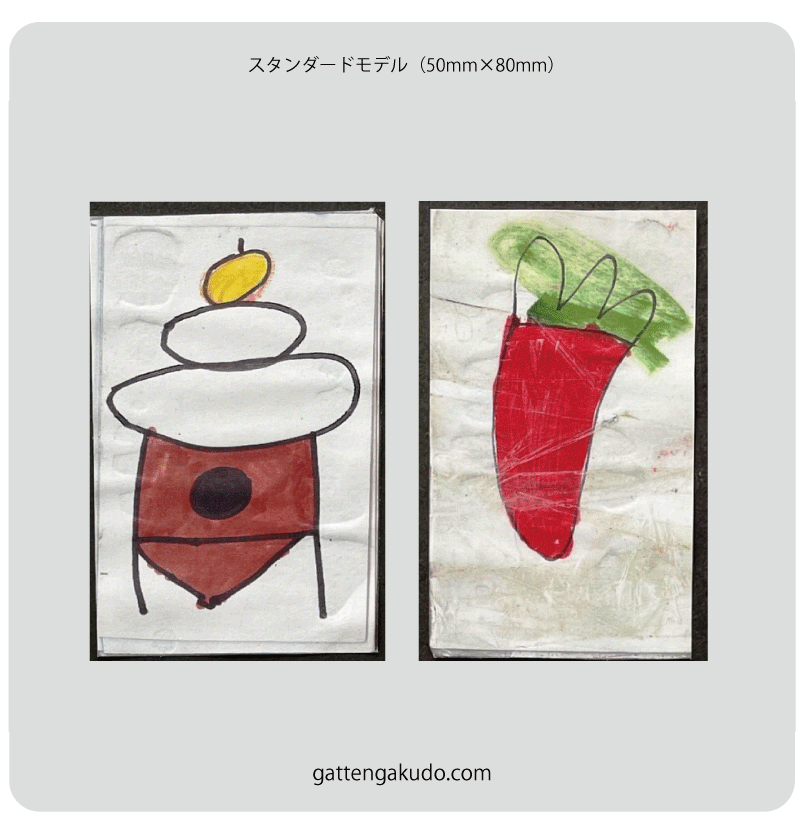
スタンダードモデルは、通常のサイズのめんこです。めんこが大流行すると、子ども達が創造力を発揮して、型破りなめんこがどんどん登場しました。後でご紹介しますので楽しみにしていてください。
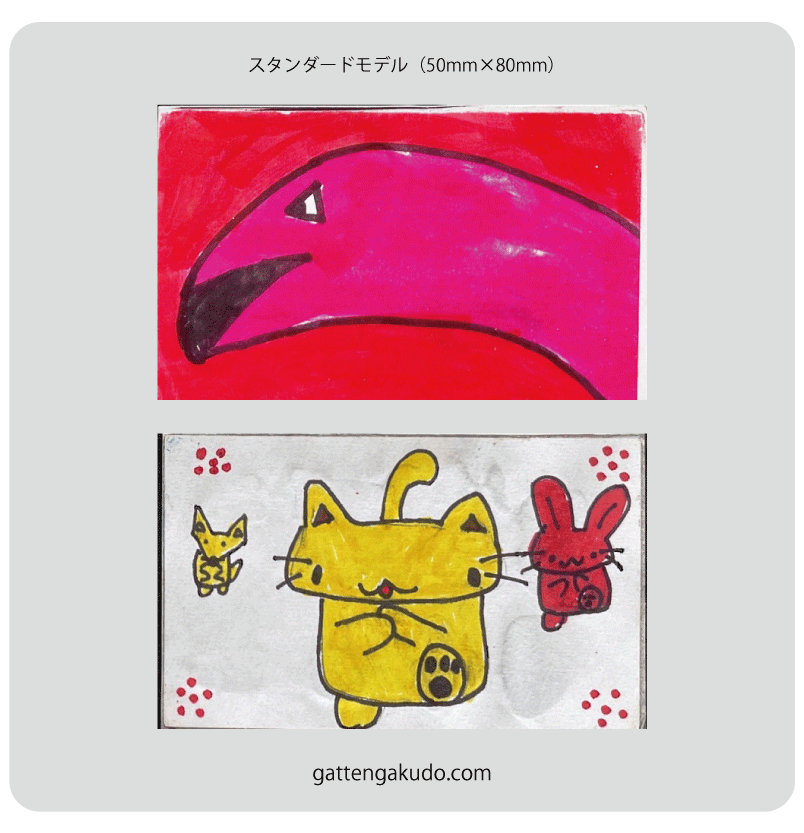
男の子だけでなく、女の子もめんこが大好きでした。じっくりと絵を描くことを楽しむ子どもや、適当に絵を描いて遊ぶことに重点を置く子どもなど、めんこの楽しみ方は人それぞれです。
マンガやゲームの大好きなキャラクターを描く子も多いです。
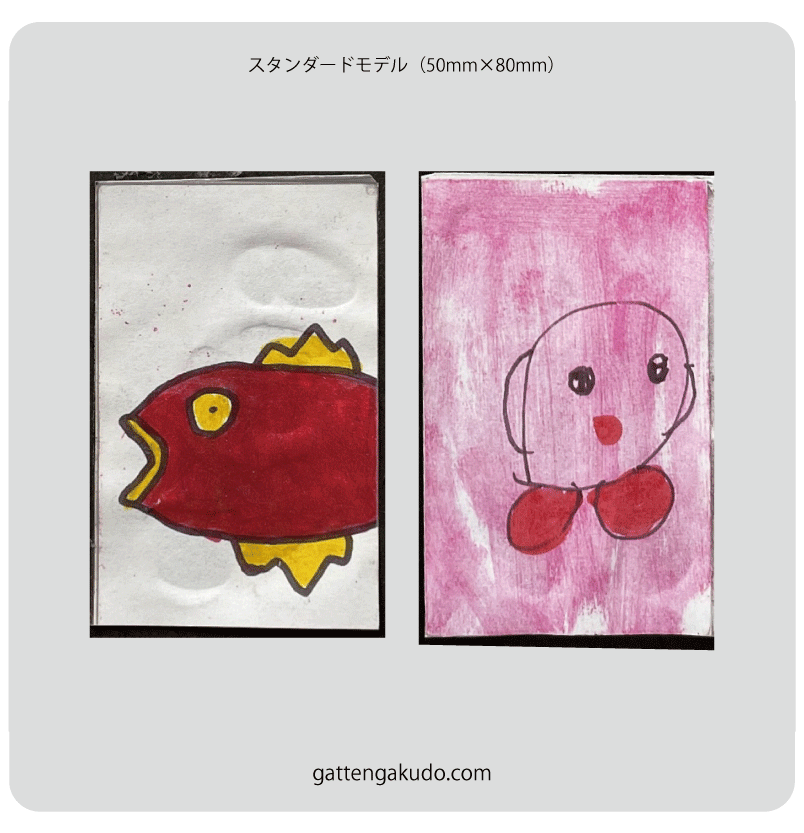
アートとしての「めんこ」
めんこが流行ると、鮮やかな色使いのめんこや、詳細な描写など、アーティスティックなめんこが登場しました。
子どもの絵って、味わいがあって面白い!壁に飾ってみたくなりますね。
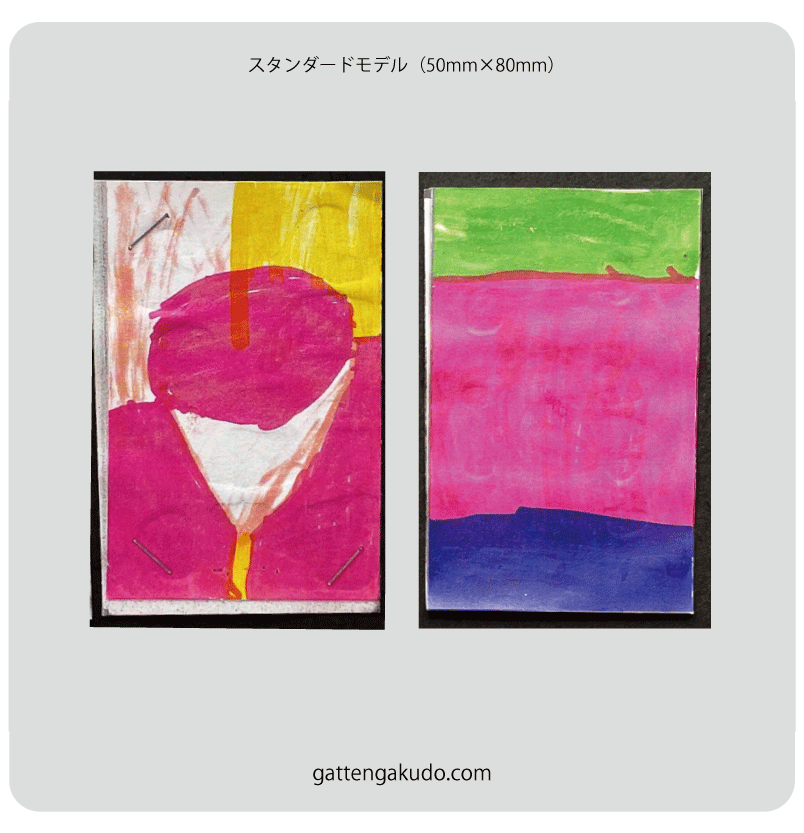
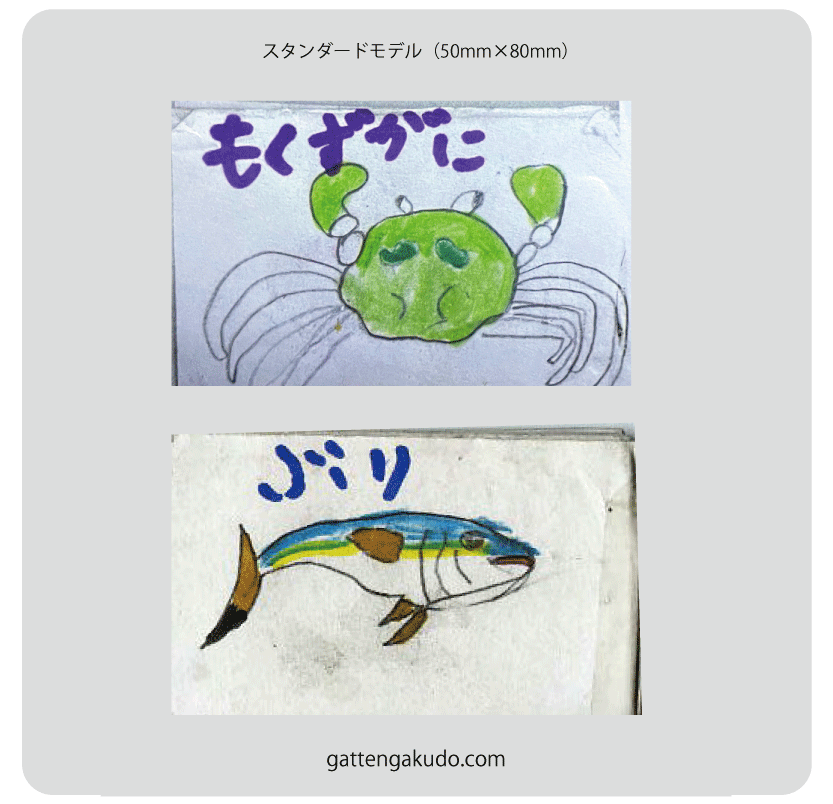
「う〇こ」の「めんこ」が大流行して困ったことも
ある時、高学年の子どもが、めんこに「う〇こ」の絵を描いて、「どや~!!」と言って、みんなが大爆笑になったんです。こういう子、どこの学童にも必ずいますよね(笑)。
それをきっかけに、「う〇こ」デザインのめんこが大流行して、その後しばらく、低学年が描くめんこはほとんどが「う〇こ」の絵になってしまいました。

「メッセージめんこ」の登場
ある遊びが超絶に流行すると、子どもたちの発想が、その遊びの概念を超えていくことがあります。そして、遊びが次々と子どもを巻き込んで、熱狂的に拡がっていきます。このような状態を「遊びの渦」と言います。
「メッセージめんこ」も、そのような遊びの渦の中で生まれました。
めんこに、友達へのメッセージや自分の夢をしたためる子どもが現れたのです。
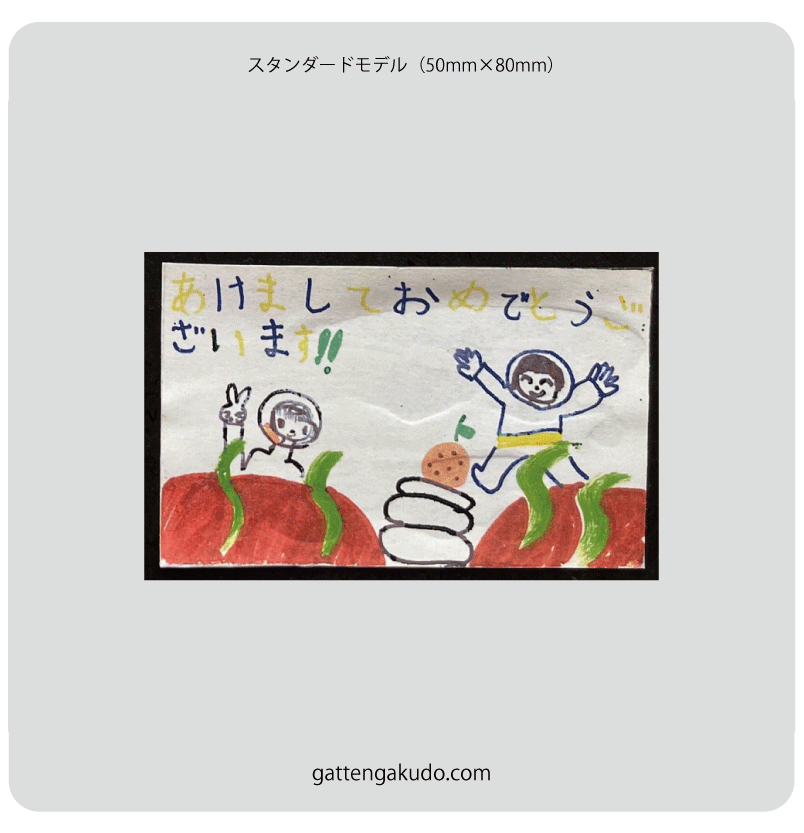

「防水モデル」の登場
その後も、子ども達は自由な発想で、めんこの枠組みを超える「めんこ」を開発していきました。
これは、セロハンテープでぐるぐる巻きにした「完全防水モデル」です。

「めんこなのに防水である必要なんてないじゃん」などと野暮なことを言ってはいけません。製作者の子どもが「防水にしたかった」というその気持ちと、それを実現したことが素晴らしいのです。
なんじゃこれは??めんこなのに防水??すんげー!!超かっこいいやん!
私の反応はこんな感じでした。(本気でそう思っているのがポイント)
こういったまわりの反応が、子どもの更なる意欲をかきたてるんです。
「攻撃モデル」の登場
子どもたちは、50㎜×80㎜のサイズを超えためんこを開発するようになりました。
より強そうな形状を追求した、「攻撃モデル」の登場です。
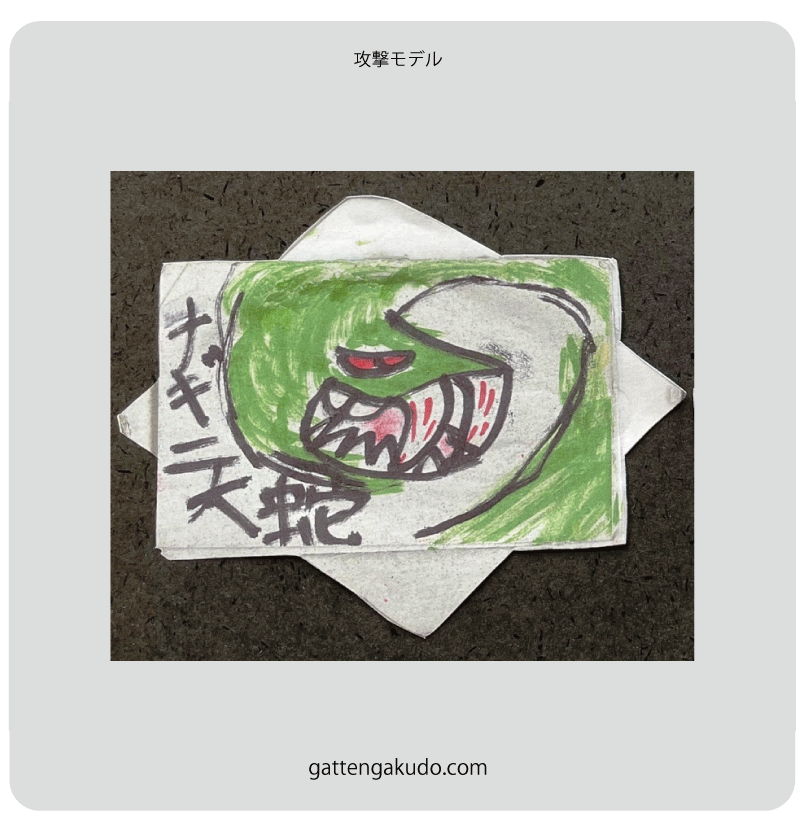
実際に強かったかどうかは問題ではありません。強そうな外観が大事なんです。

「守備モデル」の登場
攻撃モデルの登場を受け、今度は「守備モデル」が開発されるようになりました。
見た目の安定感と安心感が特徴です。

プレゼントモデル
ここまでで、読者の皆さんは、めんこワールドをかなり堪能していただいていると思うのですが、子どもの発想はとどまるところを知りません。
まだまだ続きます。
ある日、折り紙の作品を挟み込んだめんこを作る子が現れました。
「プレゼントモデル」の登場です。
もう何がなんだかわからない状態です。
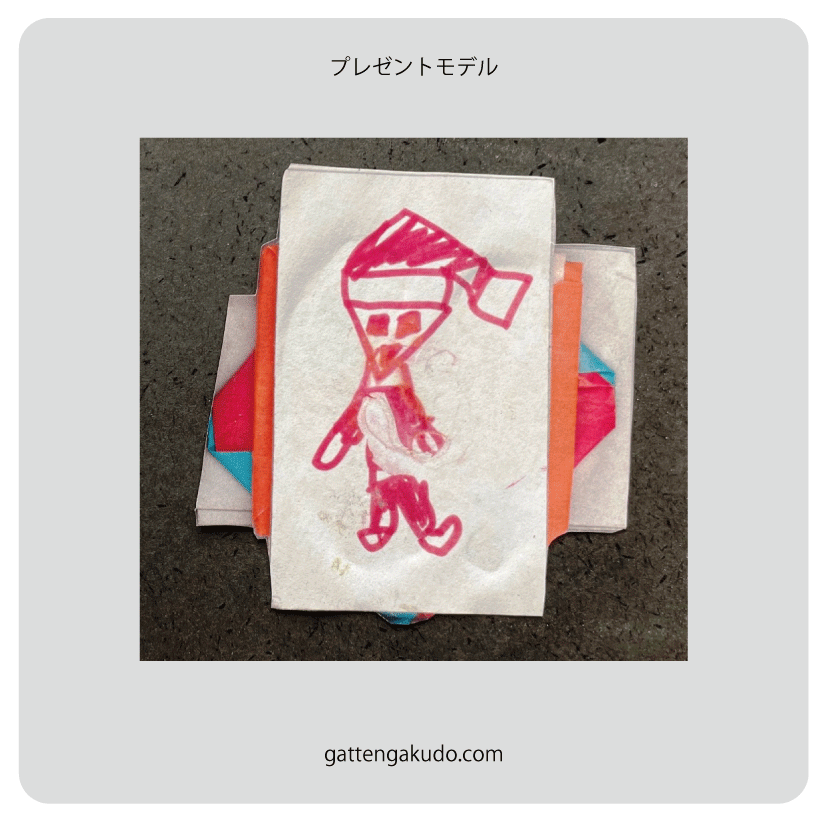
ゴージャスモデル
子どもの創造力はどんどんふくらんでいきます。
金のリボンを全体に巻き付けためんこが登場しました。
裏も表も同じなので、わかるように「うら」と書かれています。

ファンシーモデル
そのうち、スパンコールを表面に張り付けためんこも登場しました。
実用性よりかわいらしさを追求しためんこのことを「ファンシーモデル」と名付けました。
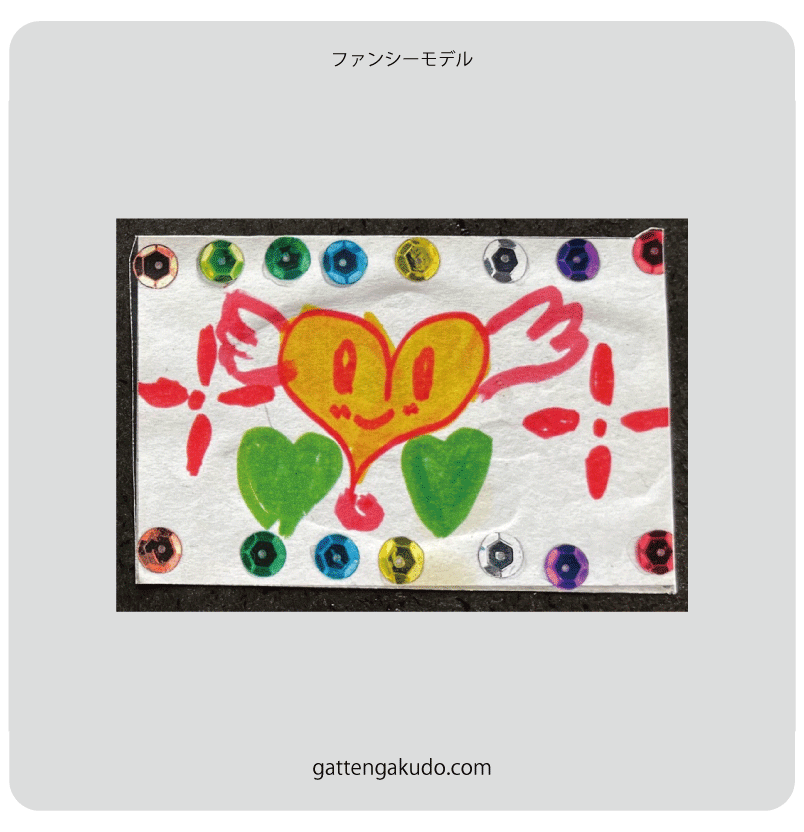
内部空洞式軽量化モデル
このめんこは、見た目にはわかりにくいのですが、内部を空洞にした構造となっています。製作者の子どもが「軽量化」を追求した結果生まれました。
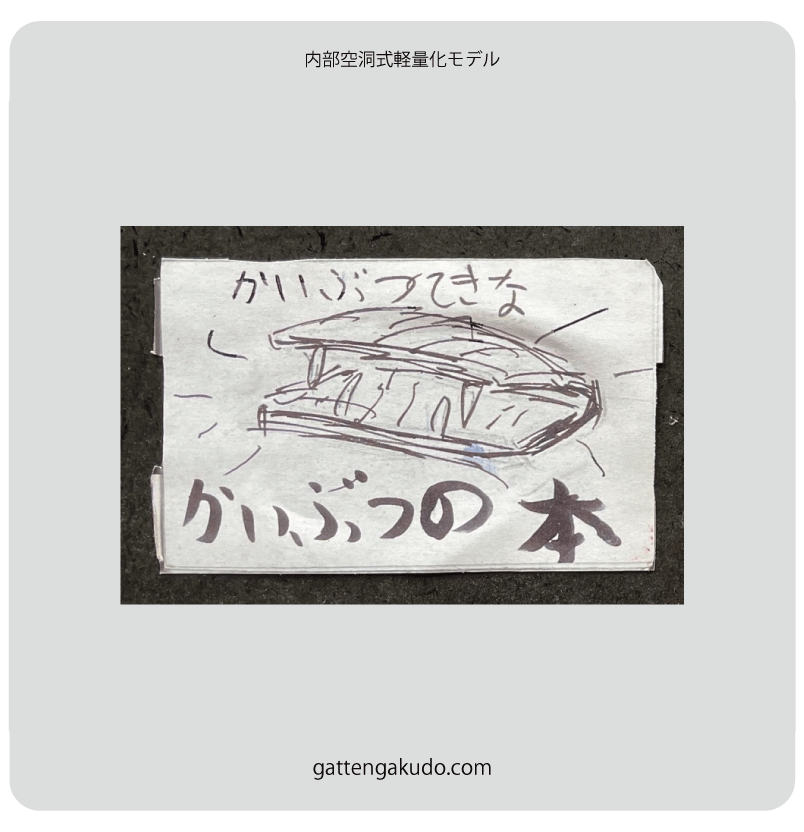
マグネットモデル
見た目は普通ですが、実は、磁石シートを内部に挟み込んでいます。冷蔵庫にくっつけることができるし、ものすごく重たくなります。
デザインからわかるように、作者は軽量化モデルと同じ高学年の子どもです。
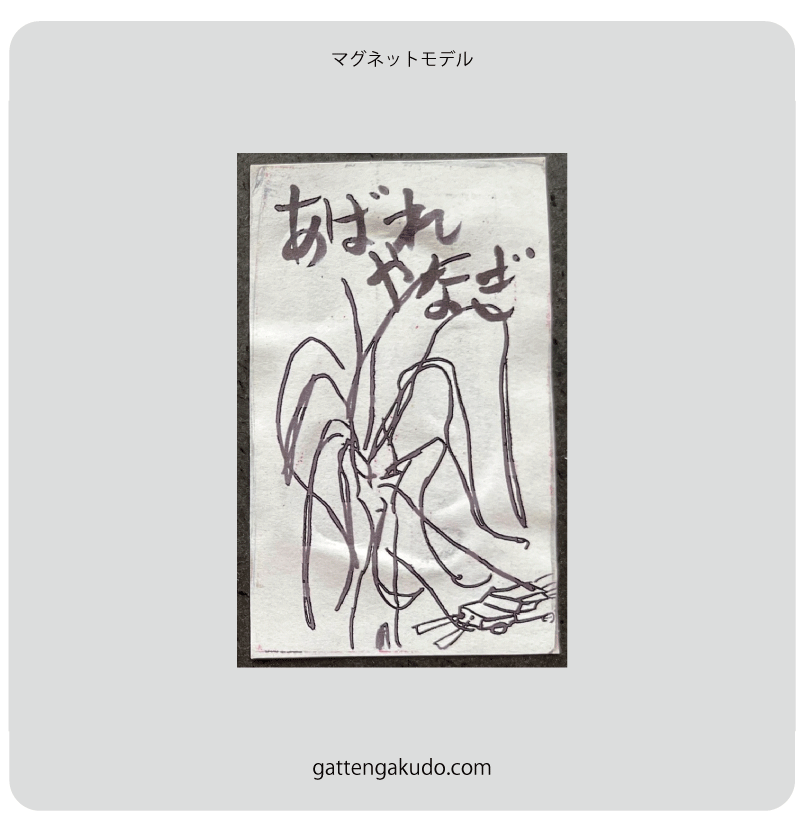
めんこの紙と紙の間に何かを挟み込むと強くなるという噂が拡がったことがあります。おまじないですね。
それがやがて、自分の髪の毛を抜いて挟み込むと魂が宿った最強のめんこになるという噂となり広がりました。
子どもたちも私も、めんこを作るときは、みんな毛を一本抜いて挟み込みました。
景品としてのめんこ
やがて、高学年の子どもが、景品となるめんこを自作して、自分で仲間を呼び集め、「めんこリーグ」を開催するようになりました。
学童の広場で遊んでいる子どもたちに、ハンドマイクで「今からめんこリーグを開催します!」と高学年が呼びかけるんです。すると、遊んでいた子どもたちが、わーって集まってくるんですね。
低学年の子どもたちがたくさん参加しました。
遊びが子ども達のものとなり、どんどん発展していったんです。
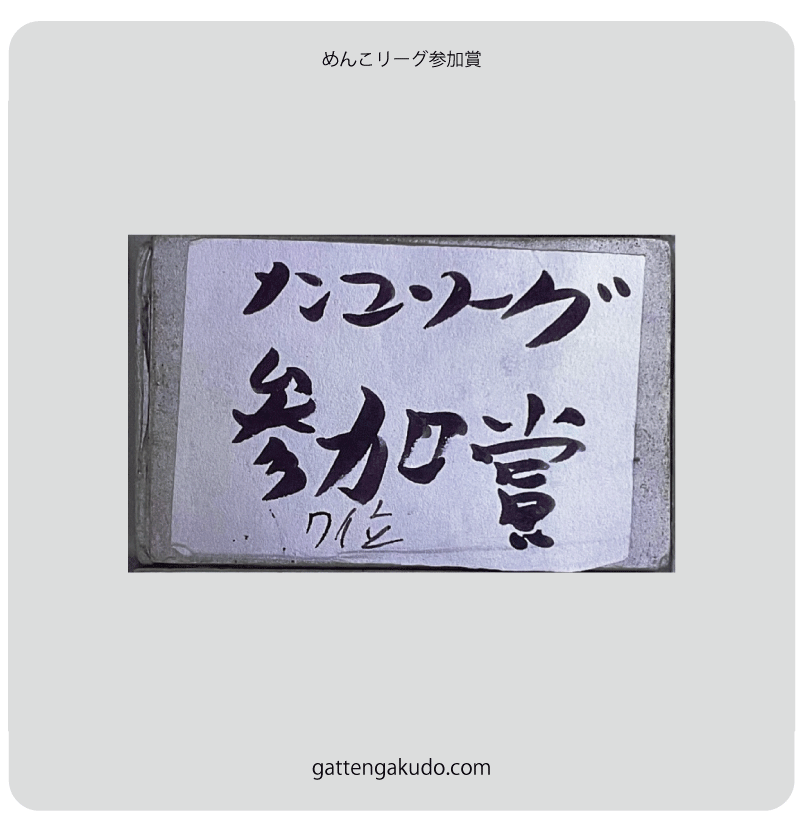
めんこコレクション
子ども達のめんこ作品はいかがでしたか?
私は、これまで紹介しためんこ(コピー)を額に入れて、学童に飾っていました。
遊んで楽しむだけでなく、見て楽しむことができるのも、めんこの大きな魅力だと思います。
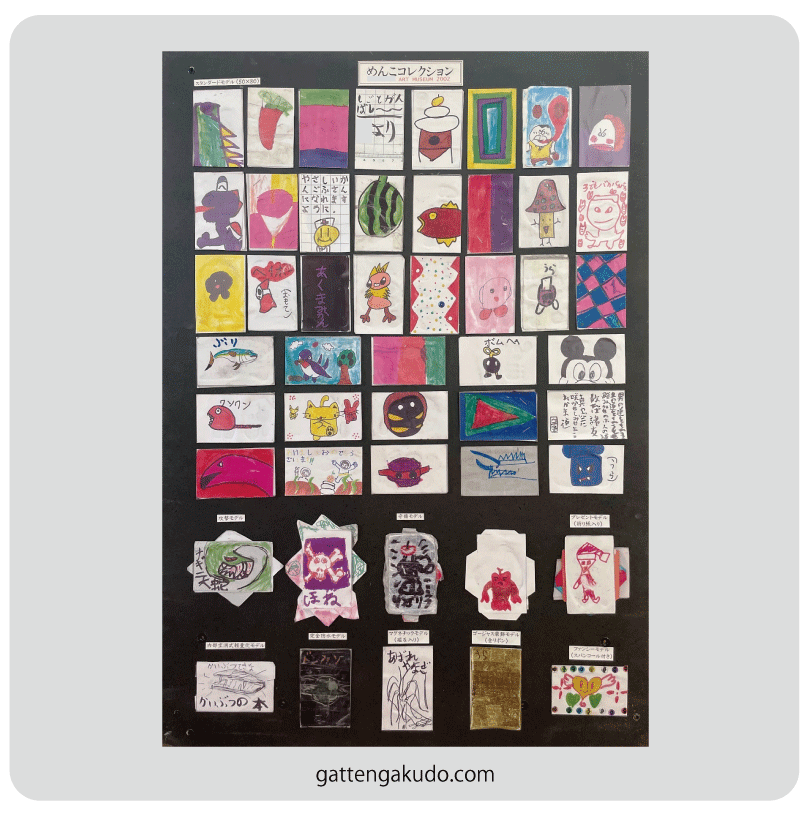
めんこの歴史
日本の伝承遊び「めんこ」の起源について触れておきます。
めんこの起源は、平安時代の資料に「意銭」などと書かれた遊戯だそうです。ただし、それより古い太古の時代には、子どもたちは貝殻や木の実・石などを使い同じような遊びをしていたと考えられてます。
明治時代には、めんこは鉛製だったそうです。しかし、鉛中毒の事件をきっかけに、私たちが馴染深い、紙製のめんこが登場したそうです。
参考:Wikipedia
めんこの作り方
めんこは、だいたいクレジットカードサイズの厚紙を数枚重ね合わせて作ります。大きさに厳密な規定はありません。ただし、同じサイズになるように紙をカットしておく必要があります。
私は、50㎜×80㎜サイズに紙を切って使っていました。
下に紹介するように、めんこ専用の用紙もありますが、割高です。私は、文房具屋で大きなボール紙を購入し、裁断機でカットしていました。
めんこを貼り合わせるのには、木工用ボンドを使用します
重しを乗せて1日ほど置いて、ボンドが完全に乾くと、カチカチに硬い完璧な平面のめんこが出来上がります。
強いめんこの条件は、「まったいら」であることです。表面が波打っていたりすると、床に置いた時に「浮き」ができて、そこを狙われると簡単にひっくり返されてしまいます。
そのために、ボンドを乾燥させる過程では、フローリングの床にめんこを並べて、学童机をひっくり返して、天板と床で挟み込んで一日置いたりしました。
待ちきれない場合は、セロハンテープで補教すると、すぐに遊べるようになりますが、ふにゃふにゃのめんこになってしまいます。
必要な材料・道具
- ボール紙(同じサイズにカットしたもの)
- 木工用ボンド
- 絵を描く道具(油性マジック・ポスカ・色鉛筆・クレパスなど)
- セロハンテープ(補強用)
作る手順
- 絵を描く、(裏・表2枚)
- めんこ用紙を貼り合わせる(絵を描いた紙の間に1~2枚紙を挟み込む)
- 乾かす(重しを乗せると丈夫なめんこになります)
めんこの用紙となる厚紙やボール紙は、文具店やホームセンターで購入することができます。
カッターナイフや裁断機で、正確に同じ大きさになるようにカットします。

ボール紙 片面白 約1.9㎜厚 A3 20枚 (297㎜×420㎜) 【工作用】

割高になりますが、便利なめんこ用紙もありますよ。
時間と手間をかけたくない方は、メンコ用紙の購入をおすすめします。

めんこ用紙無地100枚セット 708円(メルパオ)
めんこの遊び方

めんこには色々な遊び方がありますが、代表的なものは、「裏返したら勝ち」というルールです。
一人でも遊べるし、団体戦のように、たくさんの仲間で遊んで盛り上がることもできます。
個人戦(1対1)
【遊び方①】
- お互いに1枚ずつめんこを床に置きます。
- じゃんけんをして勝った方から、自分のめんこを拾って、相手のめんこに向かって勢いよく叩きつけます。
- ひっくり返した方が勝ちです。

投げる時以外、自分のめんこをさわることはできません。
有利な場所に自分のめんこを勝手に動かしたりするのは反則ですよ。
「3枚勝負」や「5枚勝負」のように、あらかじめ数を決めておいて、裏返えされたら、新しいめんこを出し、決まった数を全部裏返されたら負け、という遊び方もありあります。
備考ですが、裏返されためんこが一回転または数回転して同じ向きになることがよくあります。その場合はセーフです。
「表⇒裏」または「裏⇒表」となったら負けです。
【遊び方②】
- お互いに「3枚」「5枚」など、同じ数のめんこを床に並べます。
- じゃんけんをして勝った方から、自分のめんこを拾って、相手のめんこに向かって勢いよく叩きつけます。(自分のどのめんこを拾うか、相手のどのめんこを狙うかは自由です。)
- 裏返されためんこは、ゲームから除外します。
- 相手の最後の1枚のめんこを先に裏返した方が勝ち。

床にめんこがたくさんあると、めんことめんこが重なり合う場面が生まれ、盛り上がります。
重なった状態は不安定になるので、裏返しやすくなるんです。チャンスやピンチの場面が多いと盛り上がります。
団体戦
【遊び方①】
- 2チームに分かれます。
- 3対3の勝負だと、一人1枚ずつめんこを出し、床にならべます。
- じゃんけんをした人から時計回りで、自分のめんこを拾い、相手チームのめんこを狙って投げます。(相手の誰を狙うのかは自由)
- 相手チームにめんこを裏返された人は、その後のゲームに参加できません。
- 相手チームの全てのめんこを先に裏返したチームが勝ちです。

子ども同士の協力プレーができるため、とても白熱します。
【遊び方②】
- 2チームに分かれます。
- チームごとに順番を決めます。(先鋒・次鋒・中堅・副将・大将など)
- 最初の一人が1枚ずつめんこを出し、裏返されたら、次の人がめんこを出します。
- 先に相手チームの最後の一人(大将)のめんこを裏返したチームが勝ちです。
<団体戦の「助太刀」ルールについて>
相手のめんこが自分の上に重なった時は、チャンスですが、自分のめんこを拾うとその状況が失われます。なので、このような場合に限って、自分のチームの次の順番の人が攻撃をすることができます。

これらのルールはほんの一例です。子どもたちがルールを作り、仲間の合意のもと、ルールを拡張していく過程を大切にしてください。
めんこは、床で楽しむことができますが、座布団を敷いたり、机の天板や段ボールなどで「フィールド」を作って、その上で勝負をすることもできます。
床で遊ぶより、イレギュラーな状況が生まれやすく盛り上がります。
めんこの持ち方
めんこを投げる時は、写真のように親指とそれ以外の指で挟むようにして持ち、地面に向かって投げつけます。
地面と平行になるタイミングでめんこを離さないと、めんこの角が地面に直撃してめんこが痛みやすくなります。
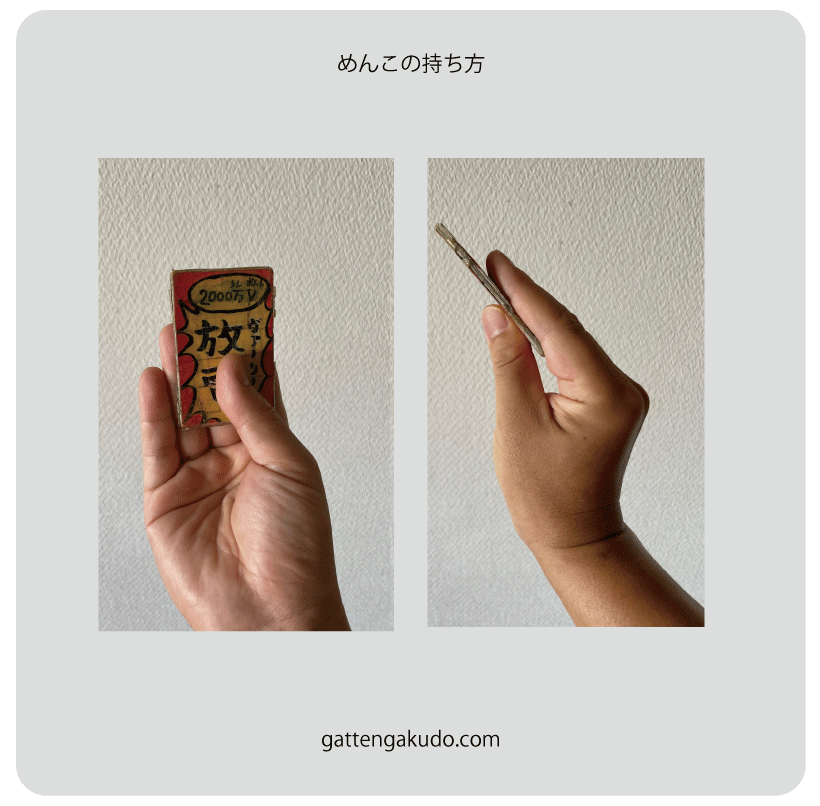
めんこは室内の格闘技
めんこを投げる動きは、ドッジボールや野球のボールを投げる動きとよく似ています。
最初は上手く床に投げられない子どももいますが、慣れてくると、
ピシャッ!!
と気持ちの良い音がするようになります。
めんこが上手に投げられるようになると、ボールも上手く投げられるようになります。
高等技術ですが、相手のめんこに直接当てずに、わずか横の床に投げつけ、「風圧」で相手のめんこを裏返す「風めん」という技があります。
一日めんこをしていると、大人の私でも利き腕の右手だけ筋肉痛になることもありますので、なかなかの運動量です。

雨の日や猛暑日で外遊びができない日に、元気な子どもたちが室内で思いっきり発散できる最高の遊びですよ。
めんこで遊ぶ時の注意
遊びが白熱すると、よく見ようとする子どもたちが、床に顔を近づけることがあります。
床から跳ね返っためんこが顔に当たる危険がありますので、メンコをする時は全員が立ってやるように声をかけました。
また、めんこを投げる時は腕を思いきり振ります。その手が人や物に当たると危険です。子ども同士がお互いに距離をとり、周囲に物がない場所で遊ぶようにしましょう。
めんこの厚さと強さの関係
めんこを強くしたいがために、大量の紙を貼り合わせる子がいました。確かにこのめんこ、重くて攻撃力は抜群なんです。
しかし、守備力が激弱で、簡単に裏返すことができます。
逆に、紙を貼り合わせずに1枚だけの紙のめんこを作った子もいました。ぺらっぺらなので攻撃力は全くありません。
しかしこのめんこ、全く裏返すことができないんです。守備力が最強なんですね。
攻守のバランスが最も良いのが、3~4枚重ねのめんこです。
一度試してみてください。
めんこを作れるのは一日1枚?
私の職場の学童でめんこが大流行した時、毎日大量に用紙を準備するのですが、瞬く間になくなってしまうということがありました。不思議に思って調べてみると、子ども達が自分のロッカーに、めんこ用紙を何枚もキープしていることがわかりました。これでは、他の人がめんこを作れなくなってしまいます。
また、人より多くめんこを作ることに必死になり、雑に仕上げる子もでてきました。
そこで、子ども達と話し合い、「用紙のキープは禁止」「1日一人1枚だけめんこを作る」ルールができました。それ以来、子ども達は、1日1枚のめんこを丁寧に作るようになりました。
めんこを作るルールについても、子どもたちと相談して決めてください。
さいごに・・・

じゃあ、みんなでめんこをやってみようか!?

やりたい!

私も!

僕も!!
いかがでしたか?
この記事を読んで、めんこの楽しさを感じていただけた方は、ぜひ子どもたちとめんこをやってみてくださいね。
めんこのように素朴で拡張性の高い伝承遊びは、子ども達の興味や創造力を存分に刺激してくれます。学童保育の遊びに最適です。
余談ではありますが、最近、私の職場の学童保育所でも、放課後の遊びの時間がどんどん短くなり、かつてのように子どもたちが「遊びこむ」ことが難しくなってきています。
学童全体を巻き込むような、熱狂的な遊びの盛り上がりや、「遊びの渦」を作ることができるのは、夏休みなどの長期休みくらいかもしれません。
それでも、私は、遊びの持つ力、子どもの遊びこむ天才的な力を信じて、日々子どもたちとかかわっています。
(おわり)
こちらもCHECK
-
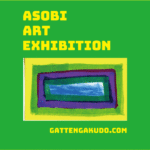
-
【学童保育】放課後の遊びの作品集「学童に落ちていた紙に描かれた子どもの遊びの世界」
続きを見る










