新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!

目次
人間関係で悩みを抱える指導員の皆さんへ

学童保育って、人間関係の悩みが尽きないですね・・・
大人数の職場なら、苦手な人を避けることもできると思いますが、学童保育のような少人数の職場の場合、必ず毎日顔を合わせないといけません。
実は私も、指導員になりたての頃は、苦手な人との人間関係に悩み、カウンセリングや安定剤の処方を受けた経験があります。
自分で言うのもなんですが、今ではすっかりたくましくなりました。
もちろん、悩んだり落ち込んだりすることは日常茶飯事ですが、大きく心身のバランスを崩すということはなくなりました。
面の皮が厚くなったということでしょうか。
今となっては、若い頃に、自分は大切な経験をした、勉強をさせてもらったと、私を悩ませてくれた人たちに感謝しているくらいです。
最初に言っておきたいことは、長い目で見ると、苦手な人とペアを組んだ経験、人間関係で悩んだ経験は、自分の糧となるということです。
そして人間関係の経験値は、別の職場に移ったときにも役に立つ一生ものです。
今回の記事では、苦手な相手と一緒に仕事をしていくうえでのポイントをまとめています。私自身が悩んだ経験やそれを乗り越えた経験も書いていますので、参考にしていただければ幸いです。

今まさに悩んでいる指導員の皆さんは辛いですよね
この記事の目次
- 苦手な人と一緒に働くときのコツ
- 子どもとのかかわりを苦手な人とのかかわりに生かす
- ポイントは「子どもが大切にされている」職場かどうか
- 学び続けることで乗り越えられる
- 「クセが強い人」とペアになった時
- 「やる気がない人」とペアになった時
- アルバイト指導員に呼び出され墓地に
- 頑固な上司・先輩とのかかわりのコツ
- 結局自分が青かった
- 施設長になって・・・
- 最後に・・・人間関係は変化する
- おまけ(元気が出る動画)
なお、この記事の内容は、ハラスメントや職場倫理に大きく反することのない範囲での人間関係の問題を扱っています。そのような場合は、また対応が変わってくるという前提で続きをお読みください。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】がってん学童所長にパワハラ疑惑?「ハラスメントの種類や対策 について」
続きを見る
苦手な人と一緒に働くときのコツ

苦手な相手とかかわる時のポイントです
ポイント
- どこが苦手なのかを分析する
- 見方を変える
- 気にしすぎない。普通にふるまう
- 好きになる必要はない
どこが苦手なのか分析する
苦手な人と関わっていると、どんどん相手のことを意識してしまい、相手のすることなすこと全てが嫌に思えて、そのうち存在自体が嫌に思えてしまうことがあります。

これは相手の嫌な部分に捉われてしまっている状態です
苦手な相手と自分の関係を、ちょっと離れた視点から、客観的に眺めてみてください。
自分自身の苦手意識を分析するのです。
そうすると、相手のどの部分が苦手なのかが見えてきます。
- いつもイライラしている
- 愚痴や悪口ばかり言っている
- 不公平・えこひいきをする
- やる気がない
- ミスを認めない・人のせいにする
- 一貫性がなく、いつも言うことが違う
- 空気が読めない
- いい加減・ちゃらんぽらん
- マイナス思考
- ずるい・卑怯
などなど、その人の言動の中に、自分が受け入れられない、尊敬できない部分があるから、相手のことを苦手に感じてしまうのですが、それは実は、その人の一部だったりするものです。
見方を変える

なぜその人は、そんな言動をしてしまうのでしょうか
今度は、相手の言動を分析してみましょう。
その人がそんな態度をとるのは(そんな態度をとることしかできないのは)その人自身が満たされない気持ちを抱えているからかもしれません。
その人は「自己重要感」が持てない人で、自信がなく、だからこんな風に人にイライラをぶつけたり、人を見下すことで自分の存在をなんとか守ろうとしている・・・。
相手の言動の理由や背景を分析することで、実はその人も自分と同じで困っている人かもしれない、いや、自分以上に苦しんでいる人かもしれないことに気付くことができると、苦手な相手を乗り越えたも同然です。
気にしすぎない・普通にふるまう
苦手な相手であっても、自然にふるまい、他の人に対するのと変わらず、挨拶やお礼を言うようにします。
無理に話を合わせたり、プライベートの話をする必要はありません。疲れるだけです。
ただ、仕事上必要なコミュニケーションと割り切って、むしろ丁寧に対応するようにします。

相手のペースに乗らない、自分のペースを守る
好きになる必要はない

苦手な人がいて当然、無理に受け入れようとしなくて大丈夫です
相手のことを苦手と思う自分を否定したり、苦手を克服しないといけないと自分を追い込むようなことはする必要は全くありません。
苦手な人、嫌いな人がいて当然です。
10人いたら、その中に好きな人が1人くらいいるのと同じで、必ず苦手な人が1人くらいいるものです。
苦手でもいいや、嫌いでもいいやと思えると、随分気持ちが楽になりますよ。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】指導員の呼び方は「〇〇先生」なのか「あだ名」なのかどっちがよいかの問題
続きを見る
子どもとのかかわりを苦手な人とのかかわりに生かす

指導員としての子どもとのかかわりを、苦手な人との関係に置き換えてみましょう
学童保育の指導員は対人援助職です。普段の子どもとのかかわりの中で、普通に考え行っていることは、苦手な相手とのかかわりに通じています。
上にあげた苦手な相手の言動をもう一度書いてみます。
- いつもイライラしている
- 愚痴や悪口ばかり言っている
- 不公平・えこひいきをする
- やる気がない
- ミスを認めない・人のせいにする
- 一貫性がなく、いつも言うことが違う
- 空気が読めない
- いい加減・ちゃらんぽらん
- マイナス思考
- ずるい・卑怯
こんな一面を持った子ども、学童にいませんか?

いっぱいいますよね~
みんな何かしら課題や問題を抱えているものです。
そんな子どもたちに、私たち指導員は歩み寄り、課題は課題と捉えつつ、その子の良い面を一つでも多くみつけようと関わっていきます。
「困った子は困っている子」とその子の問題行動の背景を探ったり、「みんな違ってみんないい」と違いや個性を認めながら、その子が指導員との関係や学童保育という場所の中で安心感を持てるように信頼関係を1mmずつ紡いでいく。

「子どもは許せても相手が大人なら許せない」という気持ちはめちゃくちゃわかりますが・・・
私が言いたいことは、指導員の皆さんは、他者を受け入れること、信頼関係を構築することに関しては、日頃から鍛錬を積んでいるのだから、少し考えをシフトすることで、苦手な相手とうまく付き合うことができるようになるはず、ということです。
ぼちぼち行きましょうね。
ポイントは「子どもが大切にされている職場かどうか」
ここまで、苦手な相手とどう付き合うかということを書いてきましたが、私は、こと学童保育所の人間関係を考える上では大事なポイントがあると思っています。
それは、苦手な相手の言動が、「子どもの権利」に反していないか、そこまであからさまではなくとも、子ども達が安心して過ごせる学童保育の役割を損なうものでないか、ということです。
本来、子どもが安心して過ごせるためには、指導員のチームワークが重視されるべきです。
指導員間がゴタゴタしているのは、子どもにとっては不利益なことです。
苦手な人の言動がその人自身の問題であれば、その相手との対応を考えればいいのですが、職場としての雰囲気や体質が、そもそも「子どもの最善の利益」を真ん中に置いていない場合は、それは苦手な相手との問題というよりは、職場の問題となります。
様々な指導員の話を聞いていると、実際にそのような職場で、心ある指導員が深い悩みを抱えている事例があると感じています。指定管理で様々な運営母体が学童保育に参入する中で、子どもの成長や安心よりも、経営が優先されるような職場があることも一つの原因でしょう。

やる気があり、子ども達と関わること、学童保育の仕事が大好きな指導員が、職場の問題で消耗したり力が発揮できない環境にあるのはとても残念なことです
こちらもCHECK
-
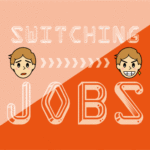
-
【学童保育】職場環境や人間関係から転職を考えている指導員の皆さんへ「転職のメリットとデメリットについて」
続きを見る
学び続けることで乗り越えられる
ここからは私の経験談です。
興味のある方は読んでみてください。
最初に結論を言うと、私にも苦手な人との関係で苦労した時期がありましたが、乗り越えることができたのは、結局のところ、学童保育という仕事が好きだったからです。
そして、苦手な人と同時に私の周りには目標とする尊敬できる指導員がたくさんいました。自分が理想とする保育がありました。

そのために学童保育について学ばないといけなかった
そうして学び続けていると、それ以外の悩みやなんやかやは、だんだんちっぽけに思えてくるものです。
今人間関係で悩んでいる指導員の皆さんにとっても、人間関係をよくする努力も必要だけど、学童保育そのものとしっかり向き合い学び続けることが、悩みを乗り越えることにつながると信じています。
「クセが強い人」とペアになった時
私が最初に悩んだのは、クセの強い人とペアを組んだ時でした。
私の相棒指導員だった人は、いわゆる「キャラの濃いタイプ」の人でした。
例えば、親父ギャグを連発する、2人きりで事務作業をしている時に、鼻歌で昭和歌謡を常に口ずさんでいる・・・などです。
私の調子の良い時は、適当に相槌を打って仕事に集中することができたのですが、こちらが疲れている時には、その鼻歌やギャグが神経に触るようになりました。
気になり始めると、相棒指導員の一挙手一投足をどんどん意識してしまうようになりました。
そして、他にも色々と重なり私は徐々に精神が不安定になり、受診をするに至りました。その相棒と過ごした計6年間の間に2度受診しました。
その間も仕事は休みませんでした。相棒と二人きりで過ごす時間はかなり辛かったし、受診している時期には、人生全てが嫌になったような心境でしたが、不思議と学童で子どもと一緒に過ごしていると、気持ちが落ち着きました。
職場に行く前は不安、行ってしまって子どもと関わるとそんな不安を忘れるという日々でした。ポケットの中に安定剤を入れてお守りのようにしていました。
2度目の受診の時には、少し慣れました。
今でも覚えていますが、受診した帰り道に自販機でジュースを買ったら、100円しか入れていないのに、なぜかお釣りが900円でてきたんです。その日の診察料が700円でしたので、チャラになって儲けが出ました。
なんかわからんけどラッキー!って思ったら、心の重荷がスッととれました。人の悩みって、そんな風に何かのきっかけで、フッと軽くなる時もあるんですね。
体と同じで心も風邪をひくことがある。また調子が悪くなったら病院に来て薬をもらったらいいや、って思えたんです。
それ以降は、自分の心が疲れてきたと思う時は、気分転換をしたり酒を控えて早寝をして回復を心掛けたり、自分の疲れをコントロールできるようになりました。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育指導員のチームワーク①】「中堅指導員」の私を疲れさせる理由は・・・
続きを見る
「やる気がない人」とペアになった時
やる気のない同僚とペアになった時などは、自分が一生懸命やっているとなおさら、腹が立ったり許せなかったりするものです。

やる気のない後輩と、やる気のない先輩では、話が変わりますよね
もちろんやっかいなのは、やる気のない先輩とペアになった時です
やる気のない後輩の場合は、先輩として、やる気を引き出す様々なアプローチを仕掛けたり、本当にこの仕事でいいのか相談に乗ったりすることもできるのですが、相手が先輩の場合はなかなかに大変です。
私の場合は、無断遅刻する、当日欠勤する先輩指導員と働いた時には、色々とやりきれない思いを経験しました。
しかもその先輩、保育や指導員の処遇改善については一家言ある人でしたので、なおさら「普段はあんないいこと言ってるのに~!口だけけか~い!!」と心で突っ込んでいる間はよいのですが、精神的な疲れを感じ始めた時に、このままではまずいと思いました。
ただ、保護者・地域の方たちは、実はそのへんはしっかり見てくれています。
自分の苦労を分かってくれている、応援してくれている保護者や地域の人と積極的に対話をして、ポジティブな空気を取り込むことで、前向きに頑張っていくことができたんです。
そして、仕事を続けていくうちに、だんだんイニシアチブが先輩から自分の方に移ってくるようになり、数年かかりましたが、自分のやりたいと思う保育を、自分が主導してできるようになっていきました。
アルバイト指導員に呼び出され墓地に?
先輩指導員との関係に悩みながらも、自分では充実した学童保育の生活を作れるようになったと満足していた頃に、私にとっては忘れられない出来事がありました。
職場のアルバイト指導員に「話がある」と呼び出されたのです。
彼は、美術の高校教師を目指して教職浪人をしている男性で、私より年下でした。家が近所なこともあり、プライベートでも付き合うようになっていました。
当時、私は子どもや保護者の信頼を集めているという自負がありましたし、自分の実践内容に自信もありました。
アルバイト指導員から、そのあたりの自分の頑張りを評価してもらえるのだろうと何となく思っていたんです。
その指導員は車で私の家に迎えに来ると、近所の夜景の見える墓地に私を連れていき、私に話をしました。
その内容が、「いっつも自分中心やで」というものだったので私は驚きました。そんなことを言われるとは思ってもみなかったのです。
彼は、学童の取り組みをやるときや発信する時に、いつも私が中心となっていて、スタンドプレーになっている、と指摘しました。正規職員二人のチームワークが感じられず、子ども達に悪影響がある、というのです。
自分では苦手な関係を乗り越えて精一杯頑張っているつもりだったけど・・・、私は客観的にはそのように目に映っていたことを初めて知りました。
彼からは大切なことを教えてもらいました。
同僚指導員のことを切り離すような保育をしてはいけない。子どもたちのためにチームワークを大切にする必要があること。
そして、相手との立場の違いがあっても(アルバイトと正規職員などの関係)自分の思っていることを率直に言うことの大切さ。
最後に、自分に自信がある時、調子に乗っている時はかえって自分のことが見えなくなる危険があること・・・
こちらもCHECK
-
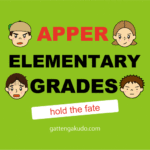
-
【学童保育】高学年保育の課題と取り組みを解説「高学年保育があなたの学童の命運を握る!」(前編)
続きを見る
頑固な先輩・上司とのかかわりのコツ
その後私は職場を異動することになり、新しい職員集団の中に入っていくことになりました。私が指導員になって6年経った時のことです。
理由の一つは、結婚して子どもが産まれ、父親になったことでした。
私の職場は、保護者運営の学童保育所で、不安定な経営だったのです。
家族のために、より安定した職場に移ることを決心しました。
異動のもう一つの理由は、学童保育のことをもっと学びたい、別の職場で自分を鍛えたいと思ったこと。指導員としてもっともっと成長したいと考えたのです。
異動して最初の1年はトイレ掃除を毎日しました。(1年後に先輩指導員から、「トイレ掃除が好きな人」と思われていることが発覚して、それからは交代でやることにしました。)
そして、誰よりも早く職場に行き、最後に職場を出るということを続けました。
新しい職場で出会った所長は、大変骨太な女性の先生でした。
保護者に言いにくいことも、子どもの立場からズバッと言うことができる人で、保護者の熱烈なファンが多い一方、敵も多い、そんなタイプの人です。
好き嫌いがはっきりしているので、嫌いな保護者ややる気のない指導員には厳しかったです。けど、子どものことでは決してブレない、温かいけど厳しくて頑固な人でした。
その所長とは、随分言い合いをしました。
私も子どものことで譲れないことは、はっきりと伝えるようにしました。
頑固な所長だから、きっとこの人が職員の時は、所長にガンガンに盾突いていただろうと思い、自分も言いたいことは言わせてもらいました。
しかしそれは、けんかではなく、子どものためにより良い方法は何か?という子どもを真ん中に置いた真剣な議論でした。そのような議論の中で、私は、私のやりたい思いがより明確になることに気付きました。
そんな関係が続き、所長が退任することになった時、「次はあんたに任せる」という一言をいただいたのです。
前所長には今でも色んな相談をしますが、だいたい怒られます。「子どものために、もっと親に、行政に言わなあかん!」「何でも受け入れてたらあかんで!!」と。そんな喝を入れて欲しい時に、会いに行ったりしています。
所長との議論の中で、私が一つだけ気をつけていたことは、相手を言い負かしてはいけない、ということでした。
先輩や施設長など目上の人と議論になった時は、言いたいことを言うのはいい、けれど、最終的に自分が折れること、そして、自分のやりたいことの40%ができればそれでよしとすることを心掛けていました。
相手のことも立てないと、関係が悪くなりチームワークに影響しますから・・・。やりたい保育のためには、焦らず、遠回りをすることも大切なことではないでしょうか。
結局自分が青かった
新しい職場で頑固な所長と出会って、色々と戸惑うこともありましたが、この時、前の職場で苦手な先輩と過ごした6年間の経験が生きました。
多少苦手な人・思い通りにならない人が相手でも、苦にならない自分に気付いたのです。
先輩指導員が自分を鍛えてくれたからです。この時、私は先輩指導員に心から感謝することができました。
そして、結局自分にだって至らないことや課題がたくさんあった、青かったんだと自分のことを振り返ることができたのです。そんな自分のことを先輩はよく受け入れてくれていたんだなと。
頑固な所長と過ごした期間、私は言いたいことを言いましたが、それも結局「言わせてもらっていた」だけなんだと今では思います。でっかい所長の掌の中で踊らされていたようなもの。
言いたいことをたくさん言わせくれた前所長にはいつも感謝しています。
自分も施設長になって、同じように子どものことで自分に向かってくるような指導員との関係は大切にしたいと考えています。
こちらもCHECK
-

-
生きていくために必要な「サボる力」
続きを見る
施設長となって・・・
施設長となった今、指導員の先生達が活き活きと働けるようにすることが自分の大きな役割となりました。
そのためには職場の人間関係は本当に大切です。

私が心掛けていることです
子どもが真ん中
全ては「子どもが安心して楽しく学童保育で過ごせるように、そして、子ども達が学童保育の生活や仲間とのかかわりを通して成長できるように」を中心に考える。そのためには指導員のチームワークが大切。子どもが大切=指導員が大切。
年休や休憩時間をしっかり取得する
指導員が働きやすい環境を整備することが大切。休憩時間はきっかり1時間。やり残した仕事はあるけど、自分が率先して弁当を開く。年休もしっかり消化する。余暇を充実させた方が、よい保育ができる。
休憩時間のコミュニケーションを大切に
お弁当後は、好きなマンガや映画の話、恋の話や結婚生活の苦労など、仕事以外の話をたくさんする。お互いのことを理解し合うとチームワークが深まる。休憩時間だから、外に出ても筋トレしても好きなことをして過ごしてもOK、強制ではない。
お互いに気遣う・協力しあう
子どもが風邪を引いたり親が体調を崩したり、家族の問題はお互いに仕事よりも優先する。仕事の代わりはいるけど家族の代わりはいない。自分が一番子だくさんなので、一番休むことが多いけど、「迷惑かけてごめん」とは言わない。ただただ「ありがとう!」
ベテランに無理をさせない
ベテランが無理をしていたら、職場全体がピリピリする。ベテランこそ休み方、手の抜き方を若手に教えるべし。とはいえ、みんな頑張り屋なので、どうしても無理をしてしまうことが課題。無理が続くときは仕組みを考え直す。
学ぶ
自分も学ぶ。指導員も学ぶ。外部からの刺激や目標は職員集団には大切。
距離感も大切
勤務時間外に所長からLINEなど回ってきたら嫌だろうと思うので絶対しない。というか自分はLINEをしていないだけ・・・。

仲良し集団ではないので、あくまでもより良い育成支援を行うため!
こちらもCHECK
-
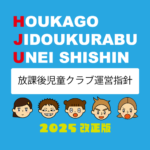
-
放課後児童クラブの「運営指針2025年改正版」一目で改正箇所がわかる!
続きを見る
さいごに・・・人間関係は変化する
人の世の常として、人間関係は、川の流れのように常に流動し変化します。
大人同士の関係も子ども同士の関係も同じです。自分も変わるし相手も変わる。古い人が辞めていったり新しい人が入ってきたり。
悩んでいる時はその状況が一生続くかのように思えますが、出口のないトンネルはありません。
まずは自分を労わることと、そしてポジティブな空気を胸いっぱいに吸い込むことです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

学童クラブは指導員の愛と苦労でできている!
クラブのクは苦労の「苦」
クラブのラブは「LOVE」










