新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
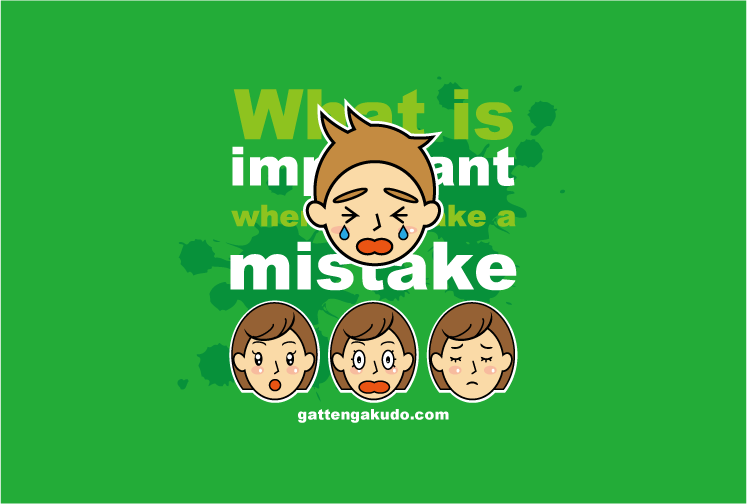
目次
ある日の保育後、

トゥルルル、トゥルルル・・・

はい、こちらがってん学童です!
あら、かける君のお母さん
どうなさいました?
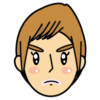
「さっきかけるが学童から帰ってきたんですが
頭を怪我しているんです・・・」

えっ??
けがやトラブルが発生してしまった時は、応急処置や子ども同士の話し合いなど、しかるべき対応をとり、保護者に連絡します。
私の職場では、次の表を基本的な対応としているのですが・・・
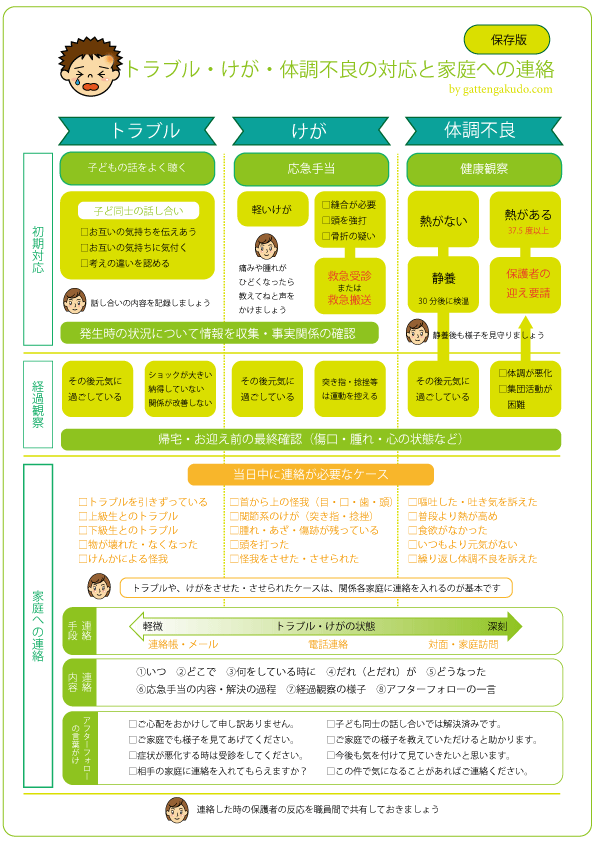
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】「図解でわかりやすい」けがや体調不良・トラブルの対応と家庭への連絡について
続きを見る
子どもがけがをしたのに、職員が気づかずに家に帰してしまった
ところが今日は、けががあった事実に職員が気付かず子どもを家に帰してしまいました。
保護者からすると、
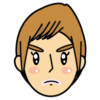
ちゃんと子どものことを見てくれているのかしら?
と、不信感につながってしまう場合も・・・。
そんな風に思うと職員は、

なんてミスをしてしまったのだろう・・・
と反省したり落ち込んだり、真面目な職員ほど、居たたまれない思いで胸が押しつぶされそうになってしまいます。
しかし、

落ち込んでる場合じゃない!
こんな時に私たち職員がしなければいけないことがあると思うんです。
今回の記事では、
- けがに気付かずに子どもを帰してしまった
- 発熱に気付かず子どもを帰してしまった
- トラブルに気付かず子どもを帰してしまった
これらのケースを、保護者からの連絡で、初めて職員が知ることになってしまった時の対応について、私の経験をもとに皆さんにお伝えしたいと思います。
この記事の内容
- あわてずに、詳しい状況を聞くことが大切
- (1)子どもが職員にけがのことを言わずに、そのまま帰ってしまった場合
- (2)子どもが職員にけがのことを言ったのに、そのまま帰してしまった場合
- 発熱やトラブルの場合は?
- ミスの原因を分析する
- 再発防止を講じる
- さいごに・・・
あわてずに、詳しい状況を聞くことが大切

あらためまして、がってん学童保育所で指導員をしているりえです
指導員歴は4年です。職場では、「中堅職員」ってポジションです。

指導員のたけしです
1年目の新人です
さて、今回のテーマ、「保護者からの連絡で初めて、けがやトラブルがあったことを知ってしまった時の対応」で、まず最初にやるべきことは、「詳しい状況を知る」ということです。
起こってしまったことはもう取返しがつきません。

だから、落ち着いて対応することが大切だと思います
以下は、保護者から連絡を受けた時の私の対応です。
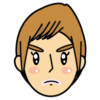
「さっきかけるが学童から帰ってきたんですが
頭を怪我しているんです・・・」

えっ?
(落ち着け私)
かける君は大丈夫ですか?
どのような怪我でしょうか?
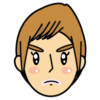
かけるは今晩御飯を食べています
おでこの右側にたんこぶができています

そうですか・・・
(詳しい状況は?)
出血はありませんか?
受診をする必要がありませんか?
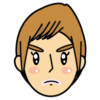
出血はしていません
受診はせず、とりあえず様子を見ています
このように、私は、まずは保護者とのやりとりで、できるだけ詳しい状況を把握しようとしました。

かける君のお母さんの話から、以下の状況を知ることができました
- かける君は頭にたんこぶを作っている
- 出血はしていない
- 受診の心配はないようだ
- 夕飯を食べれているので、元気ではいるようだ
とりあえず大きなけがではないことがわかり、少しだけホッとしました。
次は、けがをした理由についてたずねました。

かける君は、けがをした理由をどのように話していますか?
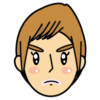
お友達と追いかけっこをしていた時に、転んで頭を打ったと言っています
かける君のお母さんだってその場にいたわけではないので、本人がどのように言っているのか、このことが大事だと思ったんです。

色々聞いてすいません
かける君はけがをしたことを職員に言ったのでしょうか?
この質問は私はとても重要だと思いました。
なぜなら、
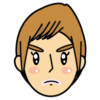
(1)いいえ
先生に言わなかったみたいです
という場合と、
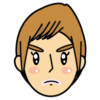
(2)はい
先生に言ったといっています
という場合では、職員が反省をしたり家庭に謝罪をするポイントが大きく変わってくると思うからなんです。
こちらもCHECK
-
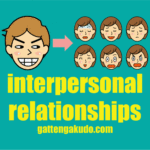
-
【学童保育】苦手な人とペアを組んだ時の対処法「職場の人間関係に悩んでいる指導員の皆さんへ」
続きを見る
(1)子どもが職員にけがのことを言わずに、そのまま帰ってしまった場合

かける君はけがをしたことを職員に言ったのでしょうか?
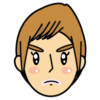
いいえ
先生に言わなかったみたいです
かける君は、けがのことを言わずに、そのまま家に帰ってしまったようです。
なぜそのようなことが起こったのでしょうか?
私は次のような場合が考えられると思いました。
- けがをしたが、遊びに夢中でそのまま遊んでしまい、そのうち忘れて家に帰ってしまった
- けがをした時点ではたいしたことはなかったので、先生に言わずに遊んでいたが、家に帰った頃になって腫れてきた
- 学童でけがをしたら先生に言えばいいことをかける君が知らなかった
- 子どもと先生との信頼関係ができておらず、けがのことを先生に言うことができなかった
いずれにせよ私は、私たち職員に反省すべき点があると思いました。
その点をふまえて、私はかける君のお母さんに次のように謝罪しました。

そうだったんですね
かける君のけがに気付いてあげることができずに申し訳ありませんでした
子ども達には日頃から「けがをしたら先生に言えばいいんだよ」と話してきたつもりですが、かける君にはちゃんと伝えることができていなかったんだと反省しています
これからは、かける君がけがをした時にもっと言いやすい関係を作れるようにしっかり見ていきたいと思います
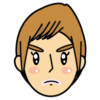
わかりました
まぁ今回は大きなけがではなかったのでよかったですが・・・

この件は、明日職員で共有して、再発防止に努めていきたいと思います
今日は本当にご心配をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした
私は少し考えて、今日のうちにかける君とも話しておこうと思いました。

あっ、すいません
ちょっとかける君とかわってもらっていいですか?
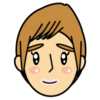
えっ?
ちょっとお待ちくださいね
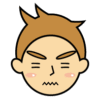
な、なんだよ~

かける君?
りえ先生だよ
今日はかける君が痛い思いをしたのに、先生気付いてあげられずにごめんね
けがは大丈夫?
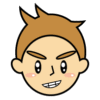
ぜんぜん
大丈夫だよ

良かった
りえ先生からかける君に一つだけお願いがあるの
今度けがした時は、ちゃんと先生に言ってね
手当をしないとひどいことになることもあるんだよ
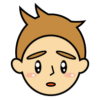
わ、わかった・・・

うん
約束だよ!
じゃぁ明日、学童で待ってるね!!

うん!わかった!!
(2)子どもが職員にけがのことを言ったのに、そのまま帰してしまった場合
次のような場合はもう少し話が深刻です。

かける君はけがをしたことを職員に言ったのでしょうか?
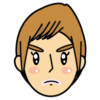
はい
先生に言ったそうです
子どもがけがをしたことを言ったのに、結果的にはそのまま家に帰してしまった。
この場合、指導員にはいくつもの反省ポイントがあると思います。
その前に、もう一点、私は大切なことをかける君のお母さんにたずねました。

その・・・
応急手当はしてあるのでしょうか?
かける君はなんと言っていますか?
この質問も大事だと思いました。
なぜなら、
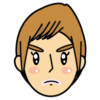
①応急手当はしてもらっているようです
という場合と、
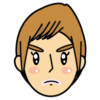
②応急手当もなかったようです
という場合でも、さらに、反省すべきポイントが変わってくると思うからなんです。

どんどん細かい話になってきちゃいましたが・・・
ミスをした以上、とことん事実を明らかにした方がいいと私は思っているんです
こちらもCHECK
-
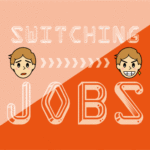
-
【学童保育】職場環境や人間関係から転職を考えている指導員の皆さんへ「転職のメリットとデメリットについて」
続きを見る
①応急手当をしていた場合
子どもが職員にけがのことを伝え、応急手当も行われていた場合、今回のミスは、
職員間の伝達ミス
そしてそのことが原因の
保護者への連絡ミス
ということになります。

けがの対応が職員間で共有されていなかったのです
②応急手当がなかった場合
子どもが職員にけがのことを言ったのに、応急手当がなかった。
なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。
お母さんとのやりとりでは、これについては知ることはできません。
私は思い切って、お母さんに、最も大事なことを聞きました。

かける君は先生にけがのことを言ったんですよね
だれに言ったと話していますか?
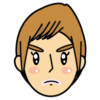
若い男の先生に言ったって話してます
若い男の先生?それならうちの学童に一人しかいないわ。
私は、ひとまず

わかりました
職員に確認して折り返しご連絡さしあげます
と言って、電話を切りました。
幸い、指導員のたけし先生が学童に残っていたので、直接たずねることができました。

たけし先生、かける君のお母さんから電話があったんだけど・・・
今日、かける君が頭をけがしたこと知ってる?

あっ!

忘れてたのね・・・
ここでも私は、なぜ、たけし先生がけがのことを忘れてしまったのかを、知ることが大事だと思いました。
なので、冷静に、たけし先生と話をしました。

なんで忘れてしまったの?

かける君が言いに来て、頭を見たんだけど、腫れたりはしていなかったから・・・
それにかける君その後も元気だったんで、たいしたことないと思いました

家に帰ったら、頭にたんこぶができていたんだって
それでお母さんが心配して電話をかけてきたんだよ

えっ?・・・
私はたけし先生にあらためて次のことを確認しました。
- けがの発生を知ったら、自分だけで判断せずに職員間で相談すること
- 特に頭のけがは重大なケースにつながる危険があること
- けががあって元気に過ごしていても、帰り際に傷を確認することがとても大切だということ

これからは、小さなけがでも必ず報告しあおうね
その後で、もう一度かける君のお宅に電話をしました。
かける君のお母さんには、たけし先生はけがの状態を見て、たいしたことないと判断してしまったことを伝え、お詫びしました。
たけし先生に、電話をかけてもらい、直接お母さんに謝罪してもらおうかちょっと悩みましたが、ここは先輩の私が連絡した方がよいと判断しました。
こちらもCHECK
-

-
保護者対応の基本は 「みんな違ってみんないい」?
続きを見る
発熱やトラブルの場合は?
今日の出来事は「けがをしたことに気付かずに家に帰してしまった」というケースでしたが、同じように、「発熱」や「トラブル」に気付かずに家に帰してしまった、ということが過去にはありました。

家に帰ってきたら38度の熱があったんですが!
というケースや、

泣きながら帰ってきたんですけど、どういうことですか?
など、保護者からの連絡で指導員が初めてそのことを知ったということがありました。

このようなケースも、けがの時の対応と基本的にはかわりません
まずは落ち着いて、詳しい状況を保護者から聞くこと。
詳しい状況を知らずに、とりあえず謝罪して終わらせてしまうようでは、その後に大切なミスの分析や再発防止があいまいとなってしまいます。
こちらもCHECK
-
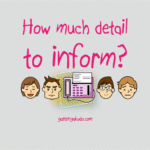
-
【学童保育】保身?事なかれ主義?子どものトラブルを保護者にどこまで伝えるかの問題
続きを見る
ミスの原因を分析する
子どもの安全を守る、私たち学童保育のような施設では、もちろん私たち職員は、日頃から子どもの状況をつかむように努めています。
それでも、ふとした瞬間や職員の死角に、けがやトラブルはは潜んでいるものなんですよね。

こんなこと言うと言い訳がましくなっちゃうんだけど~
十分な職員体制じゃない職場もたくさんあるんです。一つのトラブルの対応に追われている裏で、別のけがやトラブルが起こってしまうことだってあるわけで・・・。
けがやトラブルに気付けないことだってあるんです。

だからこそ、今回みたいなミスが起こった時は、原因をしっかりと分析しましょう
何が問題だったのか?
- 子どもの行動に要因があったのか?
- 職員の保育内容に要因があったのか?
- 職員間の連携に要因があったのか?
- 環境に要因があったのか?
多くの場合、けがやトラブル、そして職員のミスは、これらの要因が重なって発生してしまうんですよね。
再発防止を講じる

私たちは、翌日の職員会議で、今回の一件について、状況の分析と再発防止について話し合いました
ミスが発生した時は、私と、たけし先生で対応をしたんですが、あらためて所長や他の職員とこの件を共有し、対策を話し合いました。
「転んでもただでは起きない」
と言いますが、私は、ミスをした時には、必ず「再発防止」までをセットにして考えることが、より安全な保育を目指す上で大切だと思っています。
それに、保護者との信頼回復も忘れてはいけませんよね。
翌日の夕方
翌日、職員会議で話をして、保育後に私は、たけし先生と一緒に、かける君を家まで送っていくことにしました。
直接お母さんと話したかったからです。
今回、かける君のけが自体は大きくなかったけれど、応急手当や家庭への連絡ができていなかったことは重大です。

重大なケースは、電話ではなく、「対面」で話をする必要があると私は思っているんです。

ただいま~!!
りえ先生とたけし先生が来てるよ!
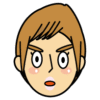
えっ?
先生が?

昨日のこと、お母さんに直接お詫びしたくて来ました
突然ですいません

昨日はご心配をおかけして申し訳ありませんでした
とても反省しています・・・
私達は、お母さんにあらためてお詫びをして、同時に、今日の職員会議で、全職員で共有したことや再発防止について話し合ったことをお伝えしました。
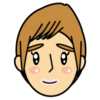
そんな・・・
けがも大したことなかったし、もう大丈夫ですよ
逆にそこまでしてもらって申し訳ないわ

いえいえ、私たちの仕事は、子どもの安全を守り、保護者に安心して預けてもらえるようにすることですから、当然です
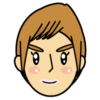
今日はわざわざありがとうございました
これからもよろしくお願いしますね
このように、今回は大事にならずに済みました。
「転んでもただでは起きない」
だれだって、どの施設だって、今回みたいなミスは起こって欲しくない。
けれど、起こってしまったからには、その後の対応をしっかりすること。
これからもそのことを大事にしていきたいと思いました。
さいごに・・・

私が、これまでの経験で学んだことですが・・・
ミスをした時に、「そのことを真摯に受け止めて、改善しようとしているかどうか」、この点を保護者は実によく見ていると私は思っています。
保護者も仕事をしている以上、どんなに注意しても起こる時にはミス起こるものだということを知っています。
だから、ミスそのものよりも、ミスが発生した時の対応によって、信頼がおける職員(施設)かそうでないのかを判断するんだと思うんですよね。
まずは真摯にミスを受け止め、お詫びをすること。
そして、なぜそのようになったのかを分析し、再発防止の措置をとること。
謝るだけではだめなんです。落ち込んでいてもだめです。
次に同じことが起こらないように、どのような対応をするか。

えらそうなこと言ってすいません
あっ、それと、私はやっぱり、職員は一生懸命に頑張るけど、子どもの全てを把握できるわけではないということを、あらかじめ保護者に伝えておくことも大事だと思っています。
これは、ミスが発生した時に言うと言い訳にしかならないから、普段からこんな風に保護者に伝えておくんです。

保護者の皆さん、私たち職員は子ども達のことを一生懸命に見守ります
けれど、私たちの施設には本当に大勢の子ども達が過ごしています
時には、けがやトラブルに気付けずに帰してしまうことがあるかもしれません
保育中の出来事で気になることがあったら、どんなに小さなかことでも構いません
職員までご連絡をください
よろしくお願いします
そして最後の最後に、子ども達がトラブルを通して本物の仲間になっていくように、けがやトラブルを乗り越えて、職員と親の関係も深まっていきます。
子どもが成長して学童を辞める時に、
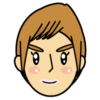
先生、本当に色々なことがあったよね

そうですね
色んなことがありました
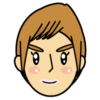
かけると私、ここに通えて成長することができたよ

私も、かける君とお母さんから、たくさんのことを学ばせてもらいました・・・
って、いつか言い合える日がくるかな・・・。
そのためにも、子どもや親のことを思って、丁寧な対応を心掛けていきたいと思います。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】理解と共感を拡げるための取り組み「発信」について
続きを見る










