新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
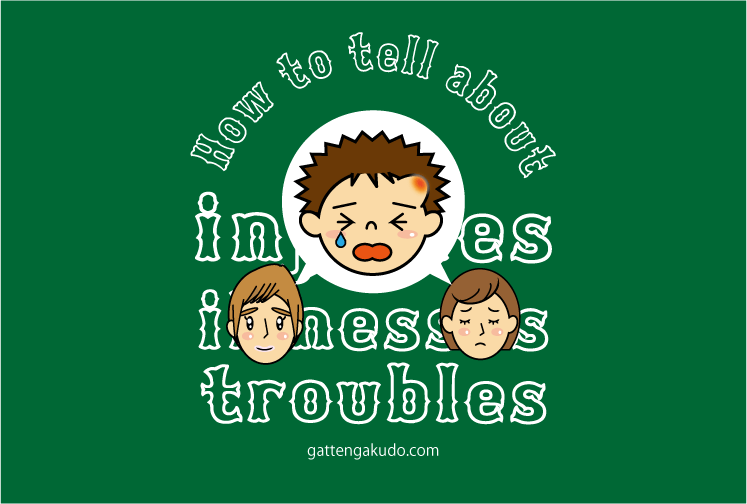
目次
今回のテーマは、けがや体調不良、トラブルの際の家庭への連絡についてです。
学童保育や保育園など、子どもを預かる施設では、どんなに注意をしていても、けがやトラブルが発生します。
そんな時に、どのように家庭に伝えたら良いのか、悩んだり迷ったりすることがありますよね。
大切なことは、施設でけがやトラブルの連絡や報告について、一定の基準を作り職員で共有しておくこと。
そして、その基準に縛られずに、柔軟に運用していくことです。

はっきりと基準に従ったらいいじゃないっすか?
なぜ柔軟にする必要があるんすか?

それはこの記事を読んだらわかると思うよ
この記事の内容
- けがやトラブルの家庭への連絡は難しい?
- その日のうちに連絡が必要なケースは?
- 家庭への連絡手段
- 家庭への連絡内容
- 連絡に迷った時は?
- 家庭への連絡のワンポイント
がってん学童には、次の表のような、保護者連絡についての一定の基準があります。
今回は、資料「けがや体調不良・トラブルの対応と家庭への連絡」をもとに、特に下半分の「家庭への連絡」について詳しく説明していきます。
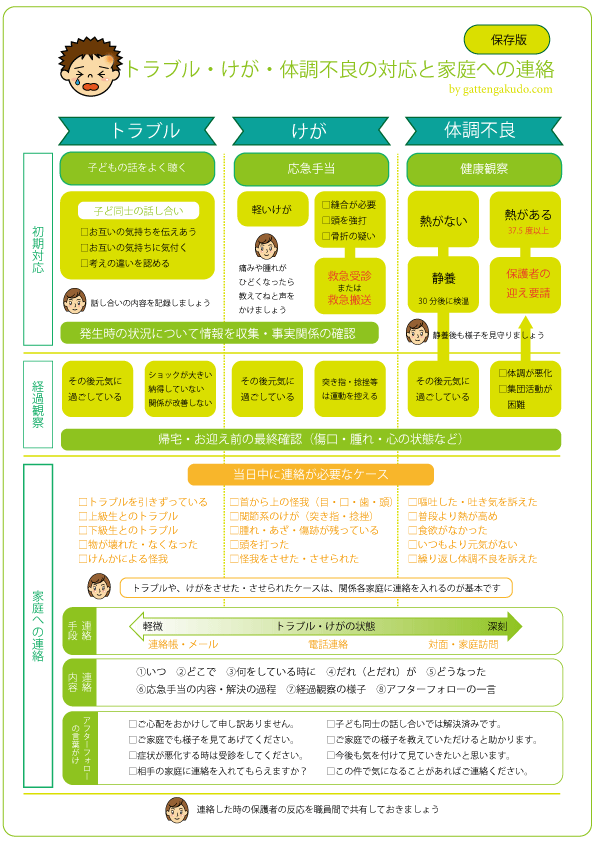
この資料、けがやトラブルの対応から家庭への連絡まで、シンプルにまとめています。
ぜひプリントアウトして職員で共有して欲しいと思います。
けがやトラブルの家庭への連絡は難しい?

家庭への連絡は、いつも悩みます

ベテランでも悩むくらいだから、新人の先生はプレッシャーが大きいだろうね

ぼくは1年目なんで・・・
家庭への連絡は、けがやトラブル対応の一連の流れの中で、最後のしめくくりとなります。
けが・トラブル対応の流れ
- 初期対応
- 経過観察
- 家庭への連絡

家庭への連絡のもとになるのは、初期対応やその後の経過観察です
これをしっかりとすることが大切です
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】理解と共感を拡げるための取り組み「発信」について
続きを見る
その日のうちに連絡が必要なケースは?

私がまず悩むのは「その日のうちに連絡が必要かどうか」です・・・
あたりまえのことですが、職員には退勤時間があります。何から何まで連絡していたら、連日超過勤務になってしまいます。
まずは、どのようなケースが、当日中の連絡が必要か見ていきましょう。
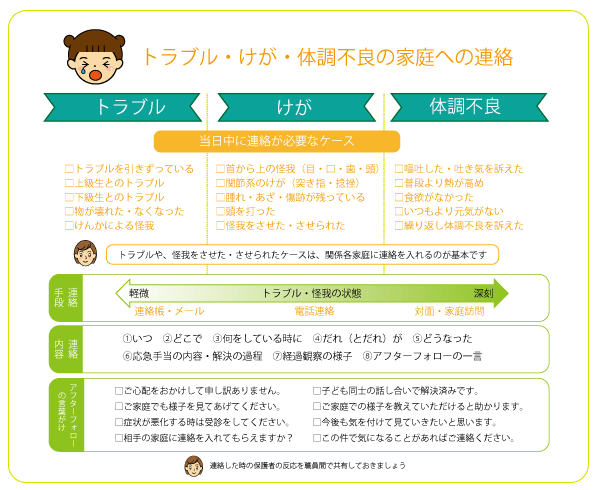
当日中に連絡が必要なケース

次のようなケースは、その日のうちに保護者に連絡するようにしましょう
子ども同士のトラブル
- 子どもがトラブルを引きずって帰ったような場合
- 上級生・下級生とのトラブル
- 持ち物が壊れたりなくなってしまった場合
- けんかによって怪我をしてしまった場合
子どもがトラブルを引きずっている場合

・・・

おや?
(帰る時間になっても元気がないな・・・)
子ども同士のトラブルで、話し合いをしたけれど、納得がいかなかったり、ショックが大きい場合など、子どもが帰る時間になっても気持ちが切り替わっていないような時は、家庭へ連絡を入れます。
子どもが元気がなく家に帰ってきたら、親は心配ですよね。
そんな時に、指導員からの連絡があれば、保護者が家庭で子どもを受け止めやすくなります。
上級生・下級生とのトラブル

生意気なんだよ!

うぇ~ん!
通常、同学年同士のトラブルと比較して、上級生とのトラブルは、子どものショックが大きくなります。
たとえ、上級生なりの事情があったとしても、子どもから話を聞いた親は、

上級生なのに、なんて乱暴なの!
というように、相手が上級生であることにまず不信感を抱いてしまうことがあります。
家庭に連絡をして、詳しく状況を説明することで、保護者も冷静になることができます。
持ち物が壊れたりなくなってしまった場合
黄帽や水筒・筆箱・ドリルなど、子どもの持ち物がなくなってしまったり、壊れてしまったような時は、家庭に連絡を入れます。
子どもが自分の持ち物を管理することができるようにすることは育成支援の目標です。

子どもと一緒に探したのですが見つかりませんでした
明日、他の子ども達にも聞いてみます
けんかによってけがをしてしまった場合
トラブルの結果、どちらかの子どもが、ひっかき傷などをつくってしまうことも、よくあります。
そのような時は、小さなけがであっても、家庭に連絡を入れ、場合によっては、けがをさせてしまった子の親から、けがをした子の親に直接連絡を入れてもらいます。

家庭間の関係がこじれてしまわないように、丁寧に対応をしましょう。
同学年同士のけんかでけがをする場合と、上級生とのトラブルでけがをする場合では、深刻さが違うことは言うまでもまりません。
こちらもCHECK
-
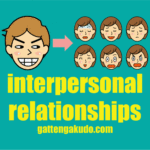
-
【学童保育】苦手な人とペアを組んだ時の対処法「職場の人間関係に悩んでいる指導員の皆さんへ」
続きを見る
けが
- 首から上(目・口・歯・頭)のけが
- 関節系のけが(捻挫・突き指)
- 腫れ・あざ・傷跡が残っているけが
- 頭を打った場合
- けがをさせてしまった・させられてしまった場合
首から上の怪我
目・口・歯・頭・顔の傷などのけがは、その日のうちに家庭に連絡します。

首から上のけがは、特に保護者が重くうけとめることが多いです
「こんな程度」と思わずに、必ず連絡しましょう

「こんな程度で連絡くれたの?」って保護者が思ってくれるなら、それでいいんです
私の経験ですが、目のまわりの怪我は、特に慎重に対応しましょう。
子どもは元気でも、「あと少しずれていたら・・・」と保護者が深刻に受け止めることが多いのです。
関節系の怪我

捻挫や突き指は、痛みや腫れがひどくなくても、家に帰って受診したら「骨折」だったという場合があります
けがの後の子どもの様子を観察して、元気そうにしていても、家庭に連絡を入れ、「腫れや痛みが収まらない時やひどくなるような場合は受診してください」と伝えましょう。
腫れ・あざ・傷跡が残っているけが
子どもがけがをして、患部に腫れやあざ、傷跡がある場合は、家庭に連絡します。

私は、子どもが帰る直前に、もう一度けがの具合を見るようにしています
例えば、15時頃に子どもがけがをして、応急手当をして、その後子どもが遊びを再開した場合などでも、17時の帰宅前に、最終確認をします。
これは、保護者に連絡をした時に、指導員の説明と実際に傷跡を見た保護者の実感に食い違いが出ることを避けるためです。
腫れやあざなどは、時間と共に引いていく場合もありますが、その逆がないとも言えません。
たとえ元気に過ごしていたとしても、「帰宅前の最終確認」を大切にしましょう。

帰宅前の確認で、傷がめだたなくなっている場合は、家庭に連絡を入れないこともありますよ
頭を打った場合
頭を打ってたんこぶができた場合など、すぐに冷やして腫れがひいたとしても、必ず家庭に連絡を入れます。
頭部打撲は、意識不明のような重大なケースを除き、ほとんどは大丈夫ですが、わずかな可能性ではありますが重大なケースに発展する恐れがあります。

頭を強打した時は、救急を受診します
帰宅後、気分が悪くなったり、頭痛がある場合などは、受診をするように保護者に伝えましょう。
けがをさせてしまった・させられたしまった場合

上述の、「けんかによるけが」の項目と同じ対応です

小さなけがであっても、自分でしたけがと、だれかにさせられたけがは、深刻さがかわります
深刻度がかわるというのは、指導員からの連絡がなかった場合の話です。
指導員が経緯やその後の対応をしっかりと説明することで、大きな問題になることはありません。

指導員からの説明って大切なんですね
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】ミッション・保護者懇談会を成功させよ!
続きを見る
体調不良
- 嘔吐した・吐き気を訴えた場合
- 普段よりも熱が高かった場合
- 食がなかった場合
- いつもより元気がなかった場合
- 繰り返し体調不良を訴えてきた場合

体調不良の場合、検温をして熱があったら保護者にお迎えをお願いします
なので、ここでの説明は、「体調不良を訴えてきたけど、熱はなく、その後普段通りに過ごせていた」というケースについてです。
詳しい説明は割愛しますが、風邪の初期症状であったり、熱があがる前に体調が悪くなる場合がありますので、念のために家庭に連絡を入れておくのが、丁寧な対応になるでしょう。

熱が出ないように、今日は早めに休ませるようにした方がいいと思いますよ
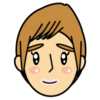
明日も仕事だから熱が出たら大変
連絡いただきありがとうございました
悩んでしまう・・・両方の家庭に連絡を入れる必要があるケース

けがやトラブルで、両方の家庭に連絡を入れる時が一番悩みます
された方の子どもの家庭に連絡を入れるのは、あまり悩むことはないのですが・・・
特に悩むのは、やった方の子どもの家庭に連絡を入れるか入れないかについてです。
しかし、これまでの話を思い出してください。

次のような場合は、やった方にも連絡を入れるようにしましょう
- 首から上の怪我
- 腫れやあざ・傷跡が残っている場合
- トラブルのショックを引きずっている場合
- 上級生とのトラブル
- 物を壊してしまった
以上のようなけがやトラブルで、やった・やられたの関係がある場合は、やった方の家庭にも連絡を入れるようにしましょう。
トラブルの報告などは、重大なケースにならないうちに保護者が知ることができてよかった、ということも大いにあります。

迷った時は連絡する!
でいいと思います
以下の内容にある「家庭への連絡で迷った時は・・・」も参考にしてください。
こちらもCHECK
-
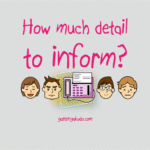
-
【学童保育】保身?事なかれ主義?子どものトラブルを保護者にどこまで伝えるかの問題
続きを見る
家庭への連絡手段について
ここからは、家庭への連絡を入れる方法や連絡の内容について説明していきます。

以下の図をご覧ください

まずは、けがやトラブルの際の保護者への連絡には、いくつかの方法があることを確認してください。
保護者への連絡方法
- メール
- 連絡帳
- 電話
- 対面

お迎えの保護者には直接伝えることができるけど、グループ帰りの子どもの家庭には、連絡帳や電話で伝えることが多いですね
伝える方法は、伝える内容の深刻度合によって変えるというのが対応の鉄則です。
最も丁寧は連絡は、「対面」で直接保護者と話すことです。
重大なけがやトラブルの対応は、必ず「対面」で保護者と話すようにします。
次に丁寧な対応は、「電話連絡」です。
直接声をを聴きあったり、お互いの顔を見せ合って連絡や報告を行うことで、指導員の真摯な思いや丁寧な感情を合わせて保護者に伝えることができます。
連絡帳やメールでは、思いや表情まで伝えることが難しいでしょう。

メールと連絡帳では、文書である連絡帳の方が丁寧だと感じる人がいることも知っておいてください

けがやトラブルの深刻さと伝える方法にギャップがあると、保護者は不満や不信感をおぼえてしまいますよね
家庭への連絡内容について
次は、伝える内容について説明します。
基本的には「5W1H」を押さえます。
- いつ
- どこで
- だれ(とだれ)が
- どうなった
- 職員の対応
- その後の様子
- アフターフォローの一言
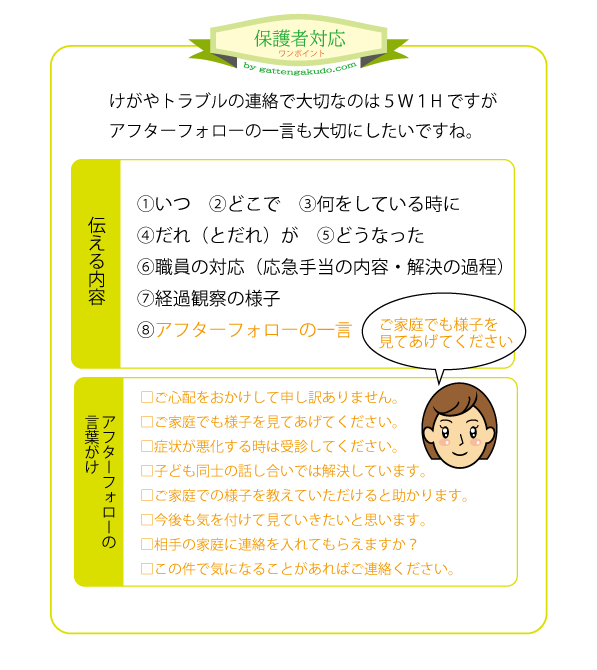
アフターフォローの言葉がけを大切にする
家庭への連絡内容は、必要な項目を押さえておくことが大切ですが、それだけでは、業務的な印象の連絡となってしまいます。

アフターフォローが大切なんですね
連絡の最後には、子どもを思いやる一言や、保護者の心配な気持ちに寄り添う一言をそえましょう。
ただ一言で、保護者の気持ちがスッと軽くなることもあります。
トラブルの対応などでは、子どもが指導員に言った言葉と、家庭で保護者に言う言葉が違うこともあります。

学童で話し合いをしたので解決済みですから!
と言うのと、

学童では、解決したのですが、本当の気持ちが言えてないかもしれません
家庭でのお話の様子も教えていただけると助かります
と言うのとでは、どちらが丁寧な対応か、言うまでもありませんね。
以下はそんな言葉がけの一例です。
アフターフォローの言葉がけ
- ご心配をおかけして申し訳ありません
- ご家庭でも様子を見てあげてください
- 症状が悪化する場合は受診してください
- 子ども同士の話し合いでは解決しているのですが
- ご家庭での話の様子も教えていただけると助かります
- 先方のご家庭にも連絡をしていただけますか?
- 今後も気を付けてみていただきたいと思います
- この件で気になることがあればいつでもご連絡ください
こちらもCHECK
-

-
新人指導員の皆さんへ あなたの「違和感」を大切にしてください【がってん学童メンバーより】
続きを見る
家庭への連絡で迷った時は・・・

それでも連絡を迷う時には、次の話も参考にしてください
入所間もない家庭には、丁寧に連絡する
私が家庭への連絡に迷った時に、判断の基準にすることの一つは、「保護者との信頼関係がどこまでできているか」ということです。
例えば、1年生や入所間もない時期のけがやトラブルについては、できるだけ丁寧に連絡をするようにします。
逆に、上級生の過程で信頼関係がしっかりとしている家庭には、連絡を省くこともあります。
保護者の状況や性格を考慮する
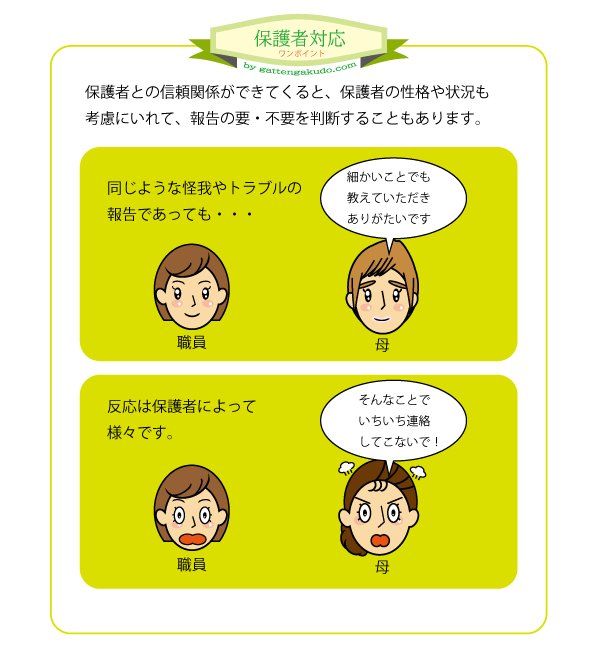
1年生の間、丁寧な対応を重ねていくと、だんだん家庭の状況や保護者の性格がわかってきます。
同じようなトラブルや怪我でも、「細かく教えていただいて助かります」という人もいれば、「そんなことでいちいち連絡をしてこなくて結構です」と言う人もいます。
後者のような保護者に対しては、軽微なけがやトラブルの連絡はしません。

同じトラブルでも連絡するしないがあるなんて、保護者の顔色を見ているみたいでなんかやだな~

そうかもしれないね
でも、保護者の状況や性格を無視してマニュアル通りの伝達をしていたらそれでいいのかな?
一番最初に、私は、保護者への連絡は一定の基準を作り、しかしそれに縛られずに柔軟に運用することが大切と言いました。
これは、保護者の考えやおかれている状況は100人いれば100通りあり、同じけがやトラブルでも、1人ひとりの受け止めが違うということが、保護者対応の大前提だと思っているからです。
マニュアル通りの対応では、長い目で見ると、保護者との信頼関係を築くことが難しい事例もたくさん出てきます。

基準は必要なのよ
基準に縛られないことが大事
家庭への連絡のワンポイント

ここから先は、余談のような話になりますが、私がこれまでの経験で学んだことをまとめています
大事なことは親に伝える

けがやトラブルの伝達を、お迎えにきた祖父母にした場合でも、その後必ず親に連絡を入れるようにします。
働きながら子育てをする、大変忙しい保護者ではありますが、親の役割を果たそうと一生懸命に頑張っています。
大事なことは、親に伝えるようにしましょう。
母親だけでなく、父親にも話をする
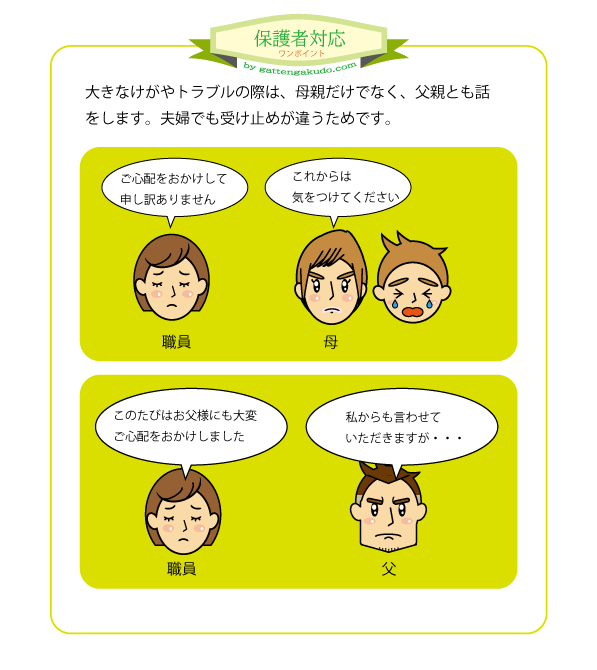
私は、重大なけがやトラブルの際には、母親だけでなく、父親とも話をするように教えられました。
その時の説明は、「世帯主は父親だから」というものでした。
実際、母親と父親では事態の受け止めが違ったり、意見が違ったりすることも多くありました。
母親が納得していても、父親が納得していない場合やその逆もありました。
信頼関係を早く回復するためには、母親・父親両方に丁寧に話をする方が良いでしょう。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】保護者の要求をどこまで受け入れたらいいの?
続きを見る
だれが保護者対応にあたるか?
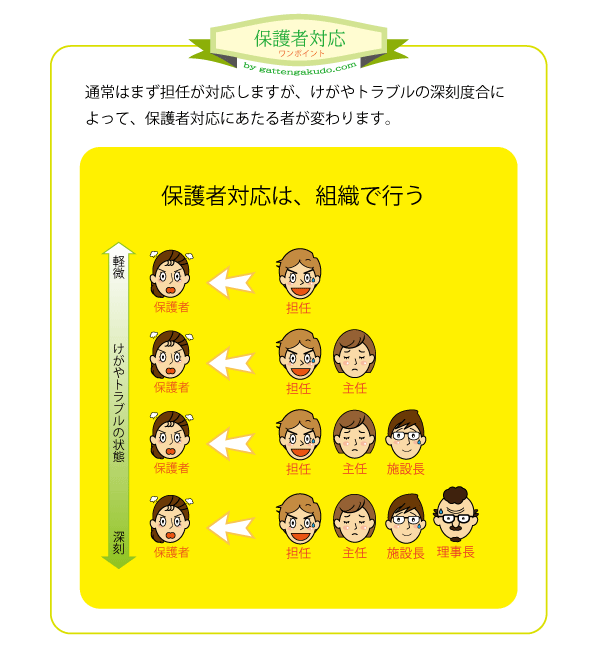
通常は、担任がまず、保護者対応にあたりますが、けがやトラブルの深刻度合によっては、主任や施設長が、担任とともに対応に当たることがあります。
重大なケースで、担任だけが対応すると、保護者からすると施設としての誠意が感じられないと受け取られてしまう場合があります。
とは言え、私はまずは担任が対応にあたる方がよいと考えています。
その理由は以下の3点です。
子どもや親と信頼関係があるから
ふだんから子どもと接している担任が、子どもや親のことを一番理解しており、信頼関係があるからです。
保護者が本音を言いやすいから
普段からかかわりのある担任には、保護者が意見や思いを出しやすくなります。
逆に施設長など、上位の役職が最初に対応にあたると、その場の雰囲気で言いたいことが言えずに保護者の不満が残ってしまう場合があります。
対応がこじれた時に上司がサポートできるから
担任が対応をしたが事態が深刻化するようなケースでは、次の対応で、主任や施設長が対応を行います。つまりサポートを行います。
一次対応に施設長があたり、そこで信頼関係が回復できなかったときに、指導員や主任ではサポートが難しく、事態が長期化してしまうことがあります。

そのようなケースはまれですが、重大なケースの対応は、必ず組織で行いましょう
こちらもCHECK
-

-
保護者対応の基本は 「みんな違ってみんないい」?
続きを見る










