新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
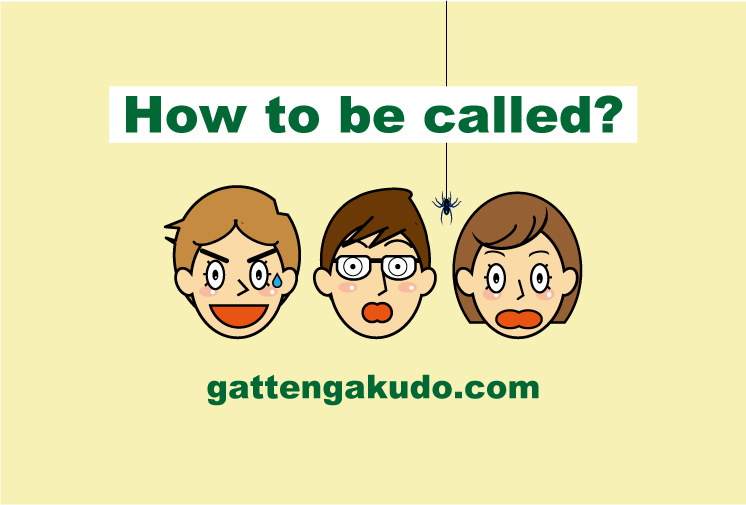
こちらもCHECK
-

-
【学童保育指導員のチームワーク①】「中堅指導員」の私を疲れさせる理由は・・・
続きを見る
ここはがってん学童保育所、がってん小学校の子どもたちが通っています。
登場人物

指導員4年目の、りえです。

4月から指導員になったばかりの、たけしっす

がってん学童保育所、所長です

ボランティアの仮田ですじゃ
指導員の皆さん、今日も一日お疲れさまでした。
がってん小学校は、今週は「個人面談週間」です。子どもたちの下校が早くて、てんやわんやの一日でした。
保育時間が長くて、指導員ににとっては大変だったけど、今日は子どもたち、たっぷり遊べて満足そうでした。

だって、4月なのに、子どもたち帰ってくるの遅いんだもん!
まだ新年度が始まって1か月なのに、1年生が15時をまわって学童に来る日が何日あったことか・・・。「放課後がまた一段と短くなった」と感じているのは私だけでしょうか?
さて、今回のテーマは、「学童保育指導員は、子どもたちからどう呼ばれるべきなのか?」についてです。
指導員を、どう呼ぶべきか・どう呼ばれるべきかの問題は、様々な意見があり、議論が多い「学童保育の問題」の一つです。
ちなみに、2014年に、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が定められ、「放課後児童支援員」が学童保育に必置の公的な資格として定められました。その後も、「指導員」で通っている地域や学童保育所が多くあるので、当サイトでは、「指導員」の呼称を採用しています。
この記事の目次
- 様々な指導員の呼び方が混在している?
- 指導員は「〇〇先生」と呼ばれるのが基本?
- 指導員の呼び方は「あだ名」でもよい?
- 「呼び捨て」はいいのか?
- 学童保育は「第三の世界」だから・・・?
- 論争の結果・・・
- 現状⇒子どもと指導員の合意で「呼び方」が決まっている
- さいごに・・・
様々な指導員の呼び方が混在している?
まずは、がってん学童保育所の現状を整理します。指導員の「子どもたちからの呼ばれ方」は、以下の通りです。
がってん学童指導員の呼ばれ方

たけし先生=「たけし」

りえ先生=「りえ先生」

仮田先生=じっちゃん

所長=所長
というように、てんでばらばら、一貫性がありませんよね・・・。
でも実は、がってん学童では、「指導員の名+先生」、という呼称が「基本原則」となっています。なので、指導員間では、「たけし先生」「りえ先生」などのように呼び合っています。(仮田先生はボランティア・スタッフなので、ちょっと特別です)
「〇〇先生」が原則ではあるけれど、実際には、新人指導員のたけし先生や、仮田先生は「たけし」や「じっちゃん」と呼ばれています。なぜ、そんなことになっているのかと言うと、それは、がってん学童のそれぞれの指導員の考えと、これまでの議論の結果なんです。
こちらもCHECK
-
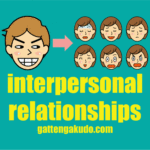
-
【学童保育】苦手な人とペアを組んだ時の対処法「職場の人間関係に悩んでいる指導員の皆さんへ」
続きを見る
指導員は「〇〇先生」と呼ばれるのが基本?

指導員は「〇〇先生」と呼ばれるべきです!
これは、私の意見です。私には、指導員は「先生」と呼ばれるべきだし、そう呼ばれる自分でありたい、という思いがあります。
全国の学童で、指導員の様々な呼ばれ方が混在しているとはいえ、やはり一般的なのは、「〇〇先生」でしょう。
指導員は、子どもたちの「指導者」です。
え?放課後児童支援員だから「支援者」だって?確かに「指導者」と「支援者」って、ニュアンスが違いますね。指導者は「上と下」、支援者は「隣で寄り添う」って感じですね。
どちらにせよ私は、「先生」という言葉をあえて使うことで、「子ども」と「指導員」お互いの立場をはっきりとさせておくことが大切だと思っています。
それがないと、「なぁなぁ」の関係、その行き着く先は秩序のない世界、ってことになるんじゃないでしょうか?
指導員が「先生」と呼ばれる存在であることは、保護者にとっては「安心」だし、私たち自身の自覚にもつながると私は思っています。

苗字+先生じゃなくて、名前+先生っていうのが、学童っぽくていいでしょ?
次の表は、2016年に「一般社団法人キッズコーチ協会」が実施した、「学童保育の利用に関する母親向けの実態調査」の中で、「あなたが学童保育の生活を通して、お子様に身につけて欲しい能力は何ですか?」と言いう質問に対する回答結果、上位3つです。
【学童保育への期待】
| 1位(59.8%) | 集団生活、集団行動に順応する力をつける |
| 2位(36.4%) | 相手の気持ちや立場を理解する力をつける |
| 3位(26.4%) | マナーや挨拶、礼儀を身につける |
保護者が我が子に、「学童で人間関係やマナーを学んで欲しい」という願いを持っていることがうかがえます。その中には、目上の人のことをちゃんとした呼び方で呼ぶことも含まれると、私は思っています。
指導員の呼び方は「あだ名」でもよい?

僕は「あだ名」がよいと思っています
これは、所長の意見です。
所長が異動してきた時に、すでに、がってん学童では「〇〇先生」という呼ばれ方が慣例だったそうです。
けど、以前の職場(保護者運営の学童保育所)では、所長はあだ名で呼ばれていたらしいです。
所長のこれまでの呼ばれ方
(保護者運営の学童時代)
1年目~ 「さとう」(呼び捨て)
3年目~ 「さとくん」(あだ名)
(がってん学童時代)
1年目~ 「たける先生」
3年目~ 「さとさと」(あだ名)
5年目~ 「たける先生」
10年目~ 「所長」or「たける先生」
・・・という感じです。

これまで、僕は色んな呼び方で呼ばれてきました。けど、その時々で、子どもや保護者との信頼関係は築けていたと思っています。むしろ、あだ名の時の方が、距離感が近かったですよ
「あだ名でないといけないとまでは思わない。逆に〇〇先生でないといけないとも思っていない。」

呼び方がどうよりも、子どもと指導員の「関係性」が大切なんです
「先生」と呼ばれるから、子どもから「信頼」されるわけではない。子どもから「あだ名」で呼ばれているから「軽んじられている」とは限らない。呼び方よりも、子どもとの信頼関係を大切にしましょう、という理屈です。
所長は、こんなことも言っています。

僕の経験では、保護者が指導員の呼び方でクレームを言ってくる時は、子どもと指導員の関係に問題がある場合です。呼び方を「先生」に改めたところで問題は解決しません。

僕が尊敬している「偉大な指導員」の皆さんの中には、子どもたちや保護者から、「あだ名」で呼ばれている人がたくさんいるんだよ
こちらもCHECK
-

-
新人指導員の皆さんへ あなたの「違和感」を大切にしてください【がってん学童メンバーより】
続きを見る
「呼び捨て」はいいのか?
では、子どもが指導員のことを「呼び捨て」にするのはどうでしょうか。

絶対だめです!

苗字の呼び捨ては✖だけど、名前の呼び捨ては、あだ名と一緒だから〇!
ここでも意見が分かれています。所長の言い分によると、山田たけし(たけし先生の名前)の場合、「山田」はダメで「たけし」はOKになります。と言いながら、昔は所長も苗字で呼び捨てにされてたんじゃないですか・・・。
こうなると、所長がどこでどう線引きをしているのか、もはや私にはわかりません。
学童保育は「第三の世界」だから・・・?
ところで、指導員の呼び方、そして子どもとの「関係性」の話になる時に、所長がよく引き合いに出してくる一冊の本があります。

『障害児が育つ放課後 学童保育は発達保障と和みの場所』白石正久著(かもがわ出版)

この本の中に、こんな文章があるんです
「同じ目の高さ」
大切なことは、学童保育での人間関係、とくに指導員との関係に、教育的意図を感じさせないということです。(中略)だからこそ、子どもは学校以外の場で、教師の教育的意図から解放されて、自分の願いで「こうありたい自分」を実現しようとするのでしょう。(中略)つまり、「同じ目の高さ」で向き合うことに、「第三の世界」を特徴づける意味があるのです。
それは、学童保育や作業所の指導員が、「こうなってほしい」「こう育ってほしい」という青年や子どもへの願いや、指導の「めあて」をもつ必要がないということではありません。むしろ、そういった教育的意図を潜ませて、彼らと同じ「目の高さ」に下りていくという、ある意味、高度な指導技術を持つということです。
『障害児が育つ放課後 学童保育は発達保障と和みの場所』白石正久著(かもがわ出版)より抜粋

この本は私も持っています。良いことがたくさん書いてありますよね
「学童保育」は放課後の自由な時間で、「家庭」でも「学校」でもない、子どもたちにとって「第三の世界」なんだ。その中で、指導員は、「親」や「教師」とは違う距離感で、子どもたちの生活を支援していくんだ。
所長は、「先生」と子どもに呼ばせることよりも、「あだ名」で子どもとの親密な距離感の中でこそ、学童保育ならではのかかわりができる、ということが言いたいんです。

それになんてったって、学童は「遊び」を中心とした生活なんだからさ!

けど、それって「〇〇先生」と呼ばれていたらできないことなんでしょうか?

できないことはないね

じゃ、いいですよね、〇〇先生で

いいけど、あだ名でもいいよね
こちらもCHECK
-
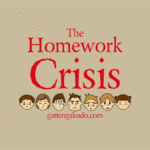
-
「がってん学童の宿題論争」前編【学童保育の宿題の悩みについて】
続きを見る
論争の結果・・・

はっきり言って、所長の考えは時代遅れです
所長が歩んできた学童人生は、古き良き時代だったんです。けど、今は、保護者の考えも学童保育に求められるものも変わっているんです。目を覚ましてください!

指導員は呼ばれ方じゃない、中身なんだよ。りえ先生は髪型でその人の中身を判断するの?

中身まではわかりませんが、髪型でその人の印象は決まります。
いいですか、所長。
短髪の爽やかなヘアスタイルが「〇〇先生」って呼ばれ方。「この人ちゃんとした人なんだ」って安心感があるでしょ。
茶髪のロン毛は、「あだ名」。「ちょっと心配かな?」って、見ている人を不安にさせます。
過激なモヒカンは「呼び捨て」。「だいぶ心配」になりますよね。
もちろん見た目で中身はわからないです。短髪で爽やかだから中身がしっかりしているとは限らない。モヒカンでも真面目で心の優しい人はいるでしょう。
けど、世間一般からしたら、やっぱり見た目で判断されることは多いですよね。
所長は職員面接にモヒカンの若者が来たら採用しますか?

中身が良かったら採用するね!

絶対採用しないくせに!

学校の先生は爽やかな短髪なんだよ。指導員まで爽やかな短髪になったら息苦しいよ

みんなモヒカンの方が息苦しいわ!私は爽やかな方がいい!
・・・というように、結局「指導員の呼ばれ方」の議論に結論がでることはなく、この問題は「継続審議」ということになりました。
子どもとの信頼関係が大切だってことは、私ももちろん同意していることなので、そのことを優先にして、事あるごとに指導員の呼び方については議論していこう、ということになっています。
現状⇒子どもと指導員の合意で「呼び方」が決まっている
結果として、指導員側としては、「できれば先生って呼んでよね」と思っているんだけれど、実際どう呼ぶかは「子どもに任せましょう」というスタンスとなっている次第です。だから、がってん学童では、様々な呼び方が混在しているんですね。
これは、「職員の思いも大切だけど、子どもがどう呼びたいかを尊重しよう」ということでもあるんです。

学童の主役は、なんてったって子どもだからね!
もちろん、指導員がそんな呼び方はやめてほしいと思う場合は、子どもたちに、「自分は〇〇と呼んで欲しいんだけど」と、はっきりと言います。子どもと指導員の合意によって、呼び方が決まっているんです。
つまり、

たけし、遊ぼうよ~!
とか、

じっちゃん、宿題教えてよ
って、子どもが呼んだとして、その呼び方で指導員が納得している場合、私たちが、

「たけし」や「じっちゃん」じゃなくて、たけし先生、仮田先生って呼ぼうね
ということは、あんまり言わないことになっているんです。
もちろん、あきらかに馬鹿にしたような呼び方を子どもがした時には、指導員が「それって呼ばれた人がどんな気持ちになると思う?」と注意することはあります。
また、子どもから指導員の呼び方が荒れるような時は、呼び方そのものよりも、子どもたちと指導員の関係に着目して、何が課題になっているのか、どうすればよいのかを指導員みんなで考えます。
こちらもCHECK
-
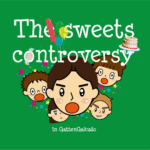
-
がってん学童の「おやつ論争」前編【トイレに学童保育のおやつが捨てられていた?】
続きを見る
さいごに・・・
いかがだったでしょうか。
今回は(も)結論がないような話になってしまいましたが、がってん学童の「指導員の呼ばれ方の問題」から、皆さんがそれぞれに考えを深めていただけたら、この記事も無駄ではないと思います。
呼び方が大事か、子どもとの信頼関係が大事かって、「卵が先か鶏が先か」みたいな話ですよね。

ところで、新人指導員のたけし先生はどう思っているの?
最近は1年生からも「たけし」って呼ばれたり、こないだは1年生の保護者からも呼び捨てにされていたようだけど。

ぼくは、今は「たけし」で馴染んでるんで、そのままでいいっす。「先生」って呼ばれるのもなんだか恥ずいっすわ~

「恥ずいっすわ~」ってのはちょっといただけないね。もっと指導員としての確固たる信念を持って「たけし」って呼ばれないと

「たけし」は「モヒカン」なのよ・・・。よっぽどの信頼関係を築かないと、棘の道を歩むことになるわよ
なんだかんだ言って、この時は、私たち呑気に構えていたんだと思います。
1年生の保護者から、指導員の呼び方に関するクレームが入るなんて思ってもみなかったんですから・・・。










