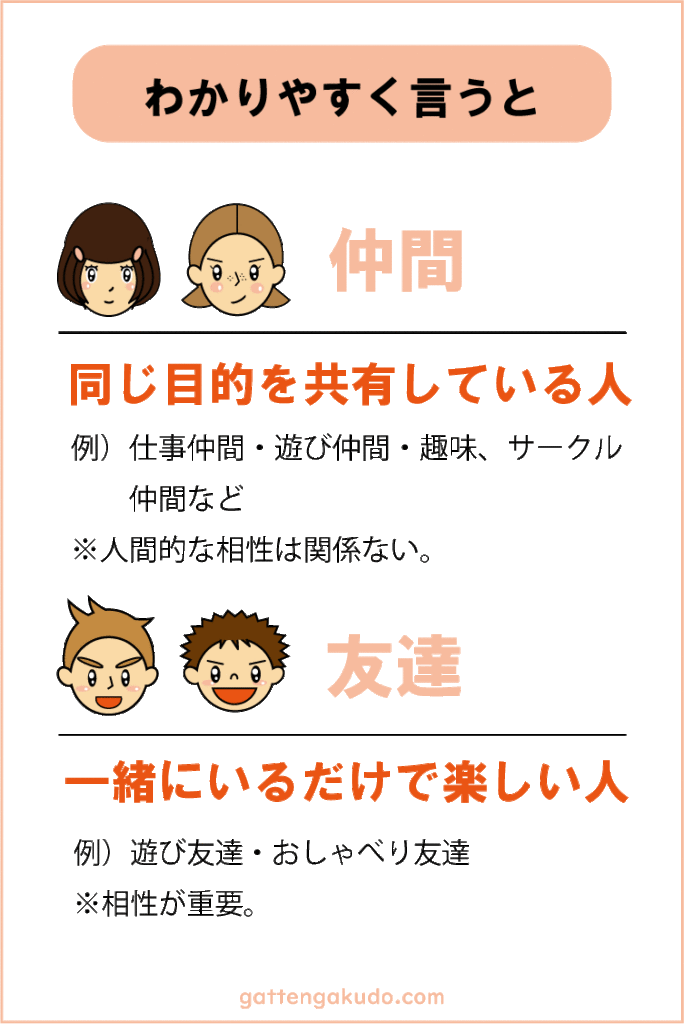今回の記事では、学童保育現場でもよく使う「仲間」や「友達」という言葉に関するトピックスを、TOP5形式でお伝えしていきたいと思います。
新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし!
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
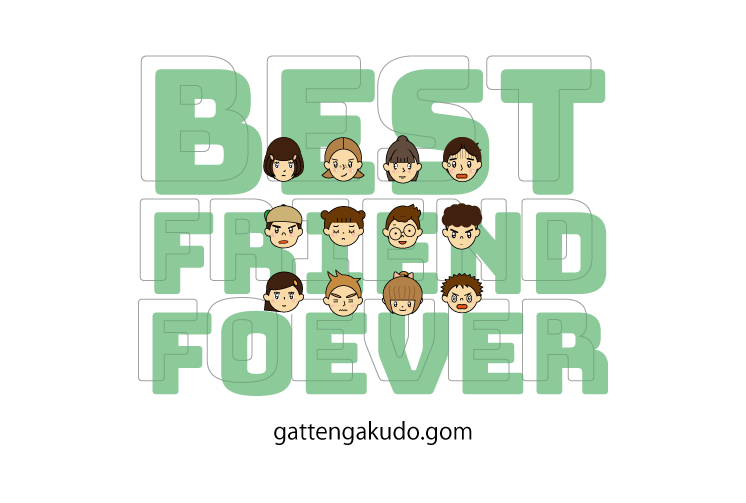
子どもから「俺たちは仲間じゃない!」と言われて・・・

皆さん、お疲れっす!
がってん学童指導員のたけしです。
先日、子ども同士のケンカの対応をしていた時のことなんすけど、こんなことがあったんです。
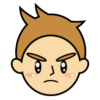
お前なんか嫌いだ!

俺だってお前なんか大大大嫌いだ!!
2年生のてっちゃんと1年生のかっけーが、結構な言い争いをしていました。それで、僕は二人に、こんな風に声をかけたんです。

まぁまぁ落ち着いて、仲間でしょうが・・・
すると、二人が口々に、

仲間じゃない!!
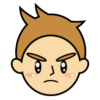
仲間なんかじゃない!
って僕に言ったんです。
結局、ケンカの途中で、おやつの時間になり、おやつ後には、何事もなかったかのように遊んでいた二人でした・・・。

ほら、やっぱり、仲良しの仲間じゃないか。
って僕は思ったんですが、これがきっかけで、「仲間」って言葉のことが気になってしまったんです。
僕は、てっちゃんとかっけーみたいに、お互いに言いたいことが言えて、ケンカもするけどまた仲直りして遊べる、そんな関係のことを「仲間」だと思っています。
家にあった実用新国語辞典(三省堂)には、「仲間:一緒に事をする人。友人。」って、さらっと書いてありました。
そこで、またまた新たな疑問ができてしまったんです。

はて?「仲間」と「友達」ってどう違うんだろう??
というわけで、今日の記事は、「仲間」という言葉に関する大切なことを、TOP5って感じでお伝えしてきたいと思います。
特に最後のやつは、目からウロコでした!
目次
【第5位】「仲間」と「友達」は違う
僕は、先輩に聞いてみることにしました。

先輩、仲間と友達ってどう違うんですか?

あら、たけし先生、そんな質問するなんて、何があったの?
僕は、てっちゃんとかっけーのケンカの話をしました。「仲間なんかじゃない!」と二人から言われたことも。

なるほど~、そんなことがあったわけね。
以下は、先輩の説明です。

言葉の意味としては、こうね。
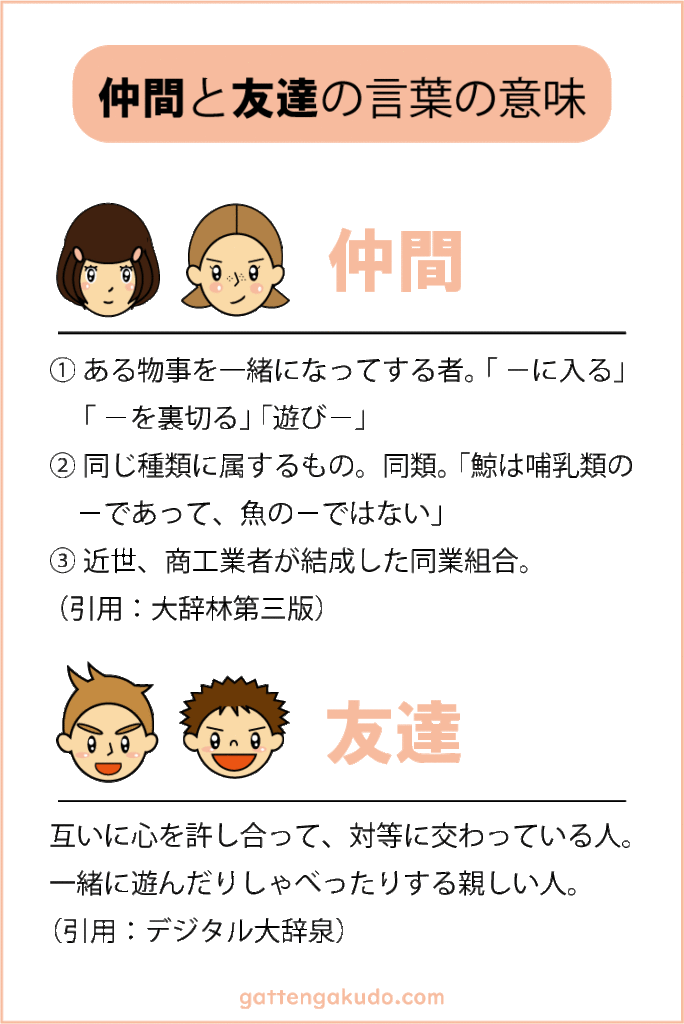
これは、辞書に載っていることだそうです。
先輩は、次のようにも説明してくれました。

もう少しわかりやすく言うとね・・・

なるほど~!
子ども達が、同じ遊びを楽しんでいる時なんかは、「楽しむ」という目的を共有しているわけであるから、「仲間」と言えるかもしれないと僕は思いました。

私とたけし先生は、同じ職場の「仲間」と言えるけど、「友達」ではないわね。

そんな風にズバッと言われるとちょっと悲し~っす!
【第4位】本人たちがそのように思っていることが大事
先輩は、てっちゃんとかっけーが「仲間なんかじゃない!」と言ったことについては、次のように言っていました。

他の人から押し付けられたりすると、反発しちゃうのわかるわ。
先輩は、子どもの前で「仲間」という言葉を使う時には、「大人が、仲間という言葉を使って、子どもをコントロールしたり管理したりしようとしていないか? 自分自身に厳しく問うことが大切じゃないかな~」だって。
例えば、
- 仲間なんだからケンカしないでね
- 仲間だから協力してね
- 仲間だから友達を大切にしよう
とか、
子ども同士であっても、
- 仲間だから先生に言うなよ
- 仲間だから許してくれよ
- 仲間だから言うこと聞いて
なんていうのは、「仲間」という言葉を都合よく使っているだけの場合もあるかもしれない。

そういうのって、伝わるものなのよね~。

てっちゃんとかっけーが怒ったのは、「仲間」という言葉を使ってその場を収めようとした僕の「ずるさ」が透けて見えたからかもしれない・・・。
「仲間」や「友達」って、まわりからどうこう言われるものではなく、本人たちがそう思っていることが大切なんだ。
言葉の意味よりも、本人たちの気持ちを大切にすることが大切かもしれない・・・。
僕は、先輩と話をしていて、そんな風に思いました。

一緒に悪さしたり、「つれしょん」したりする時に仲間意識を感じることってあるじゃない?

つ、つれしょんって・・・
そういえば、うちの所長は、「年度後半は仲間意識を深めるかかわりを大切にしたい」とか、しきりに、仲間・仲間意識などと言っています。
先輩の話によると、そんなワードを連発して、所長は子どもたちをコントロールしようとしているんじゃなかろうか??

よし。所長にもきいてみよう。
【第3位】「仲間」には、発達段階がある?

あ、所長、ちょっといいっすか?

おや、たけし先生。どうしたい?
僕は、所長に、てっちゃんたちのケンカのことや、「仲間なんかじゃない!」と言われたこと、先輩に教えてもらったことなどを話しました。

なるほど。「仲間」という言葉を追求しているわけだ。

は、はい。

たしかに、「仲間」って不思議な言葉だよね。その持つ意味は、子どもの成長に伴って、少しずつ変わってくるからね。
所長は、「遊びの中での仲間同士の関係は、子どもの発達にともなって変化してくんだよ」って話を聞かせてくれました。
以下、所長の話です。
幼児期の遊びの6つの発達段階
アメリカの社会学者パーテンによると、幼児期の遊びには6つの発達段階があります。
- なにもしない行動
- 一人遊び
- 傍観的行動
- 並行遊び
- 連合遊び
- 協働遊び
パーテンは、自由遊びの中で見られる子どもの遊び方を観察し、年齢によって子どもの遊び方が異なることを説明しました。

2・3歳頃には、「一人遊び」や「並行遊び」が多くみられる。
一人遊び
他の子どもが近くにいても、それぞれの子どもが違う遊びをしている状態。
並行遊び
他の子どものそばで、同じような方法で遊んでいるが、物の貸し借りや会話などのやりとりは行われないという遊び方。

4・5歳ごろになると、「連合遊び」や「協働遊び」と呼ばれる遊び方が多くなってくる。
連合遊び
子どもが、同じ一つの遊びをしていて、おもちゃの貸し借りや、その遊びに関する会話を行う状態。
協働遊び
子どもが共通の目標を持って、リーダーのもと役割分担をして遊ぶような遊び方。

共通の目標を持って遊ぶというのは、仲間意識の芽生えと言えるかもしれないね。

なるほど~
子ども達は、遊びの中でケンカやいざこざを経験し、それらを通して、自分の気持ちを表現したり、相手の気持ちを理解していく。そうやって、社会性を育んでいくんだって!
こちらもCHECK
-
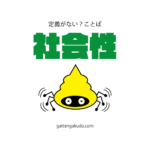
-
明確な定義がない謎の用語「社会性」【社会性が発達するってどういうこと??】運営指針解説番外編③
続きを見る
小学生になったら

小学生になると、子どもたちは新しい活動や新しい人たちと出会い、さらに子ども同士の関係を変化させてくよ。
小学生になった子ども達は、幼児期から児童期、そして思春期への発達過程を、行きつ戻りつ歩んでいきます。
心と体がダイナミックに変化するのが小学生時代の6年間なんですね。
そういった成長にともなって、子ども同士の関係や「仲間の意味」は変化していきます。
ギャングエイジ

3年生頃になると、「ギャング・エイジ」と呼ばれる子ども同士の関係が見られるようになってくる。

ギャング?
「ギャング・エイジ」と聞くと、どうしても「不良」「荒くれ者」といった印象ををぬぐい切れないのですが、れっきとした子どもの発達過程なんです。
ギャング・エイジとは
9歳から10歳ごろ(3~4年生くらい)に見られる発達的特徴。日本語では「徒党時代」と訳される。
ギャングエイジの子ども達は、以下のような行動を示す。
- 6~7人くらいの同性の仲間集団(ギャング・グループ)を作って遊ぶ
- 仲間集団の中には、リーダーやフォロワーなどの役割分担がある
- 大人が決めたルールより、自分たちで決めたルール(掟)に従って行動する
- 仲間意識が非常に強くなる一方で、仲間以外を排除しようとすることがある(閉鎖的・排他的)
ギャング・エイジ期には、子ども達が仲間とつるんで遊ぶようになります。
秘密基地を作ったり、その中で「掟」や「合言葉」を作って遊んだり、中には、高いところから飛び降りるような危険な遊びを一緒にすることで、お互いの仲間意識を試したりすることもあります。
低学年時代のふわふわとした子ども同士のつながりと比べて、仲間同士の結束が強まり、色々な遊びを遊びこむようになって、大人の言うことよりも、仲間のルールを重視するようになっていきます。
とかく否定的なイメージがつきまとうギャング・エイジですが、この時期の仲間との遊びを通して、「親友」や「友情」「絆」など、人と人とのつながりの大切な概念を子ども達は理解するようになっていくのです。
参考文献:『テキスト「学童保育士・基礎」カリキュラム』一般社団法人日本学童保育士協会・特定非営利活動法人 学童保育協会 編

ギャング・エイジについては、こちらの記事にまとめてあります!
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】「ギャングエイジ」と呼ばれる子どもたち
続きを見る
チャム・グループ

5・6年生頃になると、仲間関係はまた一段変化するよ。
9・10歳頃までは、「ギャング・グループ」として、一緒に好きな遊びなどの活動ができる仲間が中心であったのに対して、11・12歳頃になると、より内面的な思いを表現し、共感し合える仲間関係が求められるようになっていきます。
お互いの共通点や類似性を言葉で確かめ合い、同質性を意識したグループのことを「チャム・グループ」といいます。
「チャム・グループ」では、仲間内だけで通用する言葉やあだ名を使ったり、同じような服装をすることによって、お互いに結ばれていることを確認し合うような行動が見られるようになります。

「チャム」って「親友」っていう意味なんだって!
参考文献:『テキスト「学童保育士・基礎」カリキュラム』一般社団法人日本学童保育士協会・特定非営利活動法人 学童保育協会 編
【第2位】学童保育の子ども同士の関係を専門に扱う「集団づくり」という研究分野がある?

学童の仲間関係に関心や課題意識があるなら、「集団づくり」の講座に出てみるといい。

集団づくり?
所長が言うには、全国学童保育連絡協議会が主催する、「全国学童保育研究集会」や「指導員学校」などの研究会、一般財団法人日本学童保育士協会の講座などでは、学童保育の子ども同士の関係に焦点を当てた実践の交流や検討が行われているとのことです。
学童での班活動や、リーダー制などについても、全国各地の実践を持ち寄り、さかんな交流が行われるそうです。

ある学童の特定の子ども同士の関係を、数年間にわたって追跡したレポートなどがあったりして、とても勉強になるんだよ。
これらの講座では、管理やコントロールなどではなく、ケンカやぶつかりを経験しながらも、子ども達が安心して過ごせるような仲間関係を築いてくための指導員のかかわりを学んでいきます。
所長が大好きな本、「学童保育実践入門~かかわりとふり返りを深める/中山芳一著」には、学童保育の集団づくりについて、次のように書かれているそうです。
集団づくりとは
「集団づくり」とは、決して個を埋没させて集団を統制するものではなく、一人ひとりが尊重され、安心感のある平和的な人間関係を築くことを意味しています。(中略)集団づくりの基礎は、個人の尊重であり、子ども同士の人間関係でなければなりません。
引用:学童保育実践入門/中山芳一著

学童保育の「集団づくり」の前提は、一人ひとりの尊重であり、一人ひとりの子どもの理解なんだね。

言われてみたら、本当にそうっすよね!
仲間っていうけど、それは一人ひとりの集まりなんだ。
そんな一人ひとりを大切に、仲間関係を大切にしていく「集団づくり」の実践ってどんなだろうか。
僕は、今度の研究会では、「集団づくり」の分科会に出てみたいと思いました。

まぁ、難しく考えずとも、次のような遊びや活動を、子どもがたくさん経験できるようにしていけたらいいよね。
- 子ども同士のかかわりが拡がる活動
- みんながいるから楽しい活動
- みんながいるからできた活動
日常生活のふとしたかかわりから、年度末行事などの大きな取り組みにいたるまで、様々なレベルで、これらのことを体験していくことによって、

みんなでやって楽しかった~!!
とか、

みんながいたからできた!!
などの思いを、子どもたちが、たくさん感じることができたら、結果として、子ども同士の関係は豊かになってゆくんだと所長は言いました。
【第1位】仲間関係は受け継がれていく

最後に、これは僕が常々感じていることなんだけど、
仲間関係は受け継がれていくものなんだ。

え?
所長の話によると、学童保育の中での子ども同士の関係というものは、良くも悪くも、当事者たちだけのものではなく、まわりの子どもたちに影響を与えていくものなんだって。
例えば、ある子ども達の、活き活きとした心地よい仲間関係があるとすると、それは、同学年の別の仲間関係や他学年の仲間関係に影響を与え、拡がっていきます。

上級生と下級生の憧れ・憧れられる関係ってよく言うけど、それは「個人」対「個人」だけでなく、「仲間」対「仲間」でも言えることなんだよ。
素敵な仲間関係が、上級生から下級生に受け継がれ、やがて学童の文化となっていく、そんな学童保育を目指していきたいと所長は言いました。
僕は、所長がしきりに「仲間」とか「仲間意識」だとか言っていた理由が、なんとなくわかった気がしました。
さいごに・・・

いかがだったでしょうか
今回は、学童保育の「仲間」について、先輩や所長に教えてもらったことをまとめてみました。
- 「仲間」と「友達」は違う
- 本人たちがそう思っていることが大事
- 仲間関係には発達段階がある
- 学童の子ども同士の関係を専門に扱う「集団づくり」という研究分野がある
- 仲間関係は受け継がれていく
という内容でした。
TOP5って感じでお伝えしましたが、順番は関係ないと思います!

さいごに聞くけど、たけし先生が考える、理想的な仲間ってどんなだい?

え?
僕は、先輩や所長の話を聞いて、仲間って言葉は奥が深いけど、実は簡単なんだと思いました。
子どもたちがお互いを仲間だと思えること。
それに尽きるんじゃないだろうか。
けど、強いて言うなら・・・
お互いに言いたいことが言い合えて、一緒に遊んだり、ふざけたり、やんちゃできて、ケンカしたりするからちょっとウザい時もあるけど、いなかったら寂しい人。

そんな関係が学童の仲間じゃないかな~!
これは僕の意見です。
皆さんはどう思いますか?
【あとがき】
この記事は、Twitterのフォロワー様からのご質問の返答として作成しました。
フォロワー様は、「学年別大切にしたいこと」をまとめた以下の図に対して、「仲間の意味を理解していくのは10歳頃からではないかな?」といったコメントをくださりました。
とても鋭いご意見だったと思います。
「仲間」という言葉について考えを深めるきっかけをくださったフォロワー様に感謝!です。
がってん学童の記事内容にご意見やご感想がありましたら、Twitterアカウントやメールにてお受けしています。
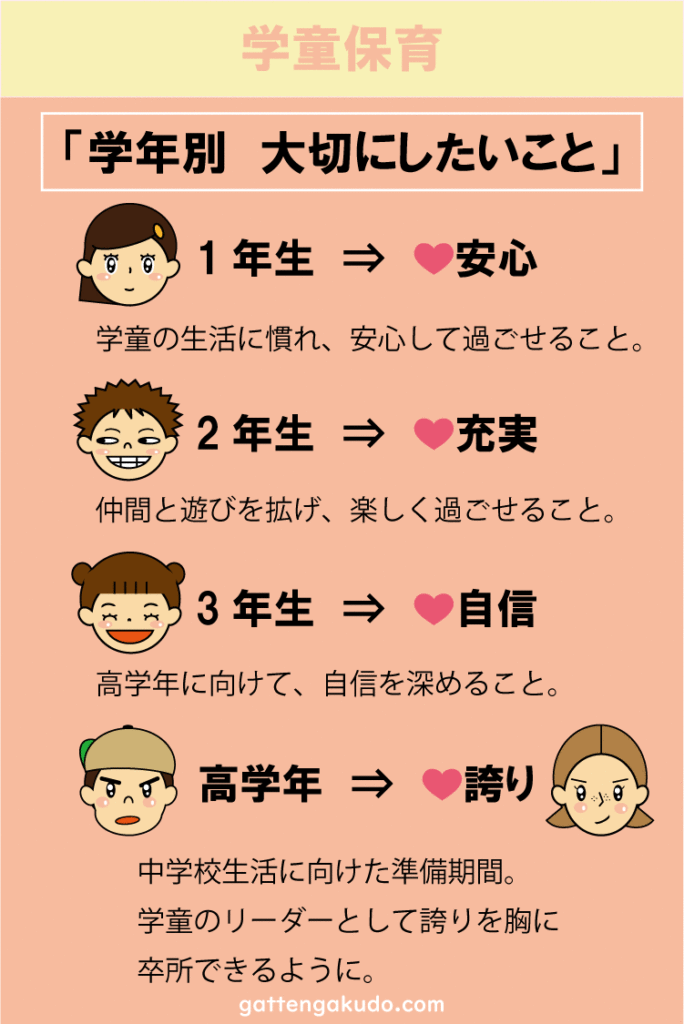
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】各学年で大切にしたい育成支援の目標「職場で話し合ってみよう」
続きを見る