新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
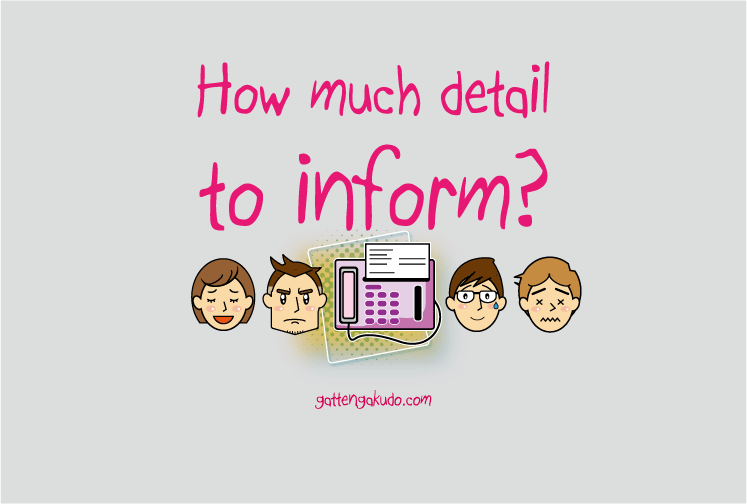
目次

今日のトラブル、今から保護者に電話するんですけど、どんな風に伝えるべきっすか?

どこまで伝えたらいいものか・・・

悩んでしまうよね
指導員の皆さん、今日も一日お疲れさまでした。
子ども同士のトラブルを保護者に伝える時に、電話の前で悩んでしまうこと、ありませんか?
事実をありのままに伝えるべきか、オブラートに包むようにソフトに伝えるべきか、はたまた今日のところは伝えないべきか・・・、いくつもの選択肢が頭をよぎり、なかなかダイヤルできないということが、私にもありました。
今回はそんな悩みについて書きました。
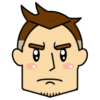
なんだか、聞き捨てならん話ですな
指導員は、事実をありのままに保護者に伝えていないんですか?
保護者会長として黙っておられん

おっと、これは会長さん
せっかくなので保護者としての意見も聞かせてもらえませんか
この記事の内容
- どのように伝えるべきか?どこまで伝えるべきか?
- トラブルの際に名前を伝えることのメリットとデメリット
- どう伝えるかより大切なことは
- トラブルの報告不足が招いた修羅場の話
- 何かあったら細かいことでも連絡して欲しいと言われたが
- さいごに・・・
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】9月の育成支援で大切にしたいこと
続きを見る
どのように伝えるべきか?どこまで伝えるべきか?
「どのように伝えるべきか?」という悩みの例で、「5年生の男の子が2年生をパンチした」、というトラブルが発生したとします。

ばっきゃろ~!(ガツン!)

びえ~ん!
適切な表現で伝える
保護者に伝える際に、

実は今日、5年生の男の子の手がてっちゃんに当たってしまって・・・
と言うのと、

実は今日、てっちゃんが5年生の男の子に叩かれるということがあって・・・
と言うのと、

実は今日、てっちゃんが5年生の男の子に殴られるということがあって・・・
と言うのでは、伝わり方が違います。
「手が当たる」という表現は、「偶然」の出来事という印象が強いので、事実に反する伝え方になってしまっていますね。
「殴る」という言葉には、より暴力的な響きがあります。
言葉の選び方によってニュアンスが変わってくるんですね。
私は、「叩く」という表現を使う場合が多いです。
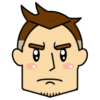
「殴る」という表現を使わないのは、事を穏便に済ませたいという指導員の心理からじゃないですか?

そうとられるかもしれませんね。
しかし私は、子ども同士の出来事で「殴る」という表現はあまり使いたくないんです。
両家庭に連絡する時は、伝え方を考える
もう一つ、トラブル報告の際に気をつけないといけないことは、関係する両家庭に連絡を入れた時に、事の重大さについて、それぞれの親の受け止めがある程度同じになっている方が良いということがあります。
指導員の報告を受けた両家庭の親が、その後、お互いに連絡を取り合うことがあるからです。
そんな時、お互いの受け止めが大きく違っていると、話か食い違ってしまいます。
楽観的な親もいれば、深刻に受け止める親もいるので、相手によって伝え方を調整する必要がありますね。

どのように伝えるか、どれだけ伝えるか、いつも悩んでしまいます。
こちらもCHECK
-
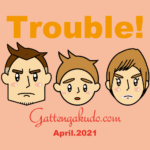
-
【学童保育保護者】1年生の息子と上級生のトラブルについて(前編)
続きを見る
トラブルの際に名前を伝えるかどうか
「どこまで伝えるべきか」に関しては、相手の子どもの名前を伝えるかどうか、と言う悩みもあります。

実は今日、てっちゃんが5年生の男の子に叩かれるということがあって・・・
と言うのと、

実は今日、てっちゃんが5年生のたくま君に叩かれるということがあって・・・
と伝えるのとでも、随分と違います。
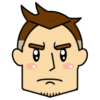
なんですかそれ?
そんなもの、親からしたら相手の児童の名前がわかった方がいいにきまってるじゃないか

今は僕も会長と同じ意見なんだけどね

なんで名前を伝えないんですか?

ずばり聞かれると私も答えられないわ
なんでなんだろう

2次トラブルの防止のためなんだよ
2次トラブルとは、トラブルの報告を受けた親が感情的になり、相手の家庭に怒鳴り込むなど、親同士のトラブルに発展することです。
保育園や幼稚園では、2次トラブル防止のために、子どもの名前を伏せることも多いようですね。
しかし、学童保育は、対象が小学生なので、ある程度子どもが親に事実を伝えると想定して報告をする必要があります。
親を信頼して、相手の名前を含めて正確に伝える方が私はよいと思っています。

子どもから親への報告では、客観的な事実が伝わらないことがありますので、私は相手の名前も含めて、できるだけ正確に状況を伝えるようにしています
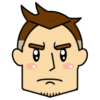
そりゃ当然でしょう
奥歯に物が挟まったような報告は、かえって不信感を持ちますよ
どう伝えるか以前に大切なことは
実は、保護者へどのように伝えるかという「連絡の仕方」以前に、大切なことがあります。
事実確認をしっかりと行うこと
一つ目は、まずは指導員が事実を把握しているということです。

事実関係の把握が曖昧だと、報告も曖昧になってしまいますものね。

保護者への伝え方は次の問題、まずは指導員が正確に事実を把握することが大切だよ。
事実を把握したうえで、原因や結果を分析して、その後の対応に見通しをもっていること。
そのうえで、それを保護者にどのように、どれだけ伝えるかを指導員間で協議するんです。
学童でしかるべき対応がされていること
二つ目は、学童で対応が行われており、当該児童同士が納得のいく解決が行われているか否かです。
報告の際には、トラブルに指導員が丁寧に向き合い対応したことも含めて伝えることで、かえって保護者が安心するということもあります。

子どもを預かる立場として、トラブルを阻止できなかったお詫びの思いを伝えることも大切です
手を出した子を悪者にしたり、全てを子どもの責任にしてしまうような伝え方は、無責任な印象を与えてしまうことがありますよ。気をつけましょう。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】理解と共感を拡げるための取り組み「発信」について
続きを見る
トラブルの報告不足が招いた「修羅場」の話

ずいぶん昔のことだけどね
僕には苦い経験があるんだ
色々と課題の多い男子がいてね、よく手を出したり、まわりの子を攻撃して泣かせたりしていたんだ。
そんな状況が長く続いた。
最初は、やられた方、やった方どちらの家庭にも連絡をしていたんだけど、やった方の親が子どもに手をあげるので、指導員で相談して、その後はやった方の家庭には連絡をしないようにしたんだ。

連絡をしないことで、学童で手を出した子どもを、家庭での体罰から守ろうとしたんだね
それからも同じように、その子は手がでたり、まわりの子どもへの攻撃が続いた。
実は、その手を出してしまう子には妹がいて、ある日、妹が同学年の子どもとのトラブルで泣かされるということがあった。

報告をしたとたんに親が激怒して、先方の複数の家庭にすごい剣幕で怒鳴り込んだ
けど、怒鳴り込まれた家庭の中には、兄から手を出されたり泣かされていた子どもの家庭もあったんだ。
怒鳴り込まれた方の親は当然納得がいかない。これまで何度もやられてきたのに、先方の親からは何の連絡もなかった。なのにこちらがやった時には猛烈に攻められたんだ。
怒鳴り込まれた親は怒鳴り込んだ親に、今までの不満をぶちまけたんだ。そこで話がかみ合わなくなった。

「そんなこと聞いてない」ってなっちゃったんだね
そうなったら非難の矛先は一気に指導員に向かった。「なんで今まで黙ってたんだ!!」って・・・。

修羅場っすね・・・
我々がよかれと思ってしたことが、自分たちに跳ね返ってきたんだよ。
今思うと、色々やり方が間違っていたよ。

誤解しないでほしいんだけど、指導員自信を守るために、伝えるべきか、伝えないべきか悩んだんじゃない
この時は、子どもにとってどうか、親にとってどうかを我々なりに考えて悩んだうえでの判断だったんだ
ありのままを伝えることが一番よいと思うけど、そうすることが子どもにとって不利益になる場合もある。
そんな時、私たち指導員は悩むんです。
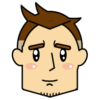
指導員も大変ですね・・・
何かあったら細かいことでも全て連絡して欲しいと言われたが

私が難しいと感じるのは、トラブルを起こした子どもの家庭への連絡ですね
私にもこんな経験があります。
繰り返し手を出してしまう子どものお母さんから、「細かいことでもいいので、全て教えて欲しいです」って言われたんです。
そのお母さんは、随分と悩んでいました。
だから、本当に細かいことまで伝えようとするとそれは数えきれないような話で、そこまで細かく伝えてしまうと、お母さんが倒れてしまうんじゃないかと心配で・・・。

忖度したんですね

そうね
その時は、伝える内容と伝えない内容を取捨選択したわ
この場合は、伝える相手である保護者がどれだけ受け止められるのかってことを、指導員として判断したんです。
毎日たくさんのトラブルがあったけど、先方の保護者に連絡する場合に限って、やった方のお母さんに連絡して、それ以外のことは伝えないようにしたんです。
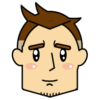
けど、親としては、子どもの事実をすべて把握しておきたいと思っていますよ
もっと親を信用してほしい

会長に質問ですが、息子さんの日々のトラブルを祖父母に逐一報告していますか?
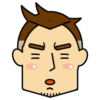
そんなことしないよ。
心配をかけるだけじゃないか

私の悩みは、その感覚に非常に近いと思います
全てを伝えないことは、伝える相手への配慮からです。
けど、私は「配慮」だと思ってトラブルを保護者に伝えなかったけど、それは「裏切り」や「保身」「事なかれ主義」と紙一重であるという思いで、胸がつぶれそうになりました。

伝えないことは、そんな批判を一身に背負う覚悟が必要なんです

同じように悩んだこと、僕にもたくさんあるよ
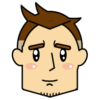
なんだか気の毒になってきました
指導員ってもっと気楽で単純な人たちだと思ってましたよ
伝え方の技術を磨くために
先ほど、私は、「殴る」という表現は、学童保育ではあまり使いたくないと言いました。
同じような理由で、「暴力」「いじめ」などの言葉も、その言葉自体が持つ印象が非常に強いため、使う時には注意をしています。

その言葉がどのような印象を与えるかということを意識して、言葉選びのセンスを身に付けたいものです
毎日の打ち合わせでは、指導員が前日の出来事などを伝えあいますが、事実に沿った報告になっているか?言葉の選び方は正しいか?伝わる印象はどうか?などについて、日頃からお互いの意見を交流しあいましょう。
そうやって指導員間で意見を言い合っていると、同じ指導員でも、これだけ受け止めの印象が違うということに気付き、伝え方の技術が向上していきます。

毎日の打ち合わせが訓練なんですね

そうだよ
プロなんだから打ち合わせから報告の仕方はこだわっていくんだ
事例報告や実践レポートなど、事実を文章化することも、伝え方の技術を高めるためには有効ですよ。
さいごに・・・

トラブルの際には、正確に事実を伝えることが、一番大切です
いつ、どこで、だれとだれが、どうなったか。事に至った経緯の説明もします。
そして、指導員がどのように対応したのか、これからどうしていきたいと思っているのか。
それら事実関係と指導員の思いを、適切な言葉で伝えること。
保護者の心情を思って、伝え方を調整することもありますが、そんな時にも、事実がねじ曲がってしまうような表現は、やはり避けるべきです。

保護者のためや子どものためを思うなら、事実は事実として伝えたうえで、心情面のフォローやアフターケアを考えていきましょう
配慮と事実関係がごちゃ混ぜになって、結果的に事実と違った伝わり方にならないように。
過去の私の失敗は、この点がよくわかっていなかったんです。

同時に、なんでもかんでも伝えればよいってわけでもありません
私は、指導員を続けてきた中で、そんな事例もたくさん経験してきました。

いつ伝えるのかが、今日でなくて1年後の方が良い場合もあるかもしれない
もし事実の一部や全部を伝えない場合には、なぜそれを今伝えないのか、という確固とした理由が必要です。
そしてその判断が個人の思いではなく、職場での議論を経た判断である必要は言うまでもありません。
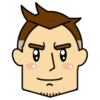
親はいつだって我が子のことを知りたいんだから
そのことだけは忘れないでくださいよ

「伝える」って奥が深すぎ~
今回の内容は、あくまでも私の考えです。他にも様々な考え方があるでしょう。
悩める指導員の皆さんの苦労に乾杯。
これからも、誠実に子ども達や保護者達とかかわっていきましょうね。










