今回は、保護者から、児童が骨折したことを告げられた時、職員としてどのような言葉がけをしたらよいのかについて考えてみたいと思います。
こんな連絡があった時の対応のポイントは?
- 子どもが新型コロナに感染した
- 保護者が新型コロナに感染した
- 職員が新型コロナに感染した
- 利用児童の身内に不幸があった時
- 職員の身内に不幸があった時
- 利用児童が骨折をした時
新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
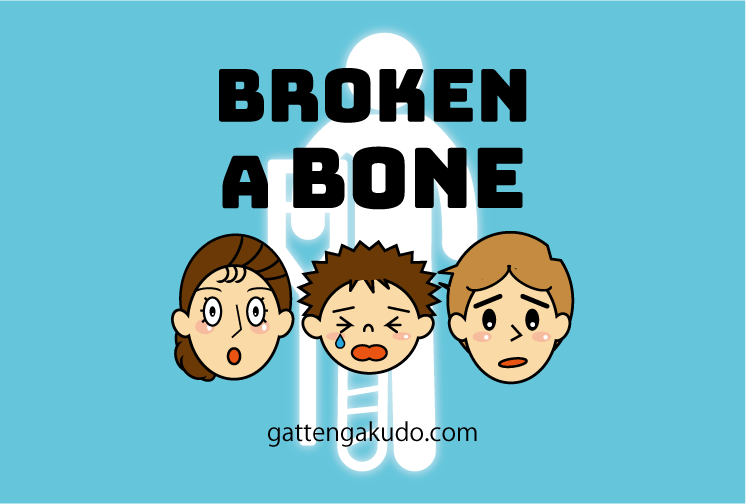
目次
利用児童が骨折した時は学童への「移動」が悩みの種に
ある日のがってん学童保育所。その電話のなり方はどこか不吉な響きでした。
嫌な連絡って、なんだかピピっとくることありませんか?

トゥルルル、トゥルルル・・・

はい!がってんです!

3年の武田です。実は昨日の日曜日、てつおが足首を骨折してしまいまして・・・。

え?え~!?

なので今日は受診のため学童をお休みします・・・。
体調不良や怪我と違って骨折?しかも足首??
こんな時、指導員が一番心配なことは・・・、
いやいや、落ち着けワタシ。てっちゃんの状態の確認が先決だ。

てっちゃん、大丈夫なんですか?

入院という程ではなかったし、昨日は家でゆっくり休んで元気にしはしているんですが。1か月は松葉杖の生活で、その後もしばらくは「装具」をつけることになるそうです。

元気と聞いて安心しましたが。
学校から学童への移動はどうしましょう?
うちの学童は小学校から子どもが歩いて15分ほどの距離があるから、子どもが骨折した時なんかは、「移動」が問題になるんです。
保護者にとっても気になる部分だと思い、こちらから切り出しました。

実はそれが悩みの種でして・・・。今週いっぱいは私も仕事を休もうと思っているんですが、その後のことは学童の先生とご相談させてほしいんです・・・。
朝の登校は、保護者の方で何とかやりくりをするとして、小学校から学童への移動となると、保護者にとっては「仕事を休む」という選択を迫られることになってしまいます。
働く保護者とその子どもたちの生活を支える学童保育としては、こういった非常事態においても、「一緒に考えていく」という姿勢が必要だと私は思っています。
施設として無理な対応はできない

・・・という状況です。

小学校へ毎日、てっちゃんのお迎えに行くとなると、職員体制の問題が・・・。
とはいえ、毎日学校から学童への移動の補助をするとなると、正直に言って厳しいところがあります。
特に今回は、松葉杖での移動ということで、通常の歩行より移動に時間がかかることになります。全体の子どもの安全を考えると安請け合いはできません。
保護者と職員で知恵をしぼって・・・

とにかく、こちらの状況もお母さんに率直にお伝えして、どんな方法があるかを考えてみよう。
最初の1週間はお母さんが仕事を休むとのことでしたので、その間に、その後のことを保護者と職員で相談することにしました。

自転車での送迎はどうですか?
それなら移動時間が短くなるのでこちらも協力しやすいと思います。

転倒が心配だわ。何かあって先生方に迷惑がかかってもいけないし・・・。
色々と相談する中で、保護者の方で、社会福祉協議会で「車いす」の無料貸し出しがあるとの情報をつかまれ、あたってみたようですが、今回のようなケースでは貸し出しはできないとのことでした。
結局、保護者と職員で一日交代で、学校まで迎えにいくということになりました。

できる限り協力をしたいと思いますが、職員体制上難しい時は早めにお伝えしますね・・・。

ありがとうございます。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。
学童での生活についてもしっかりと保護者と相談する
送迎の問題とは別に、限りあるスペースの中で、多くの子ども達が集団行動を行う学童保育の環境について、保護者に理解をしておいてもらう必要があると思いました。

ご存じのことと思いますが、学童にはたくさんの子どもが過ごしていますので、決して静かな環境ではありません。

そうですよね・・・。

まわりの子どもたちも、てっちゃんのために協力してくれると思いますよ。
これまでも、だれかが骨折をしたような時は、そのことを他の子どもたちにも伝え、まわりで暴れたりすることのないように、子ども達と話をしてきました。
怪我をした友達のことを気にかけてくれるような子もたくさんいました。しかし、子ども達が集団行動を行う場という点で、様々なリスクもあることを保護者に理解してもらうことは大切だと思います。

よくなるまでは、都合のつく日はできるだけお休みしますね。
回復期に気をつけたいこと
それから1か月半が経ち、てっちゃんの松葉づえがとれ、装具をしながらですが、自由に動き回ることができるようになりました。
そんあなある日、外遊びの様子を見に行くと

あ!てっちゃんがドッジボールに混ざっている!
びっくりして、てっちゃんをとめようとすると、

サッカーじゃなかったら大丈夫だよ!
と言い張るのです。お母さんからはそのようなことは聞いていないので、とにかく外遊びはやめて、室内で過ごさせることにしました。
お迎え時にお母さんに確認すると、

先週の受診では、まだ運動はできないと医師から言われています。
とのことでした。
回復期には、子どもの動きが活発になってくるので、逆に目が離せないようなこともあります。
保護者との連絡を密にして、現在の治療の進捗や医師からの指示等をしっかり伝えてもらうようにしましょう。
さいごに・・・
いかがだったでしょうか。
働く保護者や、その子どもの放課後の生活をサポートする学童保育では、このように骨折をした子どもを受け入れる場合もあります。
そのような時は、保護者と相談しながら、学童でどのような支援が可能かを考えていきます。
- 学童の施設環境や職員体制について理解してもらう
- 保護者の側からも協力をお願いする
- 治療の進捗について保護者から伝えてもらう
以上のことを大切にしながら、できるだけ安静に過ごせるよう配慮していきたいです。
ただし、無理な受け入れや安請け合いをして、治癒を遅らせるようなことはあってはならないことです。

子どものためにも、無理はしないこと。結果的には、その方が保護者からも信頼されることになるのではないでしょうか。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】保護者から新型コロナ感染の連絡を受けた時の対応「信頼と安心を育むとっさの受け答え①」
続きを見る
こちらもCHECK
-
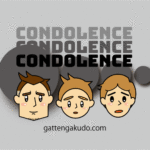
-
利用者や職員の身内に不幸があった時にかける言葉は?「信頼と安心を育むとっさの受け答え②」
続きを見る










