新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
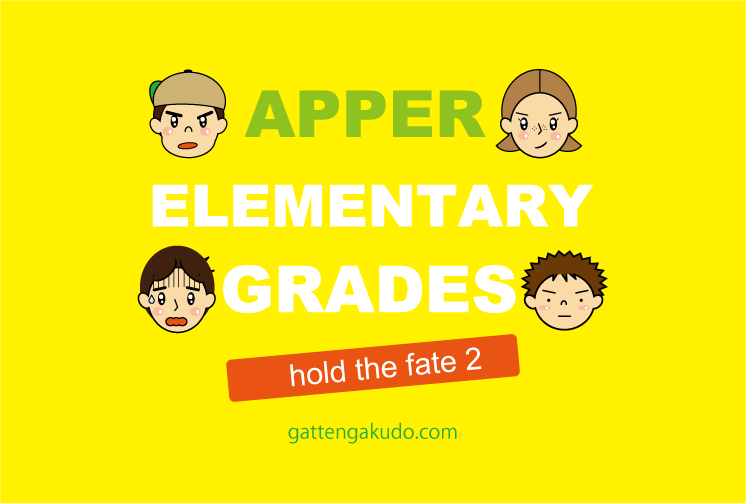
今回の記事は「後編」です。前編はこちらから。
こちらもCHECK
-
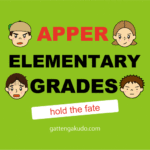
-
【学童保育】高学年保育の課題と取り組みを解説「高学年保育があなたの学童の命運を握る!」(前編)
続きを見る
目次
前回の反省・・・

ちょっと所長!そこに座ってください。

なんでしょう・・・

前回の記事で、「高学年にとっては学童が行きたい場所になっているかどうかが重要だ!」って言ってましたけど・・・
そんなのあたりまえじゃないですか!!
低学年にとっても高学年にとっても学童が「行きたい」と思える場所になるように、私は頑張っているんです!!
なにをえらそうに言っているんですか!!

す、すいません・・・
この記事の内容
- 高学年が「行きたくなる」場所であるために
- 高学年の発達段階
- 保護者の理解と協力を得る
- 高学年の自立・自治活動
- 高学年保育の年間計画
- 高学年保育の行事取り組み
- 高学年におすすめの活動や工夫
- さいごに・・・
高学年が「行きたくなる」場所であるために

高学年の子ども達にとって、学童がどんな場所なら「行きたい」と思えるでしょうか
私は次の3つの条件があることが、高学年が学童保育に通い続けるためには大切だと思います。
高学年が行きたい場所であるために
- 高学年の力を発揮できる活動内容
- 忙しい高学年がホッとできる場
- 高学年同士が仲間と過ごす時間
発達段階が大きく異なる、1年生と6年生が同じ活動内容というのは、やっぱり高学年にとっては物足りないでしょう。高学年としての力を発揮できる、高学年独自の活動を開発し定着させていくことが課題だと思います。
また、それらの活動を行ううえで、忘れてはいけないのが、高学年は低学年に比べて忙しいということです。高学年の子どもたちにとって、学童でホッとして過ごせる時間や指導員との関係は大切です。
そして、高学年の子どもたちが、学童で同じ年齢の仲間と過ごすことができること、これが最も大切だということを私は何度も思い知らされてきました。
指導員が工夫を凝らし時間をかけ、子どもたちと一緒に豊かな高学年の活動内容を築いたとしても、仲間の高学年1人が学童を辞めたことをきっかけに、数人の高学年が次々に学童を辞めてしまう、ということが起こるのです。

こんな時は、指導員としては力不足を感じて悔しいもんだよ

「来たくなかったら来なくていい」とか言ってたくせに・・・
それだけ、高学年の子どもたちにとって、仲間とのつながりは重要なんです。

低学年と高学年の間の「憧れ・憧れる関係」って大切でしょ
けど私は、まずは、高学年集団として、同年代の子どもたちの仲間関係があること。そして、高学年集団の中で、4年生と6年生の間に「憧れ・憧れられる関係」があるってことが大切なんだと思っているんです。

憧れの対象となる姿が、「すごい!」とか「かっこいい!」だけじゃなくて、子どもたちのいろんな姿を認めていけるようにしたいわ・・・
高学年の発達過程

高学年の発達過程についてもおさらいしておこうか
高学年の発達段階
【おおむね9歳~10歳】
- お金の役割等社会の仕組みについて理解し始める
- 遊びに必要な身体的技能が高まる
- 同年代の集団や仲間を好み、大人に頼らず活動しようとする
【おおむね11歳~12歳】
- ある程度、計画性のある生活を営めるようになる
- 大人からより一層自立的になる
- 少人数の仲間で「秘密の世界」共有する
- 友情が芽生え、個人的な関係を大切にするようになる
- 身体面において第2次性徴が見られ、思春期・青年期の発達的特徴が芽生える
「放課後児童クラブ運営指針より抜粋」
9歳から10歳頃は、ギャング・グループとして、一緒に好きな活動ができる仲間が中心だったのが、11歳以降の発達段階では、より内面的に共感し合える仲間関係を求めるようになってきます。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】「ギャングエイジ」と呼ばれる子どもたち
続きを見る
高学年保育の保護者協力
高学年がどのように学童で過ごすかは、低学年の保護者にとっては、いずれは我が子が通る道でもあります。
指導員と保護者で、1年生から6年生まで、子どもたちが学童保育でどのように過ごし、どのような体験をして、どのような成長を保障していくのかを考え、共有することも大切です。
豊かな高学年活動を行うためには、保護者協力も必要です。高学年活動を、低学年の保護者にも広く報告し、日頃からアピールして、高学年活動の良き理解者であり協力者である保護者を増やしていきましょう。

私は次の点を、高学年の保護者には、登録申請までにしっかりと考えてもらえるようお伝えしています
高学年の保護者へのお願い
- 子ども自身が学童に登録したいと思っていますか?子どもとしっかりと話し合ってください
- 高学年行事への協力をお願いします。高学年が豊かな学童生活を行うためには保護者の協力が必要です
- 毎週の高学年会議の日を大切にしてください
高学年の自治活動
高学年にとっての学童は、子どもの自律を促す場であり、仲間とともに自治活動を目指していく場であるという共通認識を指導員と保護者でもっておけるといいですね。
高学年生活の次には、中学校生活がやってきます。そのために、高学年の間に身につけておきたい力や、成長のイメージを話し合い、共有していきましょう。

3年生までの成長も大切です。その上に高学年生活があるのですから
日頃の、おやつや片付け・宿題などもそうですが、大人の援助を少なくして、自分たちで考え行っていけるように、その中で失敗や成功を通して子どもたちが成長していけるような、指導員のかかわりや保護者の見守りを大切にしましょう。
がってん学童の高学年活動の紹介
がってん学童で行っている「高学年行事」は、その企画や運営にあたっては、「自分たちで考え、自分たちで実現する」ことを目指して行います。

高学年集団の規模や活動内容は施設によって大きく違います
こうでないといけない、というものではなく、自分の施設の特色や環境を活かして、どのようなことができるのかを考えてみてくだださい。
がってん学童保育所の取り組みが、皆さんの参考になれば幸いです
高学年保育の年間予定

がってん学童の高学年活動の年間予定はこんな感じです
| 4月 | ・結成式 |
| 5月 | |
| 6月 | ・飯盒炊爨 |
| 7月 | ・高学年キャンプ |
| 8月 | ・夏祭り(お化け屋敷・ステージ発表) |
| 9月 | ・川遊び |
| 10月 | ・駄菓子屋さんごっこ |
| 11月 | ・バザー(駄菓子屋) |
| 12月 | ・ドッジボール大会 |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | ・春合宿 |

昨年は新型コロナウィルスのため、多くの行事が中止となってしまいました
そんな中でも、「子どもたちとしてはどうしたいのか?」「どうやったら実施できるのか?」を話し合い、高学年会議の結論と施設側(大人)の意見を突き合わせ、検討を重ねました。
結果として、やっぱり中止とせざるを得なかった行事や、形を変えて実施した行事、感染予防を考えながら予定通りの内容で実施した行事などがありました。
高学年の行事取り組み

がってん学童の高学年行事の内容をご紹介します!
結成式
高学年の子どもたちが、1年間の「やりたいこと」を話し合ったり、高学年としてのルールや目標を考えるための取り組みです。
一人ひとりの目標は、低学年の子どもたち全員の前で発表します。

低学年の人たちにいろんなことを教えてあげたいです!

高学年キャンプを頑張るぜ!

高学年会議で司会を頑張りま~す
この「決意表明」の場は、高学年の子どもたちが、新年度に、新たなステージに立ったという自覚と誇りを持てるようになるために行っています。
見守る低学年の子どもたちも興味津々です。
飯盒炊爨

キャンプに向けて、火起こしの練習をするんだぜ
夏休みのキャンプに向けて、近場の河原で、炊飯や野外調理をします。
班ごとに、メニューや役割分担を考え、当日は班のメンバーで協力して、調理や火起こしを行います。
高学年キャンプ

私はキャンプ行くために高学年学童に入ったんだよ!
6月頃から、行き先について話し合ったり、2泊3日のプログラムや野外調理のメニューを相談します。
キャンプ当日だけでなく、キャンプまでの話し合いや準備などの過程も含めて、高学年としての力を存分に発揮できる行事です。
参考までに、がってん学童の高学年キャンプのスケジュールです。プログラムは子どもたちが話し合うので、年によって変わりますが、大体このようになることが多いです。
キャンプスケジュール
【1日目】
- 集合・出発
- 移動
- キャンプ場到着
- お弁当
- 海水浴
- 夕食作り・夕食
- キャンプファイヤー
- ミーティング
【2日目】
- ミーティング
- 朝食作り
- 釣り
- 昼食(食堂)
- 海水浴
- 夕食作り・夕食
- 肝試し
- ミーティング
【3日目】
- ミーティング
- 朝食作り
- 片付け・自由時間
- 昼食(購入)
- キャンプ場出発
- 移動
- 学童に到着・解散
キャンプは、準備から当日の運営まで含めて大がかりな取り組みで、指導員の経験がいります。また、保護者協力も不可欠となります。

娘が高学年になったら、会話も少なくなって・・・
キャンプのおかげで、娘とかかわったり、娘の仲間関係を知ることができて、いい機会になっています
ちなみに、がってん学童では、低学年は、3年生をリーダーとして、1泊2日の親子キャンプを行っています。親子キャンプでの経験を活かして、高学年キャンプでは、仲間で協力し合い、できる限り子どもたちの力でキャンプ生活を営むことが目標です。
夏祭り(お化け屋敷・ステージ発表)
夏の終わりに開催する「夏祭り」は、保護者が模擬店を開いたり、3年生の子どもたちが太鼓の発表などを行います。

高学年でお化け屋敷をやるんだ
人気のコーナーが、高学年のお化け屋敷。お化け屋敷の企画をしたり、仮装をしたり、子どもたちも楽しみながら取り組んでいます。
ステージ発表では、女子がダンスを発表することが多いです。流行のグループのダンスの振り付けを夏休みの間に練習します。
川遊び

近所の川に、高学年だけで遊びにいくんだよ
バザー(駄菓子屋)

高学年が駄菓子屋さんや遊びのコーナーを開きます
学童のバザーの中で、高学年が自分たちで企画したお店を開きます。班ごとに分かれて、コーナーの内容をどうするのか、看板や準備物の作成などを協力して行います。
お店の収益は、低学年を含めた子どもたちのために、おもちゃや遊具・マンガを買うなど、高学年会議で使い道を話し合います。

原価や売り上げ、利益などを考える機会となる収益活動は、高学年にふさわしい活動だと思います。
昨年は、新型コロナウィルスの感染予防のため、不特定の来場者が訪れるバザーは中止となってしまいました。なので、高学年の子どもたちと話し合い、学童の低学年をお客さんにした、お店屋さんと遊びコーナーを高学年が開きました。
ドッジボール大会
地域の学童保育所が集まって開催するドッジボール大会の高学年の部に参加します。
春合宿
春合宿では、学童に宿泊します。金曜日の学校終了後から始まり、翌日土曜日の朝に解散します。
土曜日におでかけを企画することもあります。
夕食メニューは、各自食材を一品持ち寄って「闇鍋」をしたり、グループに分かれて、即席で作ります。夜の自由時間をたっぷりとります。

段ボールを集めて、自分が寝る「段ボールハウス」を作ったこともあったわね

真夜中まで起きてしゃべってたのが楽しかったわ
高学年におすすめの活動や工夫
高学年行事は準備が大変だし、ハードルが高いわ!という指導員の皆さんには、日常の中で取り組みやすい高学年取り組みをご紹介したいと思います。

低学年から見て、「高学年っていいな~」「ちょっとずるいな~」なんて思える取り組みがあってもいいですよね!
新しい学童のおもちゃを買った時は・・・
新しいボードゲームを買った時などは、まずは、高学年の子どもたちに遊んでもらいます。そして、帰りの会で低学年の子どもたちに新しいおもちゃの紹介をしてもらいます。高学年が低学年の子どもにゲームの遊び方やルールを教える自然な姿につながります。
高学年だけで公園に遊びに行く
高学年で行きたい場所を話し合い、「施設外活動」を行います。地域の公園や、神社などに遊びに行きます。
高学年が自分たちのおやつを注文する
1人あたり100円の金額設定で、総額も計算しながら2~3品の組み合わせを選び、自分たちでおやつを注文します。以前は毎日のおやつを高学年が注文していたこともありましたが、子どもの負担になることもあり、最近では、高学年が集まる「高学年会議」の日のおやつを、自分たちで選んでいます。
100円おやつ
子どもたちに人気の取り組みです。1人100円を持って、近くのコンビニや駄菓子屋に買い物に行きます。グループでお金を合わせて購入する子どもたちもいます。
高学年のおやつ作り
高学年でメニューを決めて、おやつ作りをします。ホットケーキなど、ホットプレートを使うおやつが簡単で人気です。
好きな本やマンガを買いに行く
学童の本やマンガを増やすときには、高学年に希望を聞いて購入します。長期休みに一緒に本屋まで選びに行くことも。
帰りの会の司会を高学年が担当する
帰りの会の司会進行は、高学年の役割です。他にも、入所式や修了式では、高学年の子どもに司会をお願いします。
こちらもCHECK
-
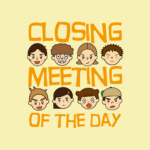
-
【学童保育】新年度の雰囲気作りは「帰りの会」から!
続きを見る
高学年会議
週に1日、高学年が集まる日として「高学年会議」を行います。行事に向けての話し合いだけでなく、高学年みんなで遊ぶ時間も大切にしています。
自転車での登所を認める
前回の記事でも触れましたが、がってん学童では、土曜日・夏休みは、高学年の子どもが学童まで自転車で来ることを認めています。中学校生活に向けて、地域で過ごす力を身につけてほしいからです。また、学童からのグループ帰りは3年生までとし、高学年は、自分たちで時間を決めて、数人の仲間と一緒に家に帰っています。17時のグループ帰りでは、来所時間が遅い高学年の子どもたちが、学童で過ごす時間がほとんどなくなってしまうからです。
高学年保護者懇談会
高学年の保護者が、子育ての悩みを出し合える場として、高学年の保護者を対象とした懇談会を開催します。思春期の子どもをもつ親には悩みや苦労がつきものです。別の家庭の悩みを聞いて、「あるある~!」と共感したり、親子のかかわりのヒントを得ることができる場は、子育て支援として大切な機会となります。指導員からも、高学年にポイントをしぼった話題の提供や、保護者と指導員で大切にしたいことを発信することができます。
新しい取り組みを行う時の注意

高学年に新しい役割を頼むときは、最初は「やりたい人」にやってもらう、というスタンスがいいですよ。そのうちみんながイメージをもてるようになったら、やりたい人が増えてきます。
〇〇君に見せ場を作ってあげたいな~とか、高学年全員にリーダー性を発揮してほしい、など、指導員の思いが先行してしまうと、役割を押し付けることになってしまいます。子どもたちと一緒に、「どんなことがやってみたい?」と話し合い、子どもが主体的に取り組むことを大事にしながら進めていってくださいね。

大事なことを言うのを忘れてた!
がってん学童保育所では、クラス担当とは別で、「高学年行事担当」の指導員をおいています。高学年会議や高学年行事の時は、年間を通じて、この担当指導員が活動をサポートしています。指導員の中では、高学年担当は結構人気なんですよ。
さいごに
いかがだったでしょうか。
今回は、がってん学童の高学年保育の取り組み内容を中心にお届けしました。
がってん学童では、2015年に、学童保育の対象が6年生までに拡大される以前の、2000年から、高学年保育がスタートしました。長年の積み重ねがあるため、子どもたちの中にも、「高学年になったら、こんなことやあんなことができるんだ」というイメージがあります。新しく高学年行事や取り組みを立ち上げることは大変なことですが、継続していく中で、子どもたちのイメージが膨らみ、新たなアイデアも出るようになっていきます。
高学年の子どもたちにとって、学童が「行きたい場所」であるかどうか
このことが、「あなたの学童の命運を握る!」というのが本稿のテーマです。
たった2割の高学年が、残り8割の低学年の子どもたちに与える影響は、良くも悪くも大きいのです。高学年の子どもたちが学童でどのように過ごしているのかを、低学年の子どもたちはしっかりと見ています。
高学年の子どもたちにとって学童が行きたい場所であるために、指導員の思い・子どもの意見・保護者の理解を深めながら、実践を重ねていきましょう。

最後に、「高学年保育」について学べる研修をご紹介しておきますね
高学年研究会(オンライン公開研究会)/一般財団法人日本学童保育士協会主催

高学年保育に悩みや課題意識のある指導員の皆さんはぜひ!










