遠足やプール・水遊び、宿泊を伴う施設外活動について、施設が実施する事前アンケートの内容や留意点、文例をまとめました。学童保育や放課後等デイサービス・保育園・小学校などの施設の先生方や、スポーツ少年団などで子どもの引率を行う指導者の方のご参考になれば幸いです。
新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
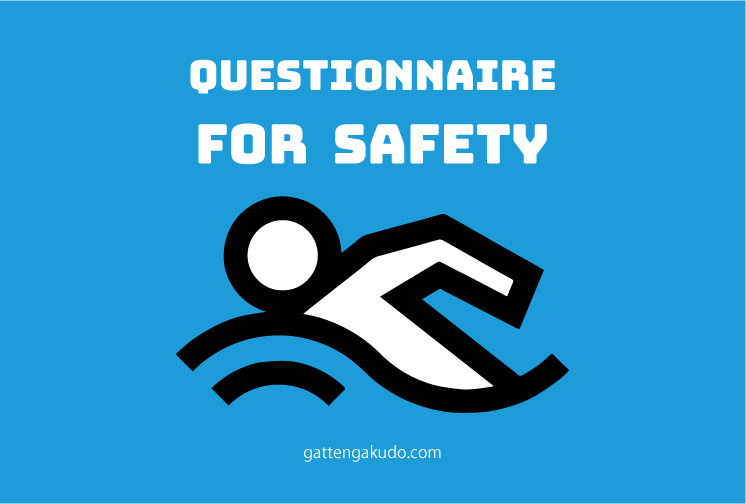
目次

こんにちは、がってん学童指導員のりえです。

新人指導員のたけしです!
夏休みには、遠足や合宿などの行事を予定している施設も多いのではないでしょうか。
今回は、それらの行事の前に保護者に提出してもらう「事前アンケート」の内容についてお伝えします。
施設外活動は、日常生活にない様々な活動を子どもたちが体験することができ、一人ひとりや子ども集団としての成長の機会となります。価値ある活動を継続していくためにも、計画や実施の段階で十分安全に配慮することが大切です。
施設外行事を行ううえで、どのようなアンケート内容が必要なのか一緒に確認していきましょう。
記事の最後にはPDF版のアンケート文例を掲載していますので、安全な行事運営のためにお役立てください。
当記事は、がってん学童所長の20年以上にわたる学童保育での小学生を対象とした引率経験をもとに書いています。学童保育以外の子どもに関わる施設の先生方や、スポーツ少年団などで子どもを引率する指導者の方々にも参考にしたいただけると幸いです。
こちらもCHECK
-
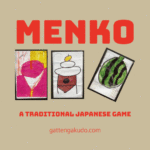
-
伝承遊び「めんこ」の作り方・遊び方【室内で思いっきり発散できて様々な楽しみ方ができる学童保育にもおススメの遊びです】
続きを見る
なぜ行事前のアンケートが必要なの?

なんで行事前のアンケートが必要なんですか?

施設外行事などでは、普段の生活にない活動が含まれる場合があるからよ。
職員は、入所時の調査票などにより、日常の子ども支援に必要な情報を保護者に提供してもらいますが、それらは基本的に、普段の施設内の活動に必要な情報です。
施設外行事では、交通機関での移動や宿泊・山登り・水遊びなど、様々な非日常の活動が含まれる場合があります。そのため、行事活動中の安全管理や子ども支援に必要な情報を追加で保護者から提供をしてもらうのです。
アンケートは、子どもの成長にともなって最新の情報を収集するために、毎年・行事ごとに行うのが基本です。
コロナ禍で、施設外行事の経験のない子どもたちや、引率経験のない職員が増えています。事前アンケートで一人ひとりの子どもの状況を職員が把握しておくことの重要性が高まっていると感じています。

コロナ禍で行事ができない期間が長かったから、久しぶりの行事は慎重に計画しましょう。

僕も行事の引率は今回が初めてです・・・。
アンケートの活用方法
アンケートを実施することで、保護者や子どもに施設側の安全意識を伝え、安心感を持って行事に参加してもらうことができます。しかし、アンケートをとるだけで安全な行事運営ができるわけではありません。
アンケートの回答を職員で共有するとともに、行事活動における以下のようなセクションで活用することが重要です。
- 計画段階
- 準備段階
- 直前の打ち合わせ
- 当日の引率
子どもの状況を事前に把握することで、職員は、計画段階から子どもの安全に配慮した取り組み内容を立案することができるようになります。
また、準備段階では、子どもの状況を把握しつつ、様々な事態をシュミレーションをして当日の引率に備えます。
行事中の安全は大人だけが守るわけではありません。子どもたちが自ら安全に気を付けて行動できるように、子ども向けの説明会などを実施することも大切です。
当日は、アンケート結果の必要な項目を活動中に確認しやすいよう一覧表にして、引率職員で共有します。
アンケート結果には、子どものプライベートにかかわる項目が含まれますので、取り扱いには細心の注意を払う必要があります。

アンケート結果を置き忘れたりしたら絶対だめだからね!

はい!
アンケートの締め切りの設定について
私の職場では、これまでアンケートは、行事の当日朝の集合時に提出してもらうことが常でした。
アンケート内容に「今朝の体調」という項目があったからです。
しかし、当日提出では、アンケートを忘れた家庭の対応が難しかったり、直前打ち合わせにアンケート回答を反映できないなどのデメリットがあります。そのため、当日の体調を「今週の体調」に改め、行事の3日前までに提出をお願いすることにしました。
計画や準備段階で必要な項目だけ、参加申し込み時にアンケートをとるという工夫もあります。詳しくは後に掲載している文例「参加申し込み書例」をご覧ください。

アンケートの締め切りは、行事ごとに職員で検討しています。
アンケートの内容①「遠足」

博物館や野外活動施設、山登りに行く場合などの事前アンケートの内容です。
【遠足】アンケート内容
- 今週の体調
- 車酔いの有無(酔い止め持参の有無)
- 飲み薬等
- 当日の健康管理で職員に知っておいてほしいこと
- その他職員に伝えておきたいこと
- 解散後の帰宅方法
- ※ハチに刺された経験の有無
- ※熱中症の経験の有無
これらは、施設外行事の基本的なアンケート項目です。
アンケート回答をもとに、車酔いをする子どもや通院中で食後に薬を飲む子どもなどに声をかけるなどの支援を行います。
集合や解散場所が施設以外となる場合は、帰宅方法も確認しておきましょう。

てっちゃん、お弁当後のお薬飲んだ?

忘れてた!

30分後に帰りのバスに乗るわよ。酔い止め薬を持ってきている人は、今のタイミングで飲んでね。

は~い!
ハチに刺された経験
山登りなどの自然活動の場合は、ハチに刺された経験の有無を聞いておきます。ハチ刺されは、2回目にアナフィラキシーショックのリスクが大きくなるからです。
万が一、行事活動中にハチに刺されてしまった場合に、職員が対応をとりやすくなります。(外部リンク:やまなしアレルギーNAVI)
ハチ刺されの経験のある子どもの場合、保護者から詳しい状況を聞き、場合によっては、行事の不参加を助言したり、行き先を変更することなどを検討します。

ポイズンリムーバー、救急セットに入ってるか確認してね。

了解です!

NEW エクストラクター ポイズンリムーバー 強力型 ハチ ブヨ ヤマビル などの虫刺され 毒吸引に
熱中症の経験の有無
暑い時期の施設外行事では、熱中症対策をすることが基本ですが、事前アンケートで、最近熱中症になったことがないかを確認しておきます。
なぜなら、一度熱中症にかかったら、しばらく再発の可能性が高くなると言われているからです。(外部リンク:健診会 東京メディカルクリニック)

このことは、以前行事に参加していただいた登山家の保護者の方からアドバイスをいただきました。
場合によっては、家庭と相談して受診してもらい、行事参加が可能か医師の判断を仰ぐことも大切です。
こちらもCHECK
-

-
「自分からお茶を飲まない子どもがいる?」学童保育の熱中症予防を通してみんなで考えたこと
続きを見る
アンケートの内容②「プール・水遊び」

子どもたちが大好きな水遊びですが、特にリスクの高い活動です。施設側には十分な安全対策が求められます。
【水遊び】アンケート内容
上記【遠足】アンケートの内容に、
- 泳げる距離
- 自然環境での水遊びの経験
- ライフジャケットを着て泳いだ経験
などの項目を活動内容に応じて付け加えます。
プールや川遊びなど水際の行事活動では、一人ひとりの子どもの泳力を職員が把握し、泳力に応じた指導・支援を行います。
具体的には、アンケート回答に基づき、泳ぎの得意な子どもと苦手な子どもを分けて、導入部分(最初の入水)を丁寧に行うということです。
また、引率職員は参加保護者などと協力して、
- 陸からの監視
- 水中で子どもと遊びながらの見守り
- 体調不良や怪我の対応をする担当
などを、役割分担を明確にして、お互いに連携しながら子どもの活動を見守ります。
自然環境の川や海での活動では、活動範囲の境界に大人が立ち、範囲外に子どもが出ないよう見守る役割をおくようにします。(川での活動であれば上流と下流に大人が立ち、その間で子どもたちが活動するなど)
また、川遊びでは、水かさが急に増える場合があります。活動開始時点での水位の目印をとっておき、活動中に水位の上昇がみられないか監視する役割もおきます。
万一水位の上昇がみられた時は、あらかじめ決めておいた合図をホイッスルで参加者に知らせ、一目散に高いところへ避難するように打ち合わせをしておきます。

これらのことは「水遊びの安全マニュアル」を策定し、見直しと改善を繰り返しています。
※プールや水遊びで、泳力など子どもの状況を把握しておくことは、安全対策の中の一部でしかありません。活動場所の選択や下見、当日の天候判断、大人の監視体制、事故の際の対応などをまとめたマニュアルを必ず作成します。
(参考サイト)
プール活動・水遊び安全マニュアル/大阪市
学校における児童生徒等に対する水泳指導等について/スポーツ庁
川遊びのルール 指導者用・大人用 安全管理基本編/天竜川総合学習館かわらんべ
子ども・保護者双方にアンケートをとる
私の職場で水遊びの事前アンケートを実施した時には、保護者に提出を依頼するとともに、子どもからも直接聴き取りを行いました。
理由は二つあります。
一つ目は、計画・準備段階にアンケート結果を取り入れるために、早い時点で子どもの泳力を把握したかったからです。そのため、子どもの聴き取りは当日の2週間ほど前に行いました。一方、保護者アンケートには直前の子どもの体調を記入してもらう必要があるため、提出期限を当日の5~3日前に設定しました。
二つ目の理由は、子どもと保護者で泳力の認識に違いがあるからです。昨年は泳げなかった子どもが、今年、小学校のプールの授業で泳げるようになった場合など、保護者が把握していないこともあります。逆に、保護者は「泳げる」としていても子どもは不安を感じている場合があるかもしれません。
実際のアンケート結果では、子どもの聴き取りでは「泳げる」となっていたのに保護者は「泳げない」と答えたケースが多くありました。

事前に把握した子どもの聴き取り結果と、直前の保護者のアンケートの両方を参考にします。
泳力の把握については、参加申し込み時にアンケートをとっておくという方法もあります。詳しくは後に掲載している文例「参加申し込み書例」をご覧ください。
泳げない気持ちに配慮して
泳力のアンケートを取る時に注意したことがあります。それは、「泳げない」ことにコンプレックスを感じている子どもの心情への配慮です。
- 泳げない
- 5メートルしか泳げない
- 15メートル泳げる
- 25メートル以上泳げる
というアンケートと、
- 泳いだことがない
- 5メートル泳いだことがある
- 10メートル泳いだことがある
- 15メートル泳いだことがある
- 25メートル以上泳いだことがある
というアンケートでは、子どもの立場からしたらどちらが「優しい」でしょうか。
安全管理上は、5メートルしか泳げない子は「泳げない」とみて見守る必要があります。しかし、本人は、「私は5メートルも泳げるようになったんだ!」と、誇らしい気持ちでいっぱいかもしれません。そういった気持ちに配慮して言葉遣いを選ぶことも大切ではないでしょうか。

けっこう細かいとこまで考えているんですね~。

泳ぎの苦手な子も安心して参加できて、子ども達みんなが楽しめることが私たちの目標だもの。
水遊びには、泳ぐこと以外の楽しさがたくさんあります。水に足をつけるだけで気持ちが良いですし、水際の生き物をつかまえたり綺麗な石を探したり、ダムを作ったり水鉄砲で遊んだり・・・。
泳力・経験に応じた目印を
泳力を把握したら、当日の指導や見守りのために、目印をつけるようにします。引率の職員や参加保護者で目印のことを共有し、全員の大人で協力して全員の子どもの安全を見守ります。
一番わかりやすい目印は、水泳帽の色分けです。
アームバンドやリボンなど、職場にあるもので代用してもよいでしょう。

泳ぎの苦手な子やちょっと怖いな~って思う子は、この「お助けバンド」をつけてね。先生たち特に注意して見守るようにするから。

うん!
このような目印の準備をするためにも、当日までに余裕をもったスケジュールで泳力の把握をしておくことが必要なのです。
泳げる子からも目を離さない
泳力の把握をしたあとに注意すべき点として、泳ぎの苦手な子どもより得意な子どもの方が危険な場合があるということです。
プールでの泳ぎに自信があるが、自然環境での水遊びの経験がない子どもなどは注意が必要です。プールと違い自然の川や海は、流れや深さ・水温などが急に変わったりするからです。自然環境での水遊びの場合は、泳力だけでなく、川や海での水遊びの経験の有無をアンケートで把握しておきましょう。
水に対する恐怖心がある子どもは無理をしません。水への恐怖心は本能的なものであり、とても大切な感覚です。子どもが水を怖いと思っていたら、「大丈夫だよ」と無理に励ますのではなく、「水が怖いって、人間にとってはとっても大事な気持ちなんだよ」と伝えてあげて欲しいです。
むしろ、泳ぎの達者な子どもや水に対する恐怖心の希薄な子どもの方が事故につながりやすいことを認識し、全体に目が行き届くようにしましょう。

水を怖いって思う気持ちは大事なんですね。
こちらもCHECK
-

-
【学童保育】「図解でわかりやすい」けがや体調不良・トラブルの対応と家庭への連絡について
続きを見る
ライフジャケットを着用する
私は、趣味でカヤックをしていることもあり、川で過ごすことが一般の人に比べて多くあります。カヤッカーにとってライフジャケットは、その名の通り「命を守る」アイテムです。
私の感覚として、水際で、ライフジャケットなしで大人一人が安全を守れる子どもの人数は一人です。
このことは、施設での引率だけでなく、ファミリーイベントの川遊びなどでも心にとめておいてほしいです。例えば保護者1人で子ども2人を川へ連れて行くことは(子どもの年齢や経験にもよるが)、その時点で大変危険であるという認識が必要です。
水遊びに子どもたちを連れて行く場合はライフジャケットは必須であり、複数の子どもを引率する場合は、全員がライフジャケットを着るようにします。
ライフジャケットは安全なだけでなく、泳ぎの苦手な子どもでも水に浮かんだり波に揺られたり、安心して水遊びを楽しめるというメリットもあります。

ライフジャケットも万能ではありません。製品自体の安全性や正しい装着方法を確認するとともに、全体に大人の目の行き届く見守り体制をとりましょう。
(外部リンク:海上保安庁「事故の際、ライフジャケットを着用していた場合の生存率は100%」)
下見の際の注意点
水遊び活動の下見で注意したいことは、見ただけではわからないことが多いということです。
下見の際には実際に職員が水に入るようにします。
特に自然の川や海では、大雨や増水で水底の状態が大きく変わります。昨年なかった岩が川底に出現したり、危険物が流れついて水中に潜んでいるかもしれません。
水に入ることで水温や川の深さ・流れの速さを体感することはとても大切です。
もちろん、当日も子どもが水に入る前に、まずは大人が入って安全確認をします。

明日の下見、水着を忘れないでね!

ガチで泳ぐんすね?
アンケートの内容③「宿泊活動」

キャンプや合宿などの宿泊行事ではプログラムに応じて、①・②の内容に加えて、以下の項目を付け加えるようにしています。
【宿泊活動】アンケート例
- 自宅以外での宿泊経験の有無
- 子どもだけでの宿泊経験の有無
- 夜尿の有無
- 生理の有無
- 平熱
- 飲み薬・塗り薬など
- 行事活動中の保護者連絡先
日帰りの行事と違い、宿泊活動では1泊2日や2泊3日など数日にわたって子どもの健康管理や精神的な支援を行います。活動時間が長い分、途中で体調を崩すリスクもありますので、必要な項目を保護者から情報提供してもらいます。
高学年であっても夜尿をする子は珍しくありません。保護者や子ども本人と打ち合わせをして対策を相談します。
また、高学年の子どもを対象とする宿泊活動については、生理の有無を確認しておきます。
行事活動中に体調不良となった場合には、迎えに来てもらうことをあらかじめ保護者に伝えておき、行事期間中に必ず連絡のとれる連絡先を聞いておきます。
事前アンケートの文例

これまでご紹介したアンケート内容について、実際の書式をダウンロードして確認していただけます。
アンケートや参加申込書を作成の際にはこれらの文例を参考にしていだけると幸いです。
①遠足の事前アンケート文例
②水遊びの事前アンケート文例
③宿泊活動の事前アンケート文例
参加申込時のアンケート文例
さいごに(事後アンケートについて)

いかがでしたか?

はい!しっかりアンケートをとって、安全に気を付けたいと思いました!!
私たちの取り組みが、皆さんの参考になればとても嬉しいです。
今回の記事の内容やアンケート文例については、そのまま使うのではなく、皆さんの職場の施設特性や子どもの年齢などによって手を加え、より良いものにしてくださいね。

さいごに、「事後アンケート」について触れておきます。
事後アンケートとは、行事活動の終了後に、参加児童の家庭から今回の取り組み内容を評価してもらうアンケートです。
行事が無事に終わった時には、職員への労いや子どもの楽しかった感想や保護者の感謝の気持ちなどがつづられるでしょう。
しかし、職員が知りたいことはそれだけではありません。
- 今回の安全対策はどうだったか?
- 子どもへの支援はどうだったか?
- 保護者が課題に感じたことはなかったか?
職員間の振り返りや子どもの感想とあわせて、これらの意見を家庭から収集し、次回の取り組みに活かしましょう。当日参加してくれた保護者や家庭で子どもの無事を願っていた保護者など、職員とはまた違う目線での意見はとても貴重です。
事後アンケートの内容
- 今回の行事はお子様は楽しめていましたか?
- お子様は安心して参加することができていましたか?
- 職員の安全対策はどうでしたか?
- 活動中のお子様への支援はどうでしたか?
- 事前の説明はわかりやすいものでしたか?
- 持ち物や準備物に不足はありませんでしたか?
- その他お気づきのことや改善点はありませんか?
事後アンケートは、匿名でかまいません。Googleフォーム等を活用するのもよいと思います。

アンケートへのご協力ありがとうございました。次回取り組みの参考とさせていただきます。
(おわり)










