新着記事
学童保育指導員になりたいないなら
スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし?
無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!
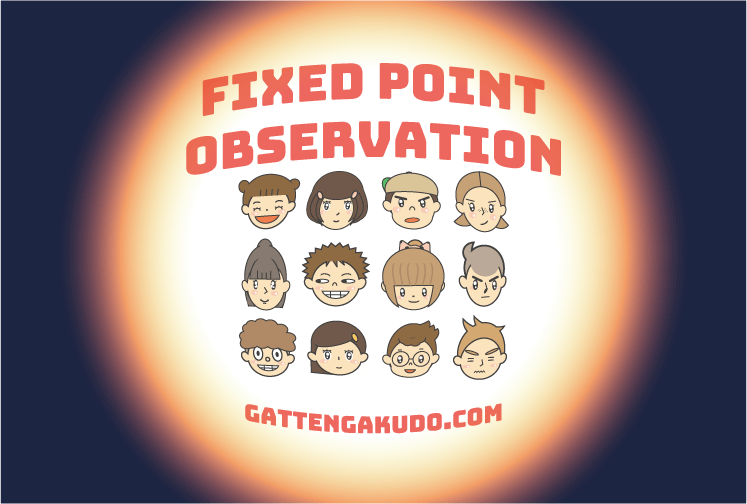
この記事は3分で読めます。

夏休み保育お疲れさまでした。

お疲れ様でした。

お疲れっす。
今年度も、9月を終えると折り返し地点。新年度保育からの夏休み保育で、ガンガンに頑張って来た指導員の皆さんも、少しペースダウンしてみましょう。
そうすることで新しい気づきがあるかもしれません。
今回は、夏休み明けに大切にしたい、子どもの変化を観察する「定点観測」について書きたいと思います。
目次
4月からの一人ひとりの変化を感じよう

たけし先生、これまで子ども達と一緒に過ごしてきたわけだけど、4月と比べて、一人ひとりの子どもがどんなふうに成長したか言えるかい?

え?

たけし先生は、4月から子ども達を見てきたわけだよね。
自分のクラスの40人の子ども達の一人ひとりが、4月と比べてどんな風に変化したか言えるかい?

え~っと・・・

もしそれが言えないようなら、9月に子ども達をじっくり観察してみるといいよ。
1人ひとりの成長を語れるようになること。
それがたけし先生の9月の目標だね!
私たちの仕事は、学童保育の生活を通じて、子ども達の成長を支援することです。
4月から、5か月間を学童で過ごした子どもたちの変化を観察し記録すること、そのことを通して、私たちが行ってきた育成支援の成果と課題を明らかにすること、年度折り返し地点の9月だからこそ、そんな取り組みを大切にしたいと思います。
子どもの様子を「定点観測」するということ

1年の中で、特に注意深く子どもの様子を観察したい時期があるよ。
子どもたちは、1年の中で行きつ戻りつ、絶え間なく成長しています。私たちは、日々の生活や遊びの中で、そんな「ふとした子どもの変化を」キャッチします。
それとは別に、「時期を決めて」子どもの様子を観察し記録するのが「定点観測」です。
- 入学や進級がある4月
- 連休明け、授業が本格化する5月
- 仲間と濃密に過ごした夏休み明けの9月
- 遊びが拡がる秋、11月
- 年度のまとめの時期である1~3月
これらの時期に、少し立ち止まって、職員間で、子どもたち一人ひとりの「今」を出し合い記録します。
放課後児童クラブ運営指針第3章の中の「育成支援に含まれる業務」には、「日々の子どもの様子や育成支援内容を記録する」と記述されています。
ただ、年間を通じて漠然と、業務的に記録を蓄積するのではなく、以前の記録をもとに、一人ひとりの子どもにスポットを当てて、「当時」と「今」の間にどのような変化や成長があるのかを明らかにしようという取り組みが大切だと思います。
職員によって見ている「子どもの姿」が違う

こないだ、てっちゃんがね・・・
事務室にいる私のところへやってきて、

トイレットペーパーちょうだい。
って私に言ったの。「なんに使うの?」って聞いたら、

かっけーがトイレでう〇こしててさ、紙がないからとってきてほしいって・・・
って言ったんだ。なんか私てっちゃんのこと見直しちゃった。

いつも調子乗りのてっちゃんでしょ?友達が困っている時に、ふざけないであんなふうに行動できるなんて。

あのてっちゃんが??

僕も意外に思うよ。
職員が見ている変化や成長を、お互いに出し合い、交流することで、それぞれの職員の視点から、自分の知らない子どもの一面に気付き学ぶことができます。
児童名簿を囲んで、職員一同で、順番に子ども一人ひとりの様子を出し合ってみましょう。
「成長」が感じられない時は・・・

・・・子どもの成長が見えない、わからない・・・。
「定点観測」で子どもの変化が感じられないのは、その子とのかかわりが非常に少ないというサインです。そんな時は、9月の1か月の中で、かかわりを増やしたり、特に念入りに様子を観察するようにします。
かかわりが少ないということの他にも、成長が感じられない原因があるとしたら、それは次のようなことかもしれません。
「こうあるべきだ」という職員の思いが強すぎるのかもしれない

「成長」って言葉のせいかもしれないけど、「できなかったことができるようになる」みたいな変化だけを見ようとしてないかい?

はい?

劇的なシーンというより、平凡な日常の中にこそ、子どもたちの変化や成長があると思うの。
例えば「けん玉の技ができるようになった」というのはわかりやすいけど、「全員がけん玉ができないといけない」なんて思っちゃったりしたら、それ以外の成長や変化が感じられなくなってしまうかもしれない。
芽が出たり花が咲いたりするのはドラマチックだけど、それ以外の多くの時間、植物は、少しずつ根をはり茎を伸ばしているの。
そういう些細な変化は、大人が「こうあるべきだ」という思いが強すぎると見えにくくなるものなの。
私がキャッチしたいのは、一人ひとりの子どもが「自分らしさ」を発揮した瞬間なんだ。
「疲れすぎていている」せいかもしれない

たけし先生、家でゆっくり休めてる?

え?

4月から大健闘だったからね、9月は自分のことをたっぷり労わってあげるんだよ
子どもの変化が見えにくくなる原因は、自分が「とても疲れている」からかもしれません。
人間は、疲れている時には、まわりの様々なことを否定的にとらえてしまうものです。逆に、気力が充実している時には、小さなことでも前向きにとらえることができるようになります。
夏休み保育で、疲れた心と体を自分自身で気遣うことも忘れないでください。

年度後半戦に向けて、9月はゆっくり休むことも大切にしようね。

はい!










